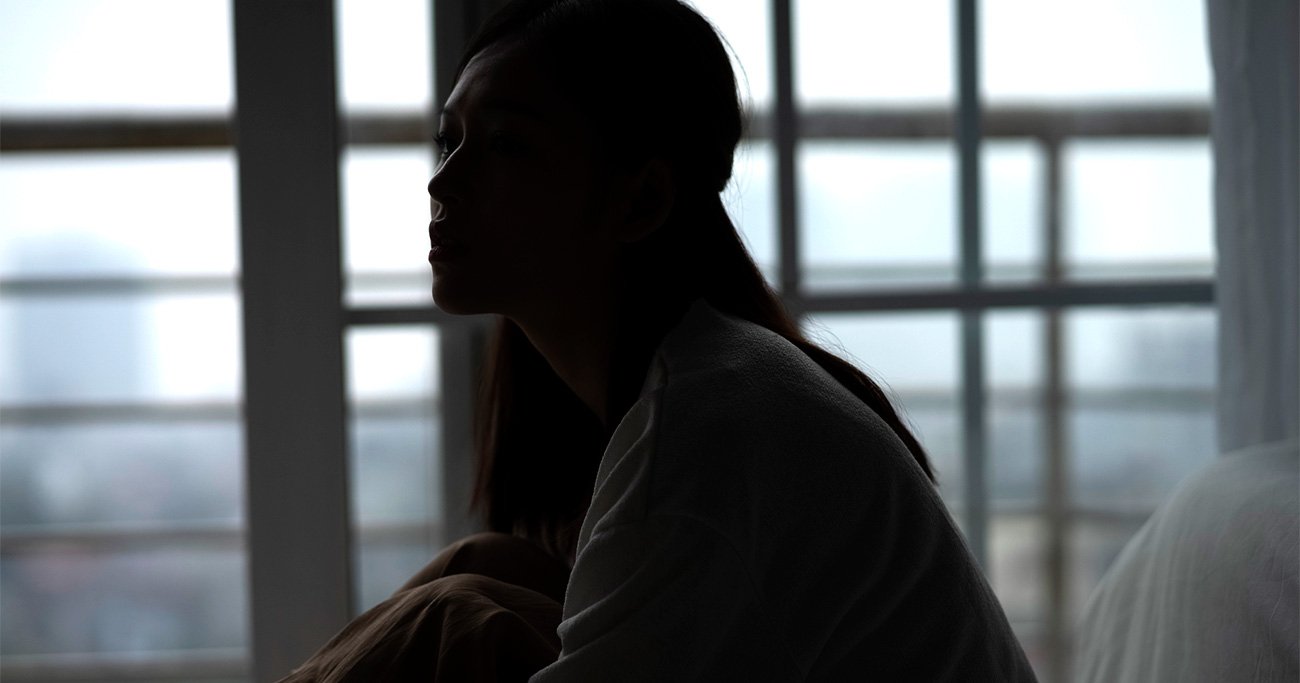 芸能人から一般人まで、なぜ自殺の連鎖が起きているように見えるのか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
芸能人から一般人まで、なぜ自殺の連鎖が起きているように見えるのか(写真はイメージです) Photo:PIXTA
竹内結子さんまで……
なぜ著名人の自殺が相次ぐのか
芸能界で自殺が相次いでいる。5月23日に、恋愛リアリティショー番組『テラスハウス』(フジテレビ系)に出演していた、プロレスラーの木村花さん(享年22)が自殺した。新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、非常事態宣言が出されていた時期であり、国民が外出自粛を求められていたタイミングでもあった。コロナ禍での孤立感により、SNSに時間を費やし、誹謗中傷を気にしてしまう雰囲気もあった。木村さんの自殺を機に、ネット上における名誉毀損が、社会的な課題として国会でも議論された。
この時期は、朝や昼のワイドショーから夕方や夜のニュースまで、毎日のように、新型コロナウイルス関連の報道がなされていた。「感染者が何人いるのか」「どの県で感染者が出たのか」「クラスターがどこで発生したのか」というニュースばかりが流された印象だ。
学校は大学を含めて休校やオンライン授業となり、特に新入生は同級生の友達ができない状況が続いた。この頃、筆者が別件の取材で話を聞いた女性の子どもが小学1年生で、「担任は○○先生なんだ。でも、どんな人かわからないし、友達もまだいない」などと話していた。この子どもの言葉は、当時の若者の孤立状況の1つを示していた。
続いて、鷹野日南さん(享年20)が7月10日に、三浦春馬さん(享年30)が7月18日に、芦名星さん(享年36)が9月14日に、藤木孝さん(享年80)が9月20日に自殺した。中でも世間に衝撃を与えたのが、国民的女優の1人であった竹内結子さん(享年40)までもが、9月27日に自殺したことだ。三浦さんと芦名さん、藤木さんは、ドラマ『ブラッディ・マンデイ シーズン2』(TBS系)で、三浦と竹内は映画『コンフィデンスマンJP』シリーズで共演していた。そのため、SNSなどでは、「共演者の死を意識したことによる自殺の連鎖か?」とも騒がれた。
コロナ禍で日本社会にかつてない閉塞感が漂う中、足もとで「自殺」が増えていると言われる。その象徴として芸能人の自殺が続き、さらにその報道に触発されたのか、一般人の間でも「後追い自殺」と思われる現象が起きている。そんな仮説を頭の片隅に置きながら、足もとの傾向と取り組むべき課題を分析しよう。







