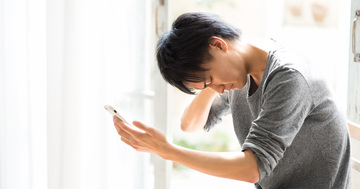スマホの使用が脳に与える影響とは? Photo:PIXTA
スマホの使用が脳に与える影響とは? Photo:PIXTA
視野を広げるきっかけとなる書籍をビジネスパーソン向けに厳選し、ダイジェストにして配信する「SERENDIP(セレンディップ)」。この連載では、経営層・管理層の新たな発想のきっかけになる書籍を、SERENDIP編集部のチーフ・エディターである吉川清史が豊富な読書量と取材経験などからレビューします。
スマホ依存が
脳に与える影響とは
経験したことはないのだが、子育てはたいへんな仕事だ。子どもが3歳から5歳くらいの幼児の場合、四六時中、親が相手をしてあげられればいいのだが、他の家事や仕事などで、とてもそんな余裕のある親は少ないだろう。
そのため、「何か」に子守をしてもらうことになる。20~30年前なら、「アンパンマン」やら「きかんしゃトーマス」やらのビデオを、テレビ画面で繰り返し見せておく親が多かった。今はそれが、iPadなどのタブレットやスマートフォンに取って代わっている。
会社の同僚で5歳の娘さんの子育て真っ最中の女性がいるので、聞いてみた。最近になって、iPadを与えたそうだ。
彼女は、娘さんに45分単位で時間を区切って見せているのだが、かなり集中して、YouTube動画などを見続けたり、ゲームをプレーしたりするのだという。「ご飯だよー」と声をかけても、「待ってー」と言ってiPadを離さない。自分で画面をタッチして動画を選び、「おもちゃを開封する動画」や「おやつを食べる動画」などを何度も見ている。
娘さんは自分から「ゆーちゅーぶ見たい」「げーむしたい」とせがむというから、iPadには「知的好奇心を育てる」という良い面はあるものの、多少なりとも中毒性があるという事実は否めないだろう。
そのiPadを世に送り出したスティーブ・ジョブズ氏は、自分の子どもにiPadを触らせる時間を、厳しく制限していたというから驚きだ。ビル・ゲイツ氏も、子どもが14歳になるまでスマホを与えなかったそうだ。