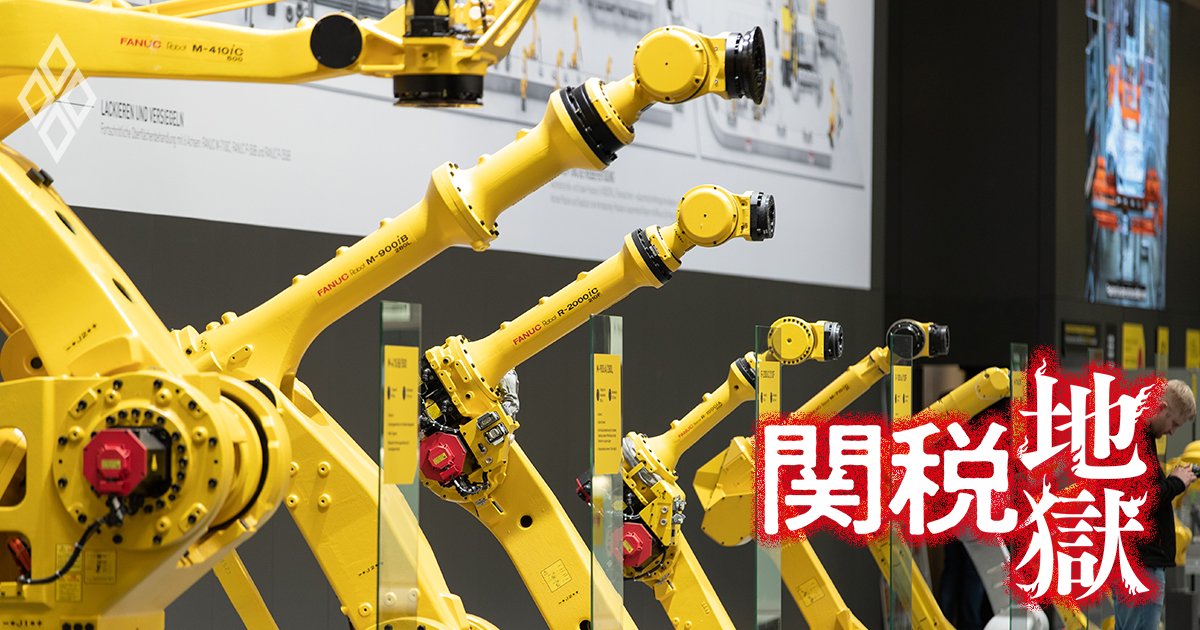Photo:Kevin Frayer/gettyimages
Photo:Kevin Frayer/gettyimages
7月1日、中国共産党創立100周年の祝賀行事が行われた。7万人が動員された天安門広場を見下ろして、習近平国家主席は楼上で1時間超にわたる演説を行った。「マスゲーム」的な演出は、世界に求心力を誇示するかのようだった。習近平氏は、建国の父として神格化された毛沢東に自らを重ねているといわれるが、この祝賀行事で明らかになったのは、むしろ中国の国家指導者としてのカリスマ性の低下だった。(ジャーナリスト 姫田小夏)
100万人が集まることができる天安門広場
今回の式典は「異例」だった!?
7月1日の祝賀行事で習近平国家主席は、毛沢東(1893~1976年)をイメージさせるマオカラー(立襟)の人民服に身を包み60分余の演説を行った。1949年の建国宣言で、毛沢東も天安門の楼上から演説したが、同じようにして習氏がこの楼上から演説をしたことは「毛沢東の後継者を誇示する意図がある」ともいわれている。
中国の国民もまた、習氏を毛沢東に重ねている。
集団指導体制を標榜した胡錦涛時代(2002~2012年)とは打って変わって、国民に対する抑圧的、監視的な統治スタイルを導入するなど、習氏の政策の随所に、毛沢東のような“絶対的カリスマ指導者”になろうとする試みが見られるためだ。中国現代政治の専門家である愛知大学名誉教授の加々美光行氏も「習氏は明らかに毛沢東を意識している」と話す。
北京の中心に位置する天安門広場は、南北880メートル、東西500メートル、面積44万平方メートル(東京の駒沢オリンピック公園と同程度の面積)を持つ。明・清時代の王宮「紫禁城」の第一門である天安門前の広場は、100万人余りが集会できるといわれている。
1949年10月1日には毛沢東による中華人民共和国の建国宣言が、文化大革命(以下文革、1966~76年)中の1966年夏には紅衛兵大会が行われた。また1976年4月5日の第1次天安門事件、1989年6月4日の第2次天安門事件も天安門広場が舞台となり、その「集会」には、50万人、100万人規模の群衆が集まった。
(筆者注:「紅衛兵」とは、文革時に毛沢東によって動員された全国的な学生運動およびその運動家)
そんな歴史を刻む天安門広場だが、今回の中国共産党創立100周年の祝賀行事は、「集会」としては“異例”のものとなった。