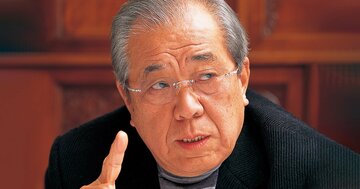プロフェッショナリズムは
意外に理解されにくい
もともと落合は旧態依然とした野球の世界にもなじめない選手だった。高校の野球部を辞め、大学を中退し、臨時工として工場で配電盤を組み立てながら野球をしていたこともある。個を圧殺し、制裁もいとわない旧来の野球とは相性が悪かった。自分が選手だったころには、星野監督のやり方に真っ向から反対して罰金を科せられたこともある。そのころの星野監督のチームは、
ベテランを放出し、高卒の若い選手に出場機会を与える中でチームを自分色に染めていった。ミスや怠慢プレーには鉄拳制裁、罰金という厳罰主義を打ち出す一方で、乱闘になれば真っ先にベンチを飛び出して選手を守った。ミスした者にはその翌日にチャンスを与えた。鉄の掟の下で血の結束を生み出す。(『嫌われた監督』より)
親分子分の組織運営方法である。好きな人には良いかもしれないが、これでは自立した個は生まれない。落合が試した方法は、個々人に徹底的なプロフェッショナリズムを求めることであり、8年間に4度のリーグ優勝、すべてでAクラスというすごい結果を出した。しかし、社会にも親会社にもその方法は理解されなかった。そして優勝したシーズンに首を切られた。さらに、これだけ高い成績を収めた監督でありながら、その後一度も他のチームを含めて監督をしたことがない。結果が出ても、嫌われる存在は、組織社会ではなかなか求められないのである。
このように見ていくと、新庄も落合も極めて高いプロフェッショナリズムに立脚しており、極めてまともで普通である。にもかかわらず、彼らが異端であるように映るのがわれわれの社会である。新庄に対する過大な期待も、落合に対する過小な評価も、元はといえば、契約とプロフェッショナリズムを理解できないわれわれの精神構造から生まれた同根のものなのである。
昨今日本企業ではジョブ型の導入が流行している。どの程度本気なのかは知らないが、本気だとしたら、会社と労働者の対等でシビアな契約を旧来の日本型組織に採り入れることになる。ジョブ型自体が悪いということではなく、今回述べた二人の監督のプロフェッショナリズムが奇抜で奇異なものに見えているうちは、到底こうした制度を日本企業が主体的に運用できるとは思えないのである。
◆参考文献
『嫌われた監督 落合博満は中日をどう変えたのか』 文藝春秋 鈴木忠平著
『落合博満 バッティングの理屈』 ダイヤモンド社 落合博満著
(プリンシプル・コンサルティング・グループ株式会社 代表取締役 秋山 進、構成/ライター 奥田由意)