NPOは全国規模では採算が合わない
新たなビジネスモデルの構築が必要
 Photo by H.K.
Photo by H.K.
日本で組織的なボランティアが活発化したきっかけは、1995年に起きた阪神淡路大震災だ。そしてその3年後に(任意団体が法人格を取得できるよう)NPO法(特定非営利活動促進法)が発足した。しかし、NPOというのは全国規模では採算が合わないのが現状だ。
そして日本では、「貧しい子どもを救う」以外の活動には寄付はなかなか集まらない。かつては多くのNPOが設立されていたが、今では起業がほとんどだ。「NPOの助成は基本は単年度。しかし企業には中期計画がある。それに対して予算を付けていく形でなければ、大きな投資ができない」とある会社員。
「あなたのいばしょ」のように、難易度が高い活動で、それでいて普遍性を持たせようとすると、非営利セクターでないと難しい。しかしその運営費は、これまでは相談員が支払う研修費用でまかなってきた。
田原氏は、「助成金に頼る運営は、サステナブルでない。NPOも売り上げの上限をなくし、きちんと稼いで税金を納めればいい。ボランティアをビジネスにするという流れもある」と見解を述べる。
大空氏は今後、営利事業を運営し、その利益をNPO活動に充てることを考えているという。「たとえば1万円出せば救急車がより早く来るというようなことは、あってはならない」。ビジネスセクターで生まれた資金を、非営利セクターへ送り込むビジネスモデルをつくり、NPOの制度を変えたいと大空氏は意気込む。
会場から質問が出た。「ビジネスの利益を投じてまでNPOを運営するのではなく、行政側に対策を施してもらえるように働きかければいいのでは?」。これに対し、「『あなたのいばしょ』では、海外に住む日本人相談員が時差を利用し、夜間の相談に対応している。このような24時間対応は、午前9時〜午後5時の勤務を基本とする行政が行うことはできない」と大空氏。
「非営利セクターも高齢化している。もっと若者にカジュアルに参加してもらい、相談者の受け皿になってもらいたい。若者の自殺を見過ごすのはシンプルにいやだという感覚もあるし、第一、相談を受けるのは楽しいこと。毎日1500人から相談がきて、相談者が『明日も生きてみたい』『人生で初めて肯定された』と言ってくれる。それが私たちの自己肯定感にもつながっている。『自分のためにやっている』という感覚でかまわないと思う。いわばエゴ。エゴだからいけない、と考える必要はない」(大空氏)
ある男子学生が手を挙げる。「生き死にに関わるような孤独に陥っている人は、人と関わること自体がしんどいのだと思う。そのような人に対し、『依存先をたくさん持て』というのは厳しいのではないだろうか」。
大空氏が答える。「複数の依存先を持つように働きかけるのは、自殺願望が比較的、軽度の人たちに対して。重度の人に対しては『アウトリーチ』を重視している。蜘蛛の糸(芥川龍之介の小説『蜘蛛の糸』にある、お釈迦様が天から垂らす救いの糸)をできるだけたくさん垂らして、どれかひとつでもいいので捕まってもらう」。
2017年、SNSで自殺願望を持った少女たち9人に、ある男が「一緒に死のう」と声をかけて、少女たちを殺害する事件があった。自殺願望を持つ者に犯罪者が接するよりも早く、地域社会や非営利セクターが接することが必要だ。「あなたのいばしょ」も、たとえばTwitterでそのような兆候を捉えるしくみの導入だったりと、積極的に対策に取り組んでいるという。
情報や経済の格差が広がるなかで
多様性をいかに担保するか
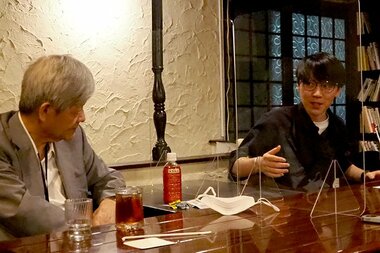 Photo by H.K.
Photo by H.K.
最後に運営側から質問が投げかけられた。「『田原カフェ』が、社会問題について自由に語り合いたいという意思を持つ人たちの集まりで終わるのではなく、もっと外側の人たちへメッセージを届けていくにはどうすればいいか」。
「この場は、個性としての多様性はあるが、参加者の多くが大学生や大学院生で、属性は多様とはいえない。属性の多様性を広げるために、たとえば『子ども食堂』(地域で子どもたちなどへ食事を提供する社会活動)内で田原カフェをやってみるといいと思う。自分も複雑な家庭環境で、子ども食堂にいる子たちと同じような境遇にいた」と大空氏。
「頭のいい人たちばかりが集まって語り合うのではなく、そういう人たちがなかなか日常で出会う機会の少ない、学歴がなく、生活が厳しい経験をしている人と、ぜひ対話や議論をしてみてほしい。選挙前に『選挙に行こう』というツイートがあふれる。意識の高い、余裕のある若者には有効な呼びかけかもしれないが、『出所したばかりで今日からどう生活していけばいいか』と悩む若者に同じことを言えるだろうか。多様な属性の人たちと対峙したときに、新たな感覚に気づくはずだ」
さまざまな論点が出た今回の田原カフェ。参加者たちが社会問題に関心を持ち、真摯に問題と向き合いつつ、このような対話会をさらに一歩進めるためには、どのように多様性を担保するか。そして、どのように外に意識を向け、インプットを社会へ波及させていけばよいのか。
このようなモヤモヤや歯がゆさを感じ、課題を認識することもまた、次へ進む第一歩なのかもしれない。







