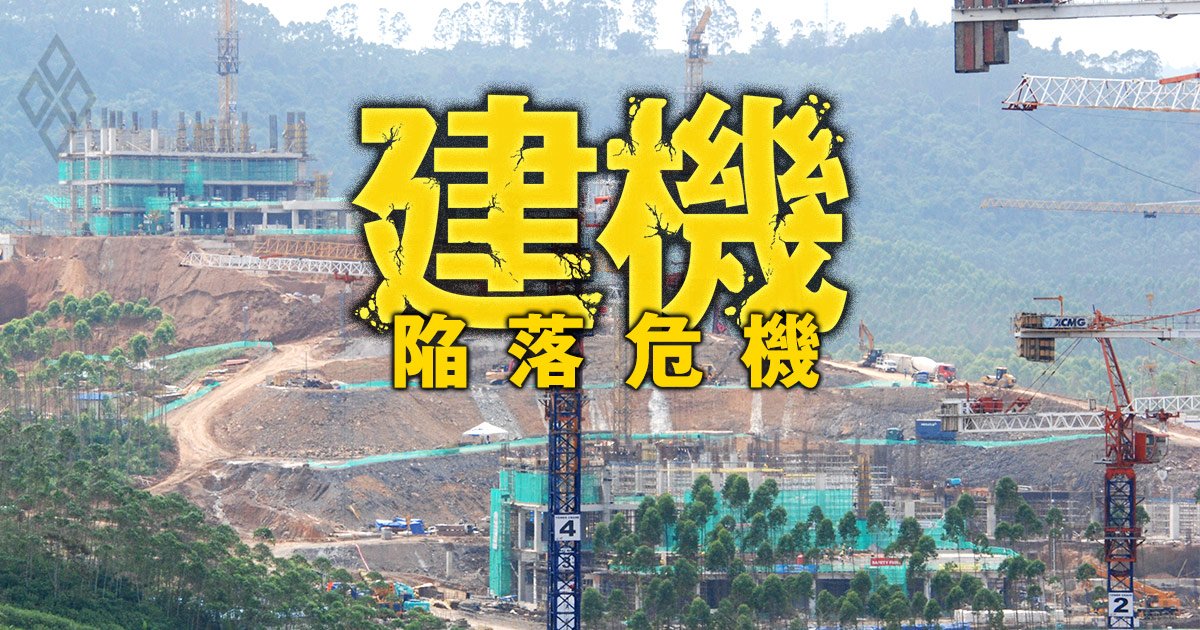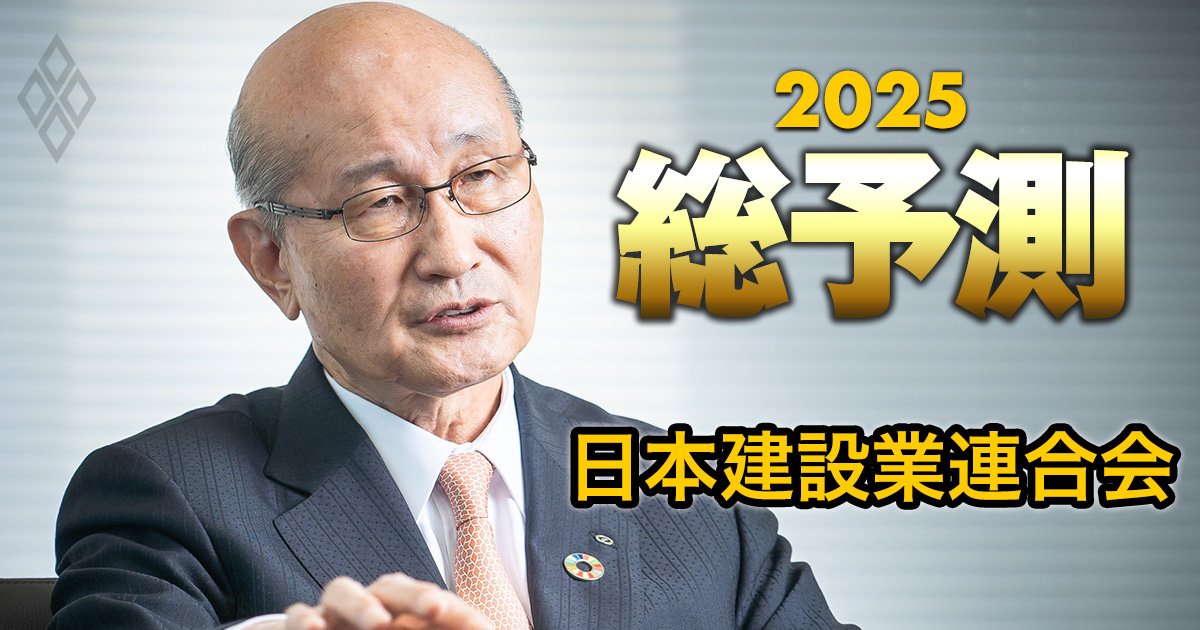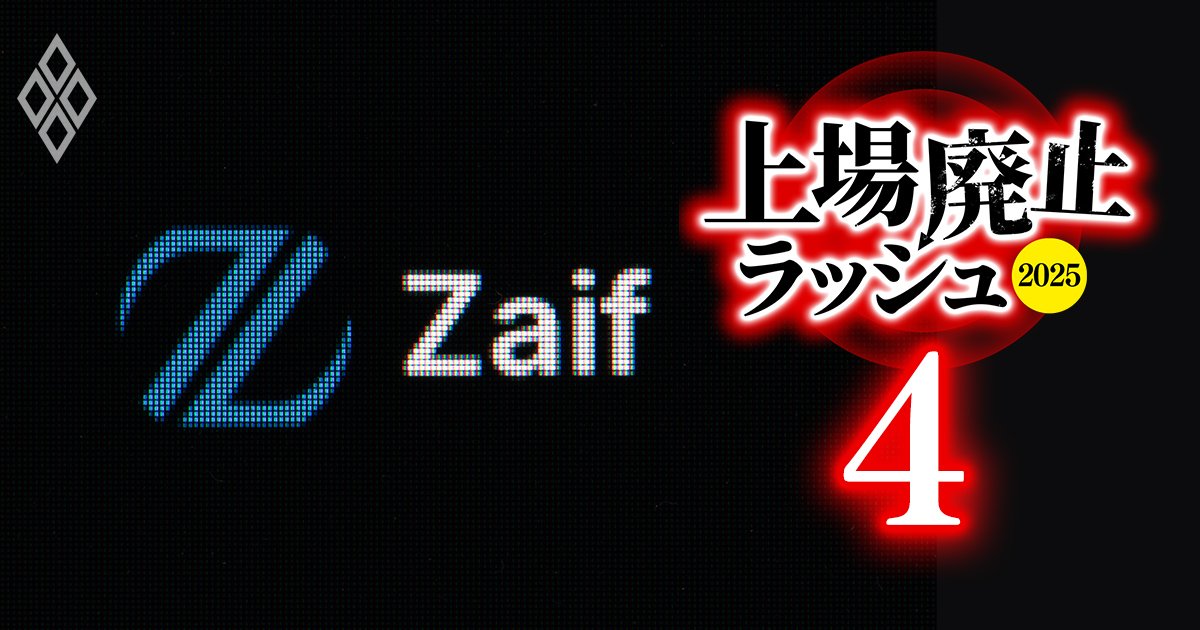(3)徹底的に「掃除」をする意味
5Sに照らし合わせれば、「整理・整頓」の次は、「清掃・清潔」となります。これも通常は仕事の準備段階でやるものですが、私たちの会社では、これを単なる準備段階のものと考えていません。
というのも、まず私たちはピアノという芸術を生み出す品を扱っているわけですから、とりわけ美への意識を高く持っている必要があります。
それに運び出したあとや、設置したあとで、つねに「掃除をする」という作業が伴うのです。私たちにとって「清掃する」という行為は、息を吸って吐くのと同じくらい自然なこととして落とし込まなければいけません。
さらに清潔でない状態で高級品であるピアノを触ろうとすれば、それだけでお客さまからの信用を失ってしまうのです。
だから「整理・整頓」「清掃・清潔」までの流れは、社員一人ひとりが当然のように実行していなければなりません。それが「しつけ」ということになるのでしょう。
そういう考え方ですから、私たちの会社では、「清掃」を「大事な仕事」と考え、必ず就業時間を使ってやることにしています。
私たちのように社員に掃除をさせる会社は他にもありますが、多くは就業時間前に掃除をさせたりして、強制的にプライベートな時間を消費させているわけです。それで「清掃することが大事」という意識が芽生えるわけがありません。
会社として「整理・整頓」や「清掃・清潔」という作業を重んじるなら、それを「利益を上げるための業務」ととらえ、きちんと投資して実行してもらう必要があります。そうしないのは社員に環境整備を説きながら、経営側が本気になっていないということになってしまいます。
ただし“業務”として掃除をする以上は、ただ“掃除らしきこと”をするだけでなく、こちらが要求する掃除の基準を満たしているかどうか、きちんと評価をしていく必要があります。つまり、その時間に対して報酬を与える業務であるなら、掃除についてもしっかりと成果を出してもらうべきなのです。
具体的には、まず掃除をする一人ひとりの社員に対して、担当する範囲を明確にしなければなりません。これは先に述べた「整理・整頓」と同様で、社屋全体をマス状に区切ってエリアマップを作成し、「何月何日の清掃で、A社員はこの区域」という具合に担当を回していきます。
そして主に社長である私の役目になりますが、それぞれの掃除に対してのチェック項目を設け、月1で私が点検に行くわけです。これは120点満点の点数制で、3カ月で330点以上取るとお食事券を支給し、ご飯をご馳走する仕組みになっています。もちろん、「掃除は新人の役目」などという変な差別もありません。大事な仕事なのですから、全員やるのが当たり前。立場上、私は入っていませんが、役員から新人まで皆がゲーム感覚で、掃除の点数を競い合っています。
(参考)
年間で調べもの・探し物に費やす時間(約550時間)=【調べものに費やす時間:1日1.6時間×年間労働日数245日(=1年365日-年間平均休日120日)=392時間】+【探し物に費やす時間:年間150時間】https://officenomikata.jp/news/10445/