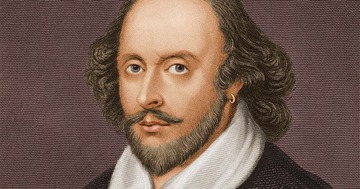松尾芭蕉が残した
「不易流行」という言葉の深み
江戸時代に活躍した俳諧師、松尾芭蕉は「不易流行」という言葉を残しました。「不易」とは「変わらないこと」という意味です。いつの時代でも変わらない本質を知っていることがあらゆることの基礎だというんです。
これはリベラルアーツの考え方と同じです。さらに芭蕉は「流行」も同じくらい大事で、本当に大切なことは時代に合わせて変化しながら残っていくというんですね。
ここに、ぼくが伝えたいことが凝縮されています。
まず、電話の発明から現在までの間に世界の人口は爆発的に増えています。1876年の世界人口は13億人程度ですが、2022年では80億人を超えています。
つまり全体を比べなければ、変化の本質を見誤る恐れがあります。さらに、インターネットやスマートフォンの普及がそのあとではじまったサービスの基盤、インフラになっています。インフラになるような技術は「本質」として改良されながら残っていきますが、ポケモンGOはどうでしょうか?5000万人のユーザーを獲得するのも一瞬でしたが、失ってしまうのも一瞬かもしれません。
数年後には、プレイ画面を見たことすらない人も出てくるかもしれない。
「古典を読む意味はある?」
という問いに対する回答とは
よく古典や古い本を読む意味はあるのでしょうか? という質問をされるのですが、時間をかけて人々が残してきたものは時を超える理由を宿しています。
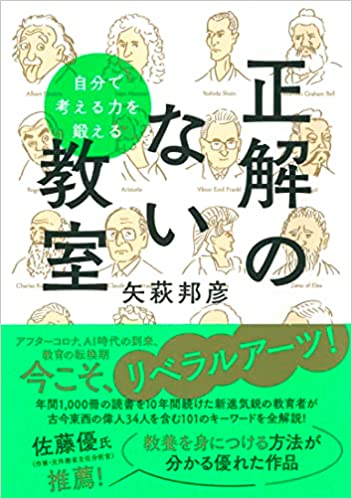 矢萩邦彦著『自分で考える力を鍛える 正解のない教室』(朝日新聞出版)
矢萩邦彦著『自分で考える力を鍛える 正解のない教室』(朝日新聞出版)
何年前の本であっても、いま書店で買うことができる本は、ただ古いのではなくて、古いのにいまだに使える価値がある情報だと多くの人が判断しているということです。
一方で、新刊書や新しいサービスは、時代や環境、流行が変わればすぐに役に立たなくなる可能性があります。
もちろん、流行したもののなかには、きっとぼくたちが求めている「本質」的な要素がありますから、それは別の形となって残っていくでしょう。それらをきちんととらえること、つまり情報をきちんと分類して活用することが、リベラルアーツの目的の一つといえます。