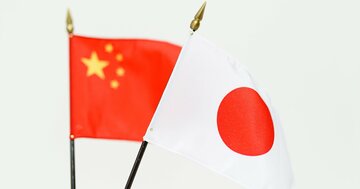Photo:PIXTA
Photo:PIXTA
改正反スパイ法が
7月1日に施行
アステラス製薬の幹部、西山寛氏は3月下旬、4年にわたる二度目の北京駐在を終え、帰国して退職することが決まっていた中で、中国から日本に帰国する際に中国国家安全局によって拘束された。
西山氏は、中国に進出する日系企業の団体「中国日本商会」の幹部を務めたこともあるベテラン駐在員で、北京の日本企業コミュニティーでは知られた人物であったこともあり、現地の日本企業では衝撃が広がった。いまだ解放の目途は立っていない。日本政府としても林芳正外相の訪中は功を奏せず、打ち手がない状況だ。
なお、世界の主要国の多くにはスパイ防止法があり、自国民がスパイ容疑で拘束された際、自国が摘発したスパイを引き渡すかわりに自国民を解放する“ディール”が行われているが、日本にはスパイ防止法がなく、そのようなディールができないのが現状だ。
また、あまり報じられていないが、中国籍で元北海道教育大学の教授、袁克勤(えん・こくきん)氏も、2019年5月に一時帰国した中国でスパイ容疑のため拘束されていまだ解放されていない。
このような状況下、中国では反スパイ法が改正され、7月1日に施行される。
改正により、国家の安全と利益に関わる情報を窃取する行為が、新たにスパイ行為の定義に加わるなど対象範囲が拡大され、恣意的運用による摘発の強化が懸念される。