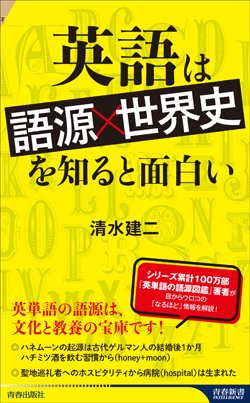巡礼者へのホスピタリティから生まれた病院(hospital)
中世ヨーロッパでは、キリスト教にゆかりのある地への巡礼が流行する。巡礼の主な目的地はカトリック教会の総本山である「ローマ」や、イエスが処刑されたパレスチナの「エルサレム」、そしてイベリア半島北西部の「サンティアゴ・デ・コンポステーラ(Santiago de Compostela)」であった。これら3つの巡礼地は中世キリスト教の三大聖地と呼ばれていた。
「巡礼者」はpilgrimで、「巡礼」がpilgrimageとなるが、語源は「土地を越える」である。grimは「土地」や「野原」を意味するagriが基になっており、acre/agriculture/agronomy/acornと同語源である。
土地の面積を表す「エーカー(acre)」は、くびきにつないだ二頭の牛が鋤を使って一日に耕せる畑の広さで、約40アール。agricultureは「土地を耕すこと」から「農業」、agronomyは「土地の管理」から「農学」、acornは、野原に落ちた実から「どんぐり」となる。
一方で、巡礼者をもてなすための客人歓待制度なる習慣があった。巡礼者をもてなすことは、同一の神イエスを崇拝する者としての当然の義務でもあったわけだ。
逆に、自分が巡礼をする時には、もてなしを受けることになる。もてなす側の「host(主人)」と、もてなされる側の「guest(客)」は、共に印欧祖語で「相互に扶助の義務を負う」というghos-tiに由来する語である。
19世紀になると、hospiceと呼ばれる、巡礼者のための宿泊施設もつくられている。現代英語でhospice(ホスピス)はガンなど末期患者のために医療や看護を施す施設だ。「病院」のhospital、「もてなし」のhospitality、「親切にもてなす」のhospitableは皆、同語源である。
見知らぬ巡礼者を受け入れるということは、それなりの危険性が伴うことから、hostile(敵意のある)、hostility(敵意)、hostage(人質)などのネガティブな語も生まれている。