当然ながら、鬱状態――それは言葉の流れによってさらに悪化する――にある人は、ソーシャルメディアでよりネガティブな個人的情報を発信するものだが、それにもかかわらず、鬱状態にない人と比べ、自分のネットワークは役に立たないと思っている。
ソーシャルメディアにおける自己演出と妬みの感情
だがソーシャルメディアは、頭の中を流れていく思考や感情を(過剰に)表明するためのプラットフォームを提供するだけではないし、ソーシャルメディアが内なる対話を脱線させる方法は、もっぱら共感と時間に関わっているわけでもない。ソーシャルメディアを通じて、私たちはまた、自分の生活の中で本当に起こっていると他人に信じてほしいことを形にできるし、投稿する話題の選択次第では他人のチャッターを煽る場合もある。
人間の持つ自己顕示の欲求は強力なものだ。私たちは、自分が他人の目にどう映っているかに影響を及ぼそうとして、四六時中見た目をつくろう。昔からずっとそうだったが、ソーシャルメディアの登場によって、同じことをするにしても私たちが手にする支配力は格段に大きくなっている。
ソーシャルメディアのおかげで、生活の見せ方を巧みに演出できる。つまり、これはいわゆるフォトショップ版の人生であり、最悪の経験や見てくれが悪い瞬間は消し去られる。
こうした自己顕示活動に取り組むことで、私たちは気分がよくなる。他人の目に魅力的な姿で映りたいという欲求が満たされ、内なる声も鼓舞されるのだ。
だが、そこには落とし穴がある。生活の華やかな場面を投稿すれば気分はいいかもしれないが、その同じ行為によって、投稿を見た利用者が感情を害する恐れがある。というのも、人間は自分をよく見せたいという気持ちを持つと同時に、自分と他人を比較せずにはいられないからだ。
ソーシャルメディアは、私たちの脳に備わる社会的比較のためのハードウェアを過熱状態に切り替える。たとえば、2015年に私が同僚とともに発表した研究で次のことが明らかになっている。フェイスブックの画面を受動的にスクロールし、他人の生活を覗いている時間が長いほど、人は妬みの感情が大きくなって気分が落ち込むのだ。
自分自身に関する情報を共有すると高揚感がもたらされる
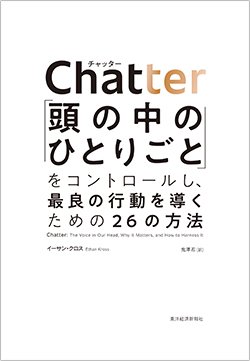 『Chatter(チャッター):「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法』(東洋経済新報社)
『Chatter(チャッター):「頭の中のひとりごと」をコントロールし、最良の行動を導くための26の方法』(東洋経済新報社)イーサン・クロス 著、鬼澤忍 訳
ソーシャルメディアで自分の感情を公開し、その自己演出の文化に加わることに、それほど多くのチャッター誘発効果があるとすれば、なぜ私たちは情報の共有をやめないのかという疑問が湧くのは当然だ。それに対する一つの答えはトレードオフに関わっている。
このトレードオフはたいてい、一時的に気分が良くても、時間とともに負の影響が出てくる行動をとる際に生じる。研究によれば、誰かに魅力を感じたり、好みの物質(コカインからチョコレートに至るあらゆるもの)を摂取したりするときに活性化するのと同じ脳回路が、自分自身に関する情報を他人と共有するときにも活性化することがわかっている。
とりわけ説得力のある説明の例として、2012年にハーヴァード大学の神経科学者たちが発表した研究がある。それによれば、人間はお金をもらうよりも自分自身に関する情報を共有するほうを好むという。言い換えれば、「社会的高揚感(ソーシャルハイ)」は、ドーパミン受容体への心地よい刺激である「神経的高揚感(ニューロナルハイ)」に似ているのだ。
要するに、ここで言いたいのは、オンラインであれオフラインであれチャッターに駆り立てられるままに社会的行動をとれば、往々にしてさまざまな悪い結果を招いてしまうということだ。
内向きと外向きの双方の会話がもたらす悪い結果として、最もダメージが大きいのは、多くの場合、自分へのサポートがやがては減ってしまうことだ。こうして社会的に孤立すると、それによってさらに傷つくという悪循環に陥ってしまう。
実際、注意して耳を傾けてみると、多くの人が他人に拒絶されたときの気持ちを表現するのに、肉体的な「痛み」という言葉を使っているのがわかるだろう。
イヌクティトット語からドイツ語、ヘブライ語からハンガリー語、広東語からブータン語に至る世界中の言語において、人びとは感情的な痛みを表現するのに肉体的な損傷に関わる言葉を用いる――「壊れた」、「傷ついた」、「ケガをした」などなど。
彼らがそうするのは、隠喩表現の才があるからというだけではない。私が自分のキャリアにおいて発見したぞっとする事実の一つは、チャッターは人の感情を傷つけるだけではないということだった。私たちの身体にも影響を及ぼすのだ。その範囲は肉体的な痛みの感じ方から、細胞内での遺伝子の働き方にまで至るのである。







