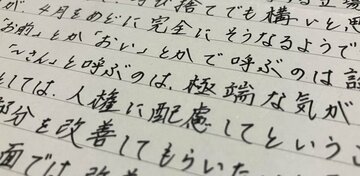傷んだ部分だけ皮をむき、変色は傷んでいるのではなく褐変(食品が調理・加工・保存などによって褐色に変化すること)なので健康被害はなく、味にも影響ないことを伝えた。
うちではごぼうは冷凍のささがきごぼうを使うが、生のごぼうを与えたらきっとなくなってしまうだろうな。ある意味真面目な彼らなら絶対そうなるだろう。
独特な冬瓜のむき方に衝撃が走る
常識外れの作業標準書の指示に唖然
冬瓜のときもたまげた出来事があった。冬瓜は夏野菜だが、冬の瓜と書くのは冬まで保存がきくからだ。白い可食部は少しスポンジのような質感で非常にやわらかい。
その半面、緑色の皮はとても頑丈だ。保存がきくのは、その分厚い皮のおかげだろう。冬瓜は非常に大きく、1個あたりの重量が3キロくらいのものもある。
あるとき、下処理係がまるで乳飲み子を抱きかかえるように冬瓜を持ち、ピーラーでむいているではないか!あまりに衝撃的な姿に目を丸くした。しかし、それ以上に驚いたのが、そう感じたのは私だけだったことだ。
「ねえ、冬瓜っていつもこんなむき方してるの?」
「そうっス。ここに書いてあります」
なんと、「作業標準書」にこんなふうに書かれていた。
「冬瓜は落とさないようにしっかりと抱えて皮をむくこと」
いやいやいや、冬瓜は断じてそんな風に皮をむくものではない。包丁で扱いやすい大きさに切り分け、種と周りのわたの部分を除き、包丁でむくのが一般常識だ。しかし、ここでは長らく丸のままピーラーでむくことがスタンダードだったらしい。
料理経験の乏しい彼らにとって、作業標準書は献立カードと並んで手放せない“虎の巻”だ。炊場にあるすべての機器に関して、例えばピーラー一つについて取り扱い方法が書かれている。
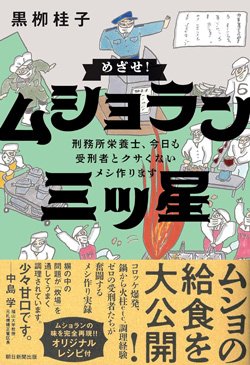 『めざせ!ムショラン三ツ星』(朝日新聞出版)
『めざせ!ムショラン三ツ星』(朝日新聞出版)黒栁桂子 著
刑務所独自で作成されていて、受刑者が機器を使ってケガをした場合に施設側の指導の落ち度になることがないように、作業事故やケガがあるたびに書き換えられている。受刑者にとって作業標準書の内容は絶対なのだが、私の目から見ると首をかしげたくなるのだ。
「ねえ、重いよね」「はい、重いっス……」「だよね」
以来、冬瓜の切り方は変わったが、その後冬瓜を使うこと自体をやめた。冬瓜を煮込みすぎて姿形がなくなり、ただの汁物みたいになることが続いたからだ。
給食作りって、難しい。