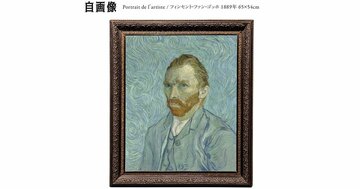ムンクは、人の内面を表現し続けたため、見たままを描いたとは考えにくいものの、この噴火の記憶を自然の脅威として自らの作品に刻んだとしても不思議ではありません。
噴火の影響は、ムンク以外の画家の作品にも見てとれます。ギリシャのアテネ・アカデミーの物理学研究者クリストス・ゼレフォス氏は、絵画の色彩を分析することによって、噴火がそれらに与えた影響について検証を行っています。作中の緑と赤の割合を比べて、赤の割合が多ければ、空気中の微粒子(火山性粒子)が多いと言えるというものです。
例えば、エドガー・ドガの作品を、クラカタウ山の噴火があった1883年以降の数年間とその他の期間とで比較してみると、《競走馬》をはじめとしたいくつかの作品で、赤の比率が高くなっていることがわかりました。
 『天気でよみとく名画』(中央公論新社)
『天気でよみとく名画』(中央公論新社)長谷部 愛 著
さらに時代を遡ると、ターナーの作品にも同じ傾向が表れています。1815年にはインドネシアのタンボラ火山が大噴火を起こし、北米やヨーロッパでは、翌年「夏のない年」と言われる記録的な冷夏となりました。イングランド中部では、観測史上、最も寒い7月で、「毎朝、太陽は煙の中を昇るようだった。赤く、輝きがなく、わずかな光や熱しか放たない」などといった記述も残っています。ターナーが1815年以降に描いた作品《赤い空と三日月》(1818年頃)などには、他の時期よりも多量の赤が使われていることがわかっています。
現在では、当時の天気や気温の状況を知る研究が、氷河や植物など様々なものを手掛かりに進められていますが、絵画の中にも確かに、気象の歴史が刻まれているのです。