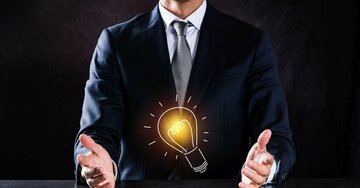明確な目的を持つ米軍
目的のブレが目立つ日本軍
ここからは、太平洋戦争における日本軍失敗の組織論的要因について、現代日本の企業・組織と照らし合わせながら読み解いていきましょう。
1つ目は「目的のブレ」です。
日本海軍・軍令部の戦略は短期決戦を目指し、太平洋を越えて来る米国艦隊を日本近海で迎え撃って、艦隊決戦によって一挙に撃破することを企図していました。計画の背景には、日本の海軍力拡張を抑制しようとする国際的な圧力があります。ワシントンおよびロンドンの海軍軍縮条約に批准したことで、日本は主力艦の保有数を制限されていたのです。
しかし、実戦部隊の最高指揮官である山本五十六連合艦隊司令長官は、積極的な作戦思想を持っていました。山本長官は、攻撃の時期や場所を決めて来攻できる優勢な敵に対し、劣勢な立場での防御戦では勝利が望めないと考え、敵に対して自主的かつ積極的な作戦を展開することを主張。その最たる例が、1941年の真珠湾奇襲攻撃です。山本長官の目的は、敵の不意をついて初動で圧倒し、続く攻勢で米国の士気を喪失させ、結果として優位な講和条件を引き出すことにありました。
いずれも「有利な講和に持ち込む」という目的は共通していましたが、この2つには根本的な思想のブレがあり、それがその後も続いたのです。
対する米国には、日本本土の直撃、直接上陸作戦による戦争終結という共通した明確な目的がありました。米国の対日戦略の基本を定めた「オレンジ計画改訂案」は、長期戦と大きな犠牲を予測。西大西洋のマーシャルおよびカロリン諸島を起点に日本の委任統治領を逐次攻略し、補給線を確保しながら徐々に進攻することを想定していました。歴史を後から振り返ると、実際この通りのプロセスを経ています。