これを見ると、近世後期の江戸語ではあれほどぞんざいな発話に用いられた「ほんに」という語が、「雅」で「馬鹿丁寧」な言葉と「吾輩」に評価されています。この語に対する認識が、130年の時を経て大きく変わったのではないかということを窺わせます。なお近代以降「ほんに」は衰退し、代わりに「本当に」という新しい語が台頭して、現代に至ります。
「めちゃめちゃ」も「超」も
今や若者言葉ではない?
さて、例に挙げられた「めちゃめちゃ」は、1996~2018年に放送されたフジテレビのバラエティ番組『めちゃ2イケてるッ!』のタイトルにもなっており、少なくとも私が高校生だった90年代末頃から「俗語」だったことが確認できる語です。その頃「超ベリーバッド」の略で「チョベリバ」という表現も流行りました。
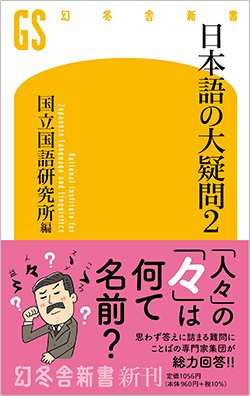 『日本語の大疑問2』(国立国語研究所編、幻冬舎新書)
『日本語の大疑問2』(国立国語研究所編、幻冬舎新書)市村太郎 著
「めちゃめちゃ」や「超」は、一体いつまで「俗」で「若者」風の言葉でいられるのでしょうか。私も大人になり、最近では「若手」と言ってくれる人もだんだん少なくなってきましたが、『めちゃイケ』を見ていた世代としてはこの経過から目が離せません。
そもそも「めちゃめちゃ」にも、「めちゃくちゃ」「むちゃくちゃ」「めっちゃ」「むっちゃ」「めっさ」など、類似する表現が複数あります。最近の大学生の会話やバラエティ番組での若い人の発言では、「めっちゃ」をよく耳にする印象があります。もしかすると、すでに「めちゃめちゃ」は少しずつ大人びてきているのかもしれませんし、あるいは役割分担をしつつもまだ「若者言葉」であり続けているのかもしれません。
これらの表現が一体今どのような役割分担をしていて、どう変わっていくのか、それ自体も史的変遷として興味深い問題です。
【執筆者による関連論文】
*市村太郎(2014)「副詞「ほんに」をめぐって―「ほん」とその周辺」『日本語の研究』10-2、日本語学会
*市村太郎(2015)「雑誌『太陽』『明六雑誌』における程度副詞類の使用状況と文体的傾向」『日本語の研究』11-2、日本語学会
*市村太郎(2014)「副詞「ほんに」をめぐって―「ほん」とその周辺」『日本語の研究』10-2、日本語学会
*市村太郎(2015)「雑誌『太陽』『明六雑誌』における程度副詞類の使用状況と文体的傾向」『日本語の研究』11-2、日本語学会







