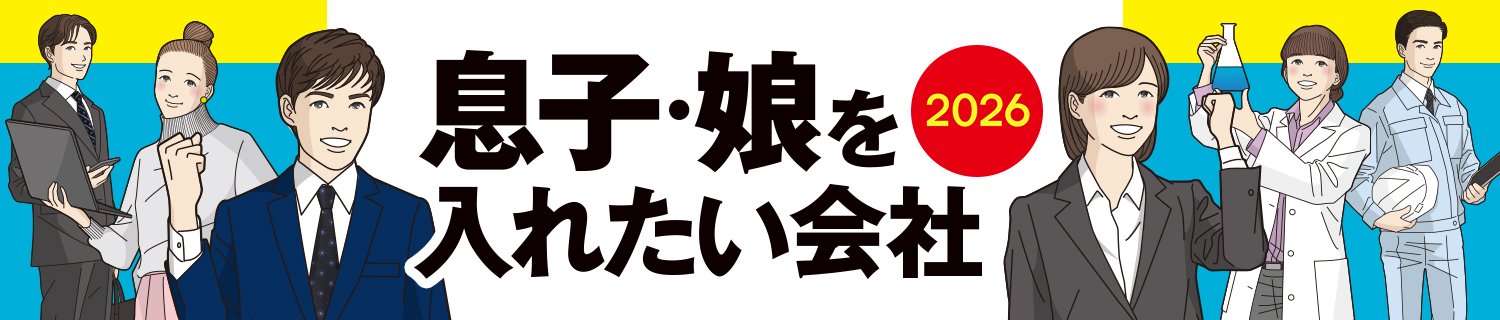24年卒学生への調査でインターンシップ等に参加するために準備したことを聞くと、「インターンシップ・1day仕事体験に関する情報収集」が79.9%、「企業研究(業種・職種研究を含む)」は58.9%、「自己分析」は45.1%、「インターンシップ・1day仕事体験に参加するためのエントリーシートなどの書類の提出」は37.8%で、いずれも23年卒のポイントを上回っていました。
参加したプログラムの期間は、「1日以下」が89.7%と大半を占めており、「2日以上~5日未満」が8.4% 、「5日以上」は1.9%でした。平均参加社数は8.93社で、1day仕事体験が多かったと見られることと合わせ考えると、業界や企業を幅広く知ろうとする学生の意識と行動が一致していることがわかります。
そして、参加したプログラムの期間が長くなると、「その仕事に就く能力が自らに備わっているかどうかを見極めることができた」という成果を感じた学生が増える傾向が見られました。「自分のスキルの見極め」をプログラム参加の目的とした学生は、1日以下のプログラムよりも5日以上のプログラムに多く参加し、その差は17ポイントありました。
「自分自身のキャリア観を明確にする」を目的とした場合も同様で、差は10ポイントでした。こうした目的でインターンシップ等への参加を考えている学生は、5日間以上の汎用的能力インターンシップ、または2週間以上の専門活用型インターンシップを検討すると良さそうです。
インターンシップの選考から漏れても
あきらめる必要はない
インターンシップの要件が明確になったことで、今後インターンシップを実施する企業が減る可能性があります。実施には現場社員の協力が不可欠で、プログラムの設計や準備にも時間と労力がかかるためです。実施したとしても、受け入れ人数を減らさざるを得なくなる可能性もあります。そのため、インターンシップに応募しても参加がかなわない学生が、これまで以上に出てくるかもしれません。
しかし、企業側が参加者を絞る理由は多くの場合、企業側の受入れ体制の制約のためだと考えられます。企業側は、インターンシップの参加者の選考を行う理由や、落選しても採用される可能性がなくなるわけではないことを丁寧に説明することが求められるでしょう。
学生側は、「インターンシップの選考結果は、本採用の選考にも影響するのだろう」「インターンシップに落ちてしまったから、応募しても無駄だろう」と解釈して、本採用への応募を見送って選択肢を狭めてしまうことのないよう気を付けましょう。
(リクルート就職みらい研究所所長 栗田貴祥)