しかも、アメリカは自らがそれぞれのドラマの演出家であることをしばしば否認します。この否認は占領期の検閲にまでさかのぼるものですが、戦後を通じ、私たちはアメリカニズムを戦後天皇制であれ、テレビ文化であれ、家庭電化であれ、それぞれナショナリズムや日本的な娯楽文化、あるいは技術力として受容してきました。
つまり戦後日本の側も、アメリカを強く欲望しながら、その欲望を否認もしてきたのだと思います。ジョン・ダワーが論じた日米の抱擁は、そうしたお互いの否認による抱擁でもあったと私は思います。
日本の家電製品やゴジラと
アメリカとの関係性
――まさに江藤淳がそうだったように思います。
吉見 ですから、戦後日本における「シンボルとしてのアメリカ」は、アメリカと日本という二分法で分けることができない、そのどちらの役も、誰が誰として何を否認しながら演じているのかという厄介さがあります。
ざっくり言えば、それは無限の仮面劇のような多重的な上演なのです。これはなかなかジャン・ジュネ的な上演とも言えますが、しかし演じている本人は、あまり自分がしていることに意識的ではありません。それぞれが無自覚になるほどまでに自分が何かに置き換えられているのです。
つまり、戦後日本人のなかで「アメリカ」は、他者でも自己でもあるような二重性を帯び、そのことがさまざまな文化表象のなかに表明されてきました。
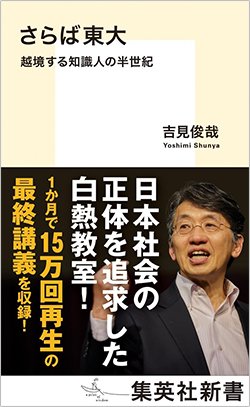 『さらば東大 越境する知識人の半世紀』(集英社新書)
『さらば東大 越境する知識人の半世紀』(集英社新書)吉見俊哉 著
たとえば、家電製品は1950年代には「アメリカ」を演じる俳優でしたが、60年代以降になると「日本」を演じる俳優に転身します。ゴジラについてみても、製作された1954年の時点では、あの巨大怪獣は第一義的には米軍のB29爆撃機のメタファーだったと思いますが、その後のさまざまな解釈のなかで、ゴジラは「B29」であると同時に、戦争で死んだ日本軍の「英霊」でもあったのではないかということになってくる。
私もゴジラにはこの両側面があると思っていて、そういう両義性が戦後日本の大衆的イメージには常についてまわっています。
しかし、さらに議論を進めると、戦後日本における「アメリカ」の上演を、このように表象の演技というレベルだけで捉えるのは、やはり不十分だという気がしてきます。
なぜなら、戦後日本、つまり日本列島やそのなかの都市を考えたとき、アメリカは演じられる役であるのみならず、そのような役が演じられる舞台でもあったのです。







