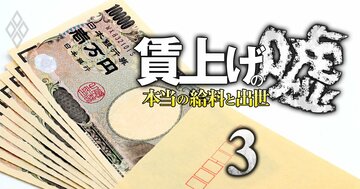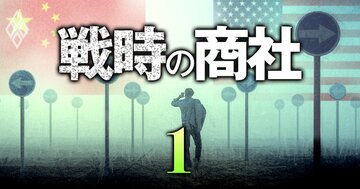Photo:boonchai wedmakawand/gettyimages
Photo:boonchai wedmakawand/gettyimages
7大商社の2023年度通期決算で、三井物産が純利益1位に輝いた。同社が首位に立つのは1999年度以来、24年ぶりだ。三菱商事が純利益でトップの座から陥落したのは3年ぶりとなる。商社業界の勢力図が激変する中、ダイヤモンド編集部は前年に続き、7大総合商社のセグメント別に社員1人当たりの純利益額をランキングした。その結果、業界勢力図だけでなく、部門別の稼ぐ力の順位も激変していることが分かった。(ダイヤモンド編集部 猪股修平)
資源ビジネスは「商品」によって天国と地獄
首位は2年連続であの名門部門
三井物産は、前王者の三菱商事に1000億円近い差をつけて、7大商社(三井物産、三菱商事、伊藤忠商事、丸紅、住友商事、豊田通商、双日)における純利益トップの座に就いた。
唯一2年連続純利益1兆円超を達成したことについて、堀健一社長は「商品市況の不振など一部影響はあるものの、リスク管理や既存事業の良質化などさまざまな取り組みが一定以上のレベルで機能した」と決算会見で語り、自信を示した。
一方、首位から陥落した三菱商事は純利益が前期比2167億円減となり、2年連続1兆円超の達成には至らなかった。
特筆すべき減益要因として、同社がオーストラリアで手掛ける原料炭事業がある。他地域の安価な原料炭の台頭による需要の減少や、価格の急落が響いた。この事業を含む金属資源部門の純利益は、前期比1438億円減の2955億円となり、10あるセグメントの中で最も減益となった。
三菱商事の原料炭事業の減速は、資源価格高騰の追い風が、一段落しつつあることを象徴している。
7大商社の23年度通期純利益の合計額は4兆1195億円で、過去最高益を出した前年度から4956億円減益となった。想定外の資源の減産や資源価格高騰の反動が減益の主な要因であり、依然として商社の「稼ぐ力」は衰えていないといえる。
では、各セグメント別に見ると、社員1人当たりでどの程度の利益を出したのだろうか。ダイヤモンド編集部は22年度に続き、23年度版の「セグメント別社員1人当たり純利益額ランキング」を作成した。すると、1年間で序列の著しい変化があったことが分かった。
次ページでは、7大商社の全61セグメントの収益格差とその偏差値をつまびらかにする。