減塩商品の歴史、醤油から梅干しまで
人々の舌は「塩分控えめ」に適応
減塩商品の歴史は、醤油から始まった。先駆けは、群馬県館林の正田醤油が1963年(昭和38)に発売した「保健しょうゆ キッコーショーヘルシー」だ。業界大手のキッコーマンも1965年に「保健しょうゆ」を発売し、2年後に「減塩しょうゆ」と改称した。
最初のうちは醤油やみそなどの調味料が中心だったが、1980年前後から加工食品にも広がってきた。一風変わった商品名で話題になったのは、1978年(昭和53)に桃屋から発売された低塩、低糖をウリにしたのりのつくだ煮「江戸むらさき お父さんがんばって!」だ。
塩分が多い梅干しも、この頃を境にどんどん塩分が下がっていった。同年の6月9日読売新聞朝刊には、「減塩梅干し作ってみませんか」と呼びかける記事が載っている。
どのくらい塩分を控えているかを確認する前に、最近の傾向にふれておこう。近頃の梅干しは塩分を控えたり、はちみつを加えたりして、「甘くなった」という声がよく聞かれる。その主流は、梅の重量の15%程度の塩で漬けたものだ。減塩梅干しになると3~12%まで開きがあり、酢だけで漬けた塩分不使用の梅干しも売られている。「昔ながら」といわれるしょっぱい梅干しは、18~20%の塩で漬けたものを指すことが多い。
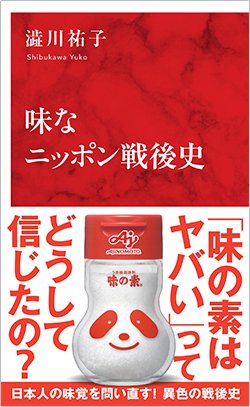 『味なニッポン戦後史』(集英社インターナショナル)
『味なニッポン戦後史』(集英社インターナショナル)澁川祐子 著
ところが、1978年の記事で減塩梅干しとして勧められているのは、なんと塩分20%のレシピである。紙面には、梅干しの塩分は「一般に30%以上ですが、20%におさえると梅特有の“すっぱさ”が出て、塩辛くないおいしいものになります」とあり、腐敗を防止するために土用干しを念入りにするようにアドバイスしている。
1983年(昭和58)6月30日朝日新聞朝刊になると、「塩分10%が限度」とさらに半量もカット。「気をつけないとカビが生えやすいので、初めて漬ける人は15%にした方が無難かと思います」とあり、おそらく15%が最終的な落としどころとして定着したのだろう。
かつての減塩梅干しは、今の「昔ながら」のしょっぱい梅干し。減塩は「慣れ」の問題だとよくいわれるが、長い時間をかけて人々の舌は塩分控えめに適応していったのだ。







