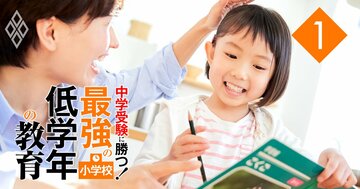写真はイメージです Photo:PIXTA
写真はイメージです Photo:PIXTA
昨今、大学受験のための塾や予備校が次々と潰れているという。というのも、自宅でしっかり勉強できる学生たちが増えているのだ。しかし、この「自立学習」の習慣は中学生になって身につけるのはなかなか難しいという。小学校6年間でゆるぎない土台を築く方法とは――。本稿は、東京高校受験主義(東田高志)『「中学受験」をするか迷ったら最初に知ってほしいこと 4万人が支持する塾講師が伝えたい 「戦略的高校受験」のすすめ』(Gakken)の一部を抜粋・編集したものです。
高校受験は小学校6年間で
すでに半分が終わっている
実は、高校受験は小学校6年間で半分は終わっているといえます。自立学習の確立、算数や国語の基礎の構築、そして中学英語へのスムーズな移行は、小学生のうちに済ませておきたい「種まき」です。これらが高校受験の「土台」となり、高校受験そのものの難易度と、到達できる学力の上限値を決定づけます。
小学校時代に揺るぎない土台を築くことができれば、高校受験は早期からの進学塾通いは不要です。保護者の経済的、精神的負担も大きなものにはなりません。反対に、土台が仕上がらないまま中学に上がってしまうと、高校受験はハードなものになってしまいます。
中学生相手の高校受験指導が難しい要因は「可塑性の低さ」にあります。つまり、子どもがなかなか変わりにくいのです。年齢を重ねるにつれて性格や習慣の柔軟性は失われていきます。勉強習慣がゼロの子を勉強に向かわせるのは、小学生よりも中学生相手のほうが大変です。
ここでは、公立中学生の学習のモデルルートを示しますが、それは、小学校時代の土台あってこそ。この点を忘れないでください。
中学受験は小学3年生の2月からのスタートが一般的とされています。
高校受験はどうでしょうか。ある中堅クラスの都立高校の新入生に対するアンケートによると、塾に継続的に通っていた生徒は60%でした。それ以外に、模試や講習会のみ塾を利用した生徒が14%、塾を利用していない生徒は26%でした。
中学受験とは違って
塾依存度が低い高校受験
継続的な通塾率がこの程度であることを意外に思うかもしれません。教育熱の高い東京であっても、高校受験の中間層はこんなものです。
さらにレベルの高い共通問題実施校最上位の都立小山台高校でも、主要7大塾の合格者の占有率は約45%にとどまっています。在校生に聞いたところ、周りは通信講座や地元密着型の塾、または講習会のみ塾を利用した生徒が多いそうです。
中学受験と高校受験の大きな違いの一つは、学校の授業内容が入試にどれだけ寄与するかです。中学受験では、小学校の学習内容と入試問題が大きく異なるため、塾のカリキュラムに頼らざるを得ない状況です。一方、高校受験は中学校の学習内容を基にしているので、学校の授業を効果的に活用すれば、塾への依存を最小限に抑えることが可能です。