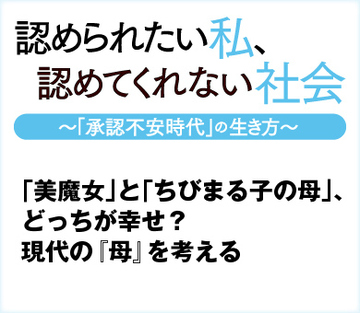ここまでの議論をまとめると以下のようになる。
(1)1990年代は、男女雇用機会均等法施行により、母親=専業主婦という「戦後家族モデル」が砕かれる過渡期だった。
(2)アダルト・チルドレン・ブームによって、親から受けた心の傷が、物語のテーマとして多く取り上げられるようになったのだ。
このふたつの流行が重なった結果、少女漫画は「理想の母」――現実には存在しない、フィクショナルな母――を描くようになったのだ。
ゴールは「母のような女になる」
90年代に描かれた理想の母親像
1990年代の「理想の母」を描いた少女漫画として、槇村さとるの『イマジン』を見てみたい。
物語の主人公は、OLとして働きつつ、炊事洗濯を引き受ける娘の有羽。彼女は、建築家で家事をまったくしない美人の母親・美津子の世話に手を焼いていた。
一方で、OLとして受動的に生きていた有羽は、自由奔放な母に憧れてもいて、自分のやりたいことや生きるべき道を探す日々が続く。最終的に、美津子と有羽は別居し、それぞれ自立した人生を生きることに決める。
娘・有羽にとって、母・美津子は、「母」であると同時に「いい女」になるまでの師匠であり、メンターである。
娘・有羽の「いい女」へのビルディングス・ロマンは、母・美津子という師匠のもとから卒業する=自立することで終わりを告げる。母娘の関係に終わりはないが、師弟の関係には卒業という終わりがある。つまり『イマジン』は、母・美津子が「いい女」道を娘に指導する成長物語なのだ。
そのため『イマジン』の最終話では、娘・有羽は母・美津子の彼氏に「美津子かと思った」と見間違われる。これが母娘の愛憎物語だったらホラーのような結末に思える(母と似た姿になって、母の彼氏に見間違われるのは、かなり怖い話だ)が、『イマジン』において、有羽が美津子に似た姿に辿り着いたこの瞬間は、美しい成長の証として描かれる。
「母のような女になること」が、『イマジン』の描いた娘のゴールだったのだ。
娘・有羽にとっての母・美津子とは、自分を常に見守り理解してくれる「母」であると同時に、自己実現のロールモデルとなる「父」でもある。まさに男女雇用機会均等法の時代における「社会的成功」と「心のケア」、どちらの欲望も叶える「理想の母」なのだ。