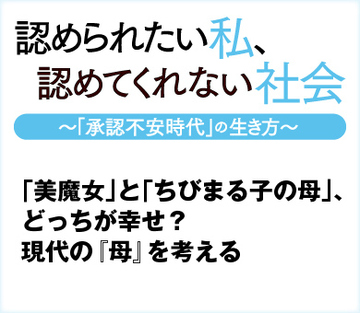「理想の母」物語による
母への幻想の強化
では、虚構のなかで「理想の母」を描くことに、問題点はあるのだろうか?
私が懸念するのは、「理想の母」の物語が、母への幻想を強化してしまうところである。
臨床心理士の信田さよ子は、母親との関係に苦しむ娘たちに対して、「母への幻想を捨てなくてはいけない」というアドバイスをする。
つまり母親はそれほどやわではなく、娘を理解して反省などしない、つまり娘のことをわかってくれるという幻想を捨てなければならないという感覚である。そのことを最初から女性たちに伝えても理解されることはない。なぜならどれほど拒絶していようと、彼女たちの母親への幻想は残り続けているからである。
信田さよ子『母・娘・祖母が共存するために』
信田さよ子『母・娘・祖母が共存するために』
たしかに、娘が母の規範を手放すことができない理由のひとつに、「母はいつも正しく、自分のことを理解してくれる」という幻想が存在する。
このような「母への幻想」は、日本の家庭が専業主婦文化から共働き文化に移行したいまもなお残っている。
夫が労働、妻が家事と育児を担う「戦後家族モデル」が主流となる戦後日本において、育児は母が担うものとされていた。だが1990年代以降、少子化対策と男女共同参画社会の双方を打ち出した日本は、母親に「家事育児と賃労働の双方を完璧な形で両立する」ことを期待する。というよりも、1990年代に始まる長い景気低迷において、育児と労働の両方を母親が担わなければ、多くの家庭が家族の型を保てなくなってしまった。
働きながらの育児は、言うまでもなく大変だ。しかしその大変さは「母は苦労する生き物だ」という言説によって美化される。母性を神聖化することで、女性が育児と労働を両立する負担を無効化しようとしたのである。
こうして1990年代以降、母が働くようになった後も、母への幻想は残り続けた。
自己犠牲的な「母親の献身」は
感動を誘うコンテンツであり続ける
作家の堀越英美は、「母親の献身」がいまなお国民の感動をもっとも誘うメジャーコンテンツのひとつであると指摘する。