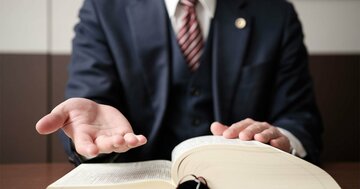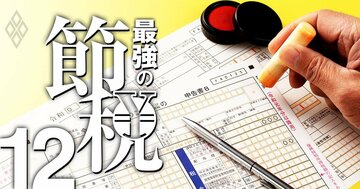それに対し、納税申告に直接携わっていない弁護士であれば、客観性をもって税務調査に臨むことができます。そして必然的に「どのような返し方をすれば危機的状況を切り抜けられるか」について、理論立てて考えることができるのです。
そもそも、私たち弁護士はこうした状況において必要とされる「交渉術」は得意分野です。数々の刑事事件において、一見すると不利な状況を覆した経験があるからこそ、税務調査における不利な状況でも、どのような手段が適切なのかということについて、冷静に判断することができるのです。
結局弁護士にできて、
税理士にできないことは何?
もう1点、弁護士が税務調査の立ち会いに適している点があります。それは弁護士が「法律の専門家である」という点です。
意外に盲点になりやすいのですが、国税庁からのアプローチはあくまで「通達」であって、法的根拠に基づくものではありません。通達が法解釈として本当に妥当であるのかどうか、検討が必要です。
 『税務調査は弁護士に相談しなさい』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)
『税務調査は弁護士に相談しなさい』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)眞鍋淳也 著
税務調査で言われたことに対して、「そう言われているのだから、間違いないだろう」と考えてしまうことは致し方ないという面もあるでしょう。他でもない「国家権力」である国税局の職員が間違ったことなど言うわけはない、というのが一般的な考え方ではないでしょうか。
そして、法律の専門家ではない税理士であれば、まずもってこうした考え方に行き着くこと自体が少ないというのもやむを得ないことではあります。税務調査で提示された内容について法律の解釈によって疑問を提示することで、交渉を有利に導くことが弁護士にはできます。それが税理士にできないのは、税理士が法律に疎いということと無関係ではありません。
一方、こうした法的解釈という観点からのやり取りにおいては、弁護士は言うまでもなく専門家です。税務調査官が税務調査で提示する「上から言われているので、こうやってください」という法的根拠のないロジックだけで終わらせない。それが税務調査に弁護士を立ち会わせることの、何よりのメリットだと言えるでしょう。