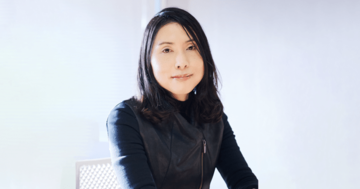「構造的無能化」とは何か。
新規事業開発組織の研究から知見
――対処療法で短期的に業績改善するけど、当事者には納得感がないのですね。
今回の執筆は、とても大変で、書きながらかなり悩みました。今まで書いてきた本とは比べ物にならないくらい複雑な問題を扱っていたからです。しかも、表向き大きな問題がないわけです。
多くの企業が置かれた状態を例えると、原因不明の発熱が続き、思うように活動ができないので、解熱剤を飲んで仕事をして、とりあえず仕事は出来ているので一定の成果は出している感じです。でも、だんだんと体調自体が悪くなっていく。症状を抑える薬を飲んで一時的にしのぐというのではダメなわけで、それを皆さん自覚している。
そういう多くの企業事例を多く見て、経営学者として、どのような視点や論点を提示すればいいのか、糸口が見えずにとても悩みました。
――慢性疾患的な企業の要因を、「構造的無能化」として提示されています。
長い間模索した結果見出した変革が進まなくなるメカニズムは、「構造的無能化」が起きているのではないかということでした。これは一定の成功を成し遂げ、成熟した企業に起きる状態だと言えます。
事業が成功した企業は、より効率的・合理的に事業を継続しようとします。分業化を進め、ルーティンが定まっていくと、結果的に組織内の視点が硬直化してしまうのです。
組織の断片化が進む中で、思考の幅と質が制約され、それぞれの部門で目先の表層的な問題解決を繰り返し、徐々に疲弊していきます。これが、先に述べたパーパスやエンゲージメントの例などにも起きていることです。
――本書では、「企業の環境適応から始まって、分業化・ルーティン化を経て、断片化・不全化・表層化」という構造的無能化のメカニズムを明らかにしています。この状態に対する変革の入口 を、宇田川先生はどう見出したのですか。
きっかけのひとつは、NECの新規事業開発組織について調査研究をしたことでした。ケーススタディ「NEC 新事業開発を起点とした企業変革へのチャレンジ」を、佐々木将人・一橋大学大学院経営管理研究科准教授、黒澤壮史・日本大学商学部准教授との共著で、『一橋ビジネスレビュー』2021年WIN.69巻3号(東洋経済新報社)に掲載しました。また、このケーススタディの執筆後も継続してお話を伺い、「NEC北瀬氏と宇田川准教授が語る、経営変革の思想と実装──なぜ有望事業をカーブアウトしたのか?」(翔泳社のWebメディア『BizZine』)などで公開もされています。それら一連の調査研究を通じて、変革への入口が見えてきたのです。
NECは、長い歴史の中での成長・成熟を経て、近年は低成長に甘んじてきた典型的な日本の大企業でした。莫大な技術蓄積があるのにも関わらず、それを活かした新規事業開発が育てられないという課題を抱えていました。しかし、近年ではイノベーションを生み出せる企業へと変わろうとしています。
例えば、AIを用いたデータ解析を行う新会社dotDateを米国でカーブアウトするなどの成果を出し、創薬事業や生体認証などでは非常にイノベーティブな事業を次々と生み出しており、事業領域は明らかにこの10年で変化してきています。
NECは、新規事業開発のため、全社横断機能を持つ新組織をコーポレート部門として設置しました。こうした取り組み自体は大手企業において珍しいことではないのですが、それが機能しているのは非常に興味深いことです。
同社の特徴的なところは、新事業開発のための組織を作るだけでなく、事業開発・組織開発・人材開発の3つの軸を持って推進し、既存事業部門やコーポレートとも上手く連携して事業を生み出す仕組みを作っていったことです。
これらが機能する背後には、経営陣についての役員以上の意識改革への長年の取り組みや、カルチャー変革本部の設置、経営陣が全国の事業所を回って従業員と話す機会を設けるなど、地道な取り組みもあります。
前述のケーススタディやウェブのインタビュー記事ではこの調査研究から得られた知見を示しましたが、実は私が最も驚いたことは、NECのような巨大成熟企業がイノベーションを起こせたことと、その方法論がとても地道というか、一見、地味だったことです。そして、個々の施策で何をしたのかを突き詰めていくと、それは「対話」なのだと気が付きました。この気づきもひとつのきっかけになって、さらに考察を深めていくことができました。
変革に関わった多くの方にお話を伺ったのですが、特にインパクトが強かったのは、NEC コーポレート・エグゼクティブ/BIRD INITIATIVE 社長兼CEO の北瀬聖光さんの次の言葉でした。新規事業開発の部門には、既存事業も予算達成をしなければならない中でなかなか人を出してもらえないという問題がよくあります。それに対してどうされたのかをお聞きした際の言葉です。
「新しい活動の成果が出るまでは人材育成という成果で、効果や存在意義を理解してもらうようにしていきました。最初は異動する本人も不安だし、既存事業部門もエースはなかなか出すことはできない。そうやって預かった人について、『この人のスキルレベルはこうでした。事業イノベーション戦略本部に来て、コーポレートでチャレンジすべきテーマに対してこういう活躍をしました。その結果、こんなスキルアップをし、成長しています。帰任したら、この方はこんな新しいジョブで活躍できます』というような、個人カルテを作っていました。」(出所「NEC北瀬氏と宇田川准教授が語る、経営変革の思想と実装──なぜ有望事業をカーブアウトしたのか?」〈翔泳社のWebメディア『BizZine』〉)
これこそが対話の取り組みだなと私は思いました。「新規事業は会社全体にとって大切なのだから、各部署は必要な人材を要請通りに出すべきだ」と迫るのではなく、「この人事異動は、本人にもプラスがあるし、派遣する部署にとっても人材育成という困りごとに貢献する」という筋から働きかけていたのです。既存事業の部門長の横に座って、「どうですか、一緒にやってみませんか」と語りかける感じで。そして、「やってみたらこういう成果がありました」ときちんと説明した。そうなると、当人も、人材を出した部署も、良かったなとなりますよね。
――丁寧に問題を乗り越えていくことがあっての成果なのですね。本書の研究アプローチに通じますね。慢性疾患状態の企業に、既存のフレームワークを適用して、即効性のある対処策を作り出すという形ではなく、現場の経営者や管理職、一般社員に寄り添い、根源的な問題を探っていく。このアプローチでなければ、本書の研究成果は生まれなかったかもしれませんね。
私の研究の特徴は、実際の現場に張り付いて、企業変革に半分当事者として携わっていくことで、自分なりの知見を見出していくものです。私は答えを最初から持っているわけでなく、企業の方と一緒に悩み、考えることを大切にしています。
――慢性疾患当事者にケアをするソーシャルワーカーやカウンセラーのようなイメージですね。本書で提示されている「対話」や「ナラティヴ・アプローチ」、今多くの分野で注目される「ケア」といった処方策について、詳しく伺っていきたいと思います。
*連載第2回に続きます。
宇田川元一(うだがわ・もとかず)
埼玉大学経済経営系大学院准教授
1977年生まれ。専門は経営戦略論・組織論。早稲田大学アジア太平洋研究センター助手、長崎大学経済学部准教授、西南学院大学商学部准教授を経て2016年より埼玉大学大学院人文社会科学研究科(通称:経済経営系大学院)准教授。企業変革、イノベーション推進の研究を行うほか、大手企業やスタートアップ企業の企業変革アドバイザーも務める。主な著書に『他者と働く──「わかりあえなさ」から始める組織論』(NewsPicksパブリッシング)、『組織が変わる──行き詰まりから一歩抜け出す対話の方法2 on 2』(ダイヤモンド社)。最新著書は『企業変革のジレンマ──「構造的無能化」はなぜ起きるのか (日本経済新聞出版)。