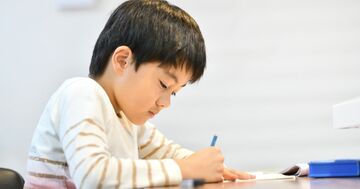「こないだの課題やった?」
「テスト解けた?」
「クラス上がったね。すごいじゃん!」
などの会話はこの塾に行っていない子はついていけない。高学年になるにつれて通塾回数も増えるため、同じ塾に通っている子同士は必然的に関わる時間が長くなる。すると、この塾に通っていない子はどう思うだろうか。疎外感を覚え、私も塾に入りたいと思うようになるのも当然だ。
だが、こうした場合、塾に通い始める目的、スタートラインを確認する必要があるだろう。塾とはどういうところなのか、中学受験をするというのはどういうことなのか、そこをしっかりと子どもと話し合わずに入塾すると、お互いに苦しいだけの受験生活になってしまう。
子どもは塾でも友達と話せてハッピーだが、目的が友との交流のため、勉強にはそれほど身が入らない可能性もある。下手をすると、高い月謝を払って遊びに行かせているような状態になりかねない。勉強に身の入らない子どもを見ると、親はやるせなくなってくる。そして、最後にはこうなるのだ。
「あなたがやりたいと言ったから始めたのに!なんでちゃんと勉強しないの?」
「自分でやりたいと言って入ったのだから、頑張りなさい!」
こうして親子はぎくしゃくしていく。
親のこうした言い分は確かにもっともらしく聞こえるのだが、子どもはそこまで真剣に考えて中学受験をスタートさせたわけではないため、お互いに苦しくなるのだ。
子どもに語りかけるときは
声のトーンに気をつける
幼稚園の頃に「ケーキ屋さんになりたい」と言っていた子が本当にケーキ屋さんになるケースは稀だ。子どもの心変わりは当たり前と思って接しておかないと、知らない間に子どもを抑圧してしまう。
宿題をするのもおっくうになり、「もう塾やめる!」と子どもが言い出しても、
「あなたがやりたいと言ったんじゃない!」
と、ついつい責めてしまう。
しかし公認心理師によると、いったん子どもの気持ちを受容する必要があるという。でないと子どもはその後も本音を言わなくなるそうだ。