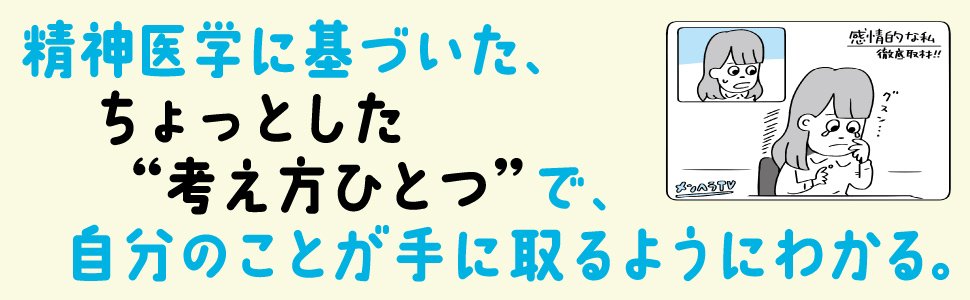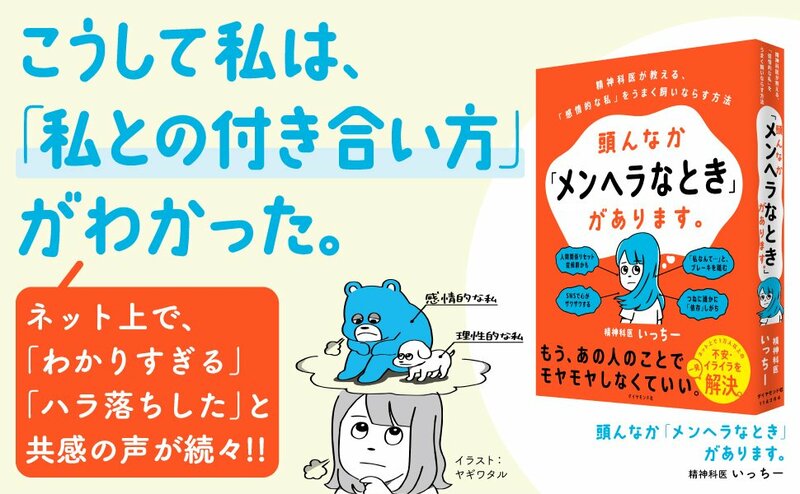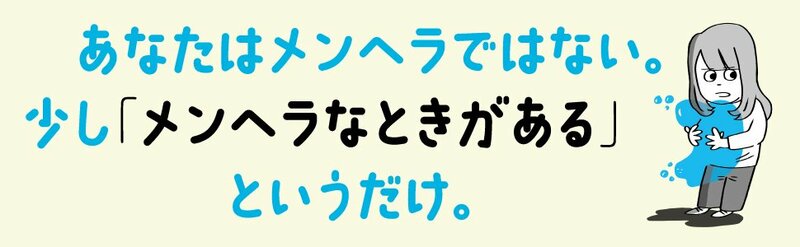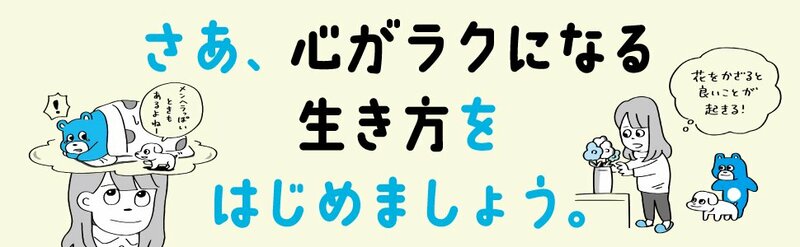【永久保存版】精神科医が教える「やる気」を簡単に作り出す方法・ベスト3とは何か。
それを語るのは、これまでネット上で若者を中心に1万人以上の悩みを解決してきた精神科医・いっちー氏だ。「モヤモヤがなくなった」「イライラの対処法がわかった」など、感情のコントロール方法をまとめた『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』では、どうすればめんどくさい自分を変えられるかを詳しく説明している。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、考え方次第でラクになれる方法を解説する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)
 Photo: Adobe Stock
Photo: Adobe Stock
モチベーションの科学:脳研究が明かす「やる気の不思議」
「今日はどうしてもやる気が出ない...」
そんなため息をつきながら、あなたも一度は考えたことがあるのではないでしょうか。
「どうして自分はこんなに意志が弱いんだろう」と。でも、ちょっと待ってください。
それは本当にあなたの意志だけの問題なんでしょうか?
私たちの脳は、単純な「やる気スイッチ」で動いているわけではありません。
科学的な研究によると、「やる気」とは、複数の要素が絡み合って生まれる、とても複雑な感情だとわかっています。
例えば、十分な睡眠を取れていない日や、栄養バランスが崩れている時期には、どうしてもやる気が出にくくなることがわかっています。
また、目の前のタスクや責任が大きすぎると感じたときも、私たちの脳が自己防衛的に「これは危険かもしれない」というシグナルを送ってやる気をそいでしまうようです。
そのため、やる気が出ないのはあなたの意志が弱いせい、というのはじつは正しくないのかもしれません。
むしろ、あなたは何とか頑張ろうとしているのに、脳や体が何かしらのメッセージを送っているせいで動きだせないのかもしれません。
そんな「やる気」の不思議な正体と上手に付き合っていく方法について、今日は共有したいと思います。
脳が教えてくれる「やる気」の秘密
私たちの頭の中では、驚くほど精巧な仕組みが働いています。
特に興味深いのは「報酬系」と呼ばれる神経回路の存在です。
この回路は、前頭前野から側坐核まで広がる広大なネットワークを形成していて、私たちの「やる気」を支えています。
面白いことに、この報酬系は単純な「快感」だけでなく、「やりたい!」という「やる気」と呼ばれる気持ちも生み出していると考えられているんです。
まるで、私たちの中に「やる気のプロデューサー」がいるようなものですね。
そんな「やる気」も3つの要素から成り立っています。
まず「やりたい」という気持ちを作り、次に実際の行動を始める合図を出し、そして最後までその行動を持続させる。
そんな重要な要素のなかでも、気持ちを作るためのプロデューサーが誤った働きをしてしまうこともあるのです。
なぜ時々「やる気が出ない」のか
私たちの脳は、ストレスやプレッシャーを感じると活動が鈍くなるとわかっています。
脳の中の「やる気のプロデューサー」ともいうべき部位は、私たちの感情によって大きく左右されてしまい、ここが上手く働かないと、やる気も出にくくなってしまうのです。
そんなとき、不安を減らすためにスマートフォンやSNSから情報を脳に取り込みすぎると、余計に脳に大きな負担がかかってしまうようになります。
そんな過度な負担をゆるめるために、「やる気が出ない」というシグナルを送ることで、脳が私たちを守ろうとしているのかもしれません。
脳に優しい「やる気の育て方」
そんなやる気を生み出せるようになるためには、脳の習性を理解することが大切です。
脳には「神経可塑性」という素敵な特徴があります。
これは、繰り返し行う行動によって、脳の中に新しい道筋が作られていく性質のこと。言わば、「やる気の近道」が脳に段々と増えていくようなものです。
例えば、毎日同じ時間に同じ場所で作業を始めると、脳は徐々にそれを「作業モード」として覚えていきます。
すると、意識して頑張らなくても、自然と行動を始められるようになっていくんです。
そんな「慣れ」や「習慣」なんて呼ばれる脳の機能って、じつはすごい仕組みなんです。
そのためやる気を生み出し安くするために、上手に付き合うための3つのコツをお勧めします。
脳と上手に付き合う3つのコツ
1. 朝の光を味方につける
朝日は人間の感情を整えて、やる気を出してくれる重要な要素です。
さまざまな研究でも、人間の気分は朝にもっとも良くなりやすく、朝から動き出すことでやる気も起こりやすくなることがわかっています。
そのため1日のやる気を生み出すコツとして、少しだけ朝を意識してみてください。
2. 大きな課題は小分けにする
人間の脳は、自分のキャパシティを超えるような難しそうな課題を前にすると、つい「逃げ出したい」と思ってしまうようにできています。
でも、その課題を小さく分けていくと、脳が「負荷が減った」と認識することで、やる気が保ちやすくなります。
大きな課題と捉えすぎず、やる気のためにも視点を変えることも大切なんです。
3. 環境の力を利用する
私たちの脳は周りの環境からかなりの影響を受けています。
特定の場所を「作業する場所」として決めておくと、そこに座っただけで脳が「あ、今は頑張るモードだな」と理解してくれるようになります。
そのためあなたが負荷を感じにくいようなお気に入りのカフェや勉強スペースなどを意識的に作っておくと、やる気も起こりやすくなるでしょう。
大切なのは新たな「視点」を手にすること
「やる気」の問題は、もはや単純な「気合」や「頑張り」の問題ではありません。
それは、私たちの脳が見せる、とても興味深い現象の一つなのです。
「やる気」のメカニズムを理解することは、そんな自分を責めることから解放してくれるはずです。
そして、より優しく、でも効果的な方法で自分と付き合っていくためのヒントを与えてくれます。
完璧を目指す必要はありません。あなたの脳と、上手に対話しながら、少しずつ自分に合った方法を見つけていってくださいね。
(本稿は、『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』の著者・精神科医いっちー氏が特別に書き下ろしたものです。)
精神科医いっちー
本名:一林大基(いちばやし・たいき)
世界初のバーチャル精神科医として活動する精神科医
1987年生まれ。昭和大学附属烏山病院精神科救急病棟にて勤務、論文を多数執筆する。SNSで情報発信をおこないながら「質問箱」にて1万件を超える質問に答え、総フォロワー数は6万人を超える。「少し病んでいるけれど誰にも相談できない」という悩みをメインに、特にSNSをよく利用する多感な時期の10~20代の若者への情報発信と支援をおこなうことで、多くの反響を得ている。「AERA」への取材に協力やNHKの番組出演などもある。