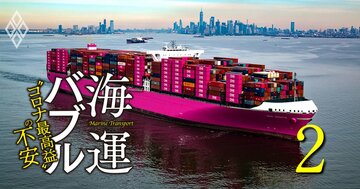Photo by Yuito Tanaka
Photo by Yuito Tanaka
2025年3月期も好調が続く商船三井。課題は、海運市況に左右されない安定収益型事業の拡大だ。そのためにLNG(液化天然ガス)や不動産事業に加え、1.2兆円の巨費を投じて新規事業への進出を模索する。海運会社は、ボラティリティーの高さという長年の弱みを克服できるのか。長期連載『経営の中枢 CFOに聞く!』の本稿では、商船三井専務執行役員チーフ・フィナンシャル・オフィサー(CFO)の濱崎和也氏に、同社の未来のビジョンを聞いた。(聞き手/ダイヤモンド編集部 田中唯翔)
「ROE9%がわれわれの最低ライン」
安定収益型事業への投資を拡大
――商船三井における最高財務責任者(CFO)の役割とは。
商船三井がCFOを導入したのは2018年のことです。それ以前も経理財務担当役員はいましたが、単体中心からグループ経営の形に進化する過程で、グループ全体に最適な財務戦略を立てる役割が必要になったこと、横断的にガバナンスを利かせる必要が生じたことで、CFOが設置されました。私はCFOとして、会社価値を向上させることを強く意識しています。
――会社価値を上げるために、濱崎CFOが最も重視されている経営指標を教えてください。
中期経営計画の中には、重要業績評価指標(KPI)として、税引前当期純利益や自己資本利益率(ROE)、ネットギアリングレシオ(純負債比率)を挙げています。その中でも非常に重視しているのは、資本コストを上回るリターンを上げ続けるためのROEです。
現在はコンテナ市況が上振れているので、ROEは12.2%ですが、ROE9%がわれわれの最低ラインです。安定的にリターンを上げることができる体質のポートフォリオを作っていき、加えてROEの分母の部分、自己資本についても自社株買いなどで圧縮してまいります。
――24年3月期の税引前純利益は2954億円でした。グループ経営計画「BLUE ACTION 2035」にある、36年3月期の目標の4000億円はどのように設定されたのですか。
目標としているのはROE9~10%で、約8%の資本コストを上回るリターンを安定的に上げ続けると、総資産規模が大きくなると考えられるため、現在5.1兆円の総資産(オフバランス資産を含む)を35年時点で7.5兆円に積み上げる計画です。これを前提にすると自己資本も積み上がるはずなので、目標のROEで逆算して、目標の税引前純利益が4000億円になります。
――25年3月期第2四半期の決算は増益増収になりました。好調の要因を教えてください。
上期が大幅な増益になった要因は、ベースとしてLNG事業やオフショア事業、不動産事業などの長期安定事業で着実に利益を積み上げた上で、市況の追い風を受けて、コンテナ船、ケミカル船、自動車船などが上振れたことにあります。
――コンテナ船事業については、7月をピークに運賃が下がってきています。下期の業績にはどういった影響があるとお考えですか。
上期の業績が好調だった要因の一つは、中東情勢の影響で喜望峰を経由する航路が増えたことです。元々今年は世界的に新造船が大量にできる予定で、マーケットはよくないと思われていました。遠回りの喜望峰回りになったことで、船の数が足らなくなり、かつ航海日数が増えたので、お客さんが早め早めに荷物を出して在庫を積み増す動きが欧州航路には見られました。北米は結局回避されましたが、東海岸でのストライキや、トランプ大統領になった場合に関税が高くなることを懸念して、出荷の前倒しが起きました。その結果、荷物量が増えて運賃が上昇しました。
顧客の前倒し出荷により、下期の荷動きが鈍る可能性があったため、保守的な業績予想を立てました。しかし、運賃は下がってはいるものの、現状の荷動きは旺盛ですし、10月に盛り返したこともあり、24年度第3四半期は予想より良かったです。ただ第4四半期を含めると下期全体としてどうなるかはまだわかりません。
――グループ経営計画「BLUE ACTION 2035」には「M&A(企業の合併・買収)をスピード感を持って推進する」とあります。今後はどの事業でM&Aを検討していますか。
海運市況の追い風を受け好調が続く商船三井は、36年3月期の目標総資産7.5兆円に向けて、26年3月期までに1.2兆円の事業投資を予定している。その投資計画には、既存の事業の延長線上にない投資もあるという。次ページで濱崎CFOが語る。