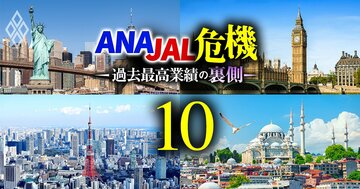田中唯翔
九州を地盤とする中堅航空会社、ソラシドエア。インフレによるコスト増加に加え、円安のあおりを受けており、コロナ禍以降も苦戦を強いられている。空港使用料や燃料税の減免などの公的支援も2026年度で終了し、今後は事業環境の厳しさに一層拍車が掛かる。この窮状をどのように切り抜けていくのか。ソラシドエアの山岐真作社長に、円安が続く25年度下期の現状、そして国内線の問題解決に残されたタイムリミットを聞いた。

フードデリバリー業界の覇権争いが再び激化している。その中心にいるのは、「お店と同じ価格」を旗印に掲げる韓国発の「ロケットナウ」だ。同サービスの急成長を受け、既存各社は価格戦略の抜本的な見直しを迫られている。業界最大手のUber Eats(ウーバーイーツ)も、サブスクリプション会員を対象に配達料とサービス料を無料化する方針を打ち出し、真っ向から反撃に転じる。だが、クーポンで一時的にシェアを奪っても、その先に待っているのはジリ貧の我慢比べに他ならない。コロナ禍の教訓は生かされるのか。再び過熱するフードデリバリー業界の舞台裏と、その構造的な課題を浮き彫りにする。
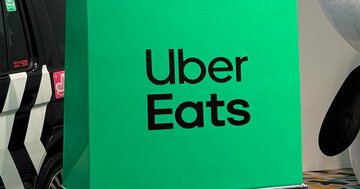
日本航空(JAL)と東日本旅客鉄道(JR東日本)が、航空機と新幹線を組み合わせた新たな物流サービス「JAL de はこビュン」を始動させた。従来の半分以下の時間で海外へ荷物を運ぶ今回の“異例”の取り組みは、物流を成長分野と位置付けるJR東の戦略を映し出している。同社の強みを生かせば、物流事業は航空だけでなく、商社や流通、小売り、ECなどとの協業も現実味を帯びていく。JR東が物流事業に力を入れる狙いと、その先に描く戦略を追う。

東日本旅客鉄道(JR東日本)と伊藤忠商事が不動産分野での提携を発表した。2026年春をめどに両社の不動産子会社を経営統合する計画で、JR東は念願だった住宅開発に本腰を入れる構えだ。一方で両首脳の発言からは、不動産にとどまらない幅広い連携の可能性もにじむ。業界を代表する大企業同士の協業が、今後どこまで深化していくのかについて深掘りしていく。

#14
トランプ米大統領の通商政策や新造船の大量投入などを背景に、海運業界の先行き不透明感が強まっている。陸運業界も物価高や消費低迷の影響を受け、業績は低調だ。陸運・海運業界の倒産危険度ランキングを検証し、“危険水域”に入った14社の顔触れを明らかにする。

海運業界にとって2025年は、トランプ米大統領の通商政策に翻弄されっ放しの一年だった。10月の米中首脳会談で、米中貿易戦争は“一時休戦”ムードになったものの、地政学リスクにさらされている状況は依然として続いている。日本船主協会の長澤仁志会長に「決して楽観はできない」理由と、脱炭素戦略の後退への懸念について話を聞いた。

#13
航空・鉄道業界は、移動需要の回復やインバウンド増加を追い風に、過去最高益を更新する企業が相次いでいる。一見、好調だが、その足元では建設費の高騰や国内線の採算悪化といった不安要素もくすぶる。両業界の経営実態を検証し、“危険水域”に沈んだ26社の顔触れを明らかにする。

インバウンド6000万人時代に向けて、日本の空港運営は大きな転換点を迎えている。とりわけ多くの人手を要する地上支援業務では、省人化と効率化が待ったなしの状況だ。そうした中、全日本空輸(ANA)と日本航空(JAL)が貨物運搬業務の一部自動運転化に踏み切った。その狙いはどこにあるのか。

2026年は、鉄道会社が金融事業に本腰を入れるターニングポイントの年となる。東日本旅客鉄道(JR東日本)はSuicaを大幅に進化させ、コード決済「teppay(テッペイ)」を導入すると発表した。関東私鉄各社のPASMOでもテッペイが順次利用可能になる。PayPayや楽天ペイなど強力なライバルがひしめく中、鉄道系の決済サービスが存在感を高めることはできるのか。鉄道系決済サービスには「明らかなネック」がある。このネックの正体とともに、継続的に利用者からの支持を得るための条件を示す。

日系ラグジュアリーホテル「パレスホテル東京」を展開するパレスホテルの業績が、2024年に引き続き25年も好調だ。インバウンド増加の恩恵を受け、単価は年々上昇している。そんな中でパレスホテルは26年、「丸の外」に精を出す。吉原大介社長に、その真意を聞いた。

#14
パイロット不足が深刻化している。国内の資格保有者は約7100人にとどまり、その中心は50代。2030年ごろには大量退職の波が押し寄せ、便数維持すら難しくなる懸念が高まっている。そんな中、パイロットがより高待遇な海外航空会社へ転職するケースも増えている。パイロットのキャリアパス、そして知られざる日系と海外エアラインの待遇・働き方の違いの実態を明らかにする。

#11
2024年1月、日本航空(JAL)は鳥取三津子氏の社長就任を発表し、初のCA(客室乗務員)出身女性社長として大きな注目を集めた。経営破綻後、一貫して現場出身者を社長に登用してきたJALだが、ここ数年は整備不備や機材の接触事故、飲酒問題などのトラブルが後を絶たない。安全を揺るがす問題が多発する中、トップに求められる資質とは何か。JAL関係者へ取材をすると、事務系復権の兆しも見える。JALの次なる社長は誰が担うのか。候補3人の実名を公開する。

2025年3月に高輪ゲートウェイシティを開業させるなど、非鉄道事業の拡大を目指す東日本旅客鉄道(JR東日本)。26年にはICカード「Suica(スイカ)」にコード決済機能を搭載する大型アップデートを計画しており、交通系の少額決済から日常の決済手段への転換を図っている。JR東日本の喜勢陽一社長に成長のドライバーと位置付ける不動産事業の今後の展望に加え、スイカ・金融事業の発展の可能性について話を聞いた。

マンション価格の高騰に歯止めがかからない中、東京都千代田区は不動産協会に対して2025年7月、新築マンション販売時に5年以内の転売と同一建物における同一名義での複数物件の取得を制限する“異例”の要請を行った。当初、協会側は慎重な姿勢を示したが、態度に変化の兆しが見える。また、11月に入り三井不動産レジデンシャルが一部の新築マンションで転売規制を導入する動きを見せた。樋口高顕・千代田区長にマンション転売規制を要請した背景とその狙い、26年のマンション価格高騰に対する“次なる秘策”を聞いた。
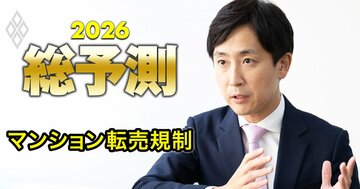
#5
J-STARは、中堅・中小企業を投資対象とするミッド・スモールPEファンドの雄として業界内でも一目置かれている。ところが、その名門ファンドで今年、前代未聞の投資崩壊劇が起こっていた。炎上案件は、医療系スタートアップのMTUである。買収完了からわずか1カ月後、J-STARはMTUの原拓也社長を「重大な疑義」により電撃解任。その背景にある“衝撃疑惑”がダイヤモンド編集部の取材で判明した。本稿では、買収後に明らかになったMTUの事業実態や不正行為に関する疑惑の数々を、投資責任者が周囲に明かした内容とともに公開する。

東日本旅客鉄道(JR東日本)が新たに発表した中期経営計画で、売上高1兆円アップの大胆な目標をぶち上げた。鉄道事業と生活ソリューション事業の二軸経営での成長を目指す一方で、1兆円のうち半分をM&Aによって補完すると宣言。財務トップの伊藤敦子副社長に、新中計で掲げる成長戦略の真意とM&Aのターゲット分野を聞いた。

#14
パイロット不足が深刻化している。国内の資格保有者は約7100人にとどまり、その中心は50代。2030年ごろには大量退職の波が押し寄せ、便数維持すら難しくなる懸念が高まっている。そんな中、パイロットがより高待遇な海外航空会社へ転職するケースも増えている。パイロットのキャリアパス、そして知られざる日系と海外エアラインの待遇・働き方の違いの実態を明らかにする。

#12
北海道と本州・九州を結ぶ航空会社AIRDO(エアドゥ)。他社同様、コスト増と単価の下落により国内線は厳しい状況が続いている。打開策として2022年10月、ソラシドエアとの共同持ち株会社設立を発表。整備の一元化やスケールメリット拡大により収益性向上を目指しているが、協業には課題も多い。エアドゥの鈴木貴博社長が、低迷する現状の打開策、そしてソラシドエアとの協業の「足かせ」について語る。

#11
2024年1月、日本航空(JAL)は鳥取三津子氏の社長就任を発表し、初のCA(客室乗務員)出身女性社長として大きな注目を集めた。経営破綻後、一貫して現場出身者を社長に登用してきたJALだが、ここ数年は整備不備や機材の接触事故、飲酒問題などのトラブルが後を絶たない。安全を揺るがす問題が多発する中、トップに求められる資質とは何か。JAL関係者へ取材をすると、事務系復権の兆しも見える。JALの次なる社長は誰が担うのか。候補3人の実名を公開する。

#10
移動需要の回復により、世界の空に再び活気が戻っている。だが、その追い風をどれだけ成長につなげられたかは、航空会社によって大きな差がある。為替や収益構造の違いが、業績の明暗をくっきりと分けたのだ。コロナ前後の世界の航空会社の売上高ランキングを作成すると、国内2強は順位を下げていることが分かった。