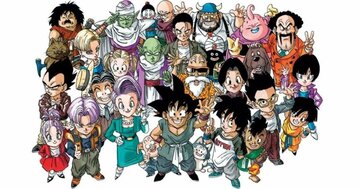Photo:Tomohiro Ohsumi/gettyimages
Photo:Tomohiro Ohsumi/gettyimages
なぜ、「ひとりディズニー」が増え、今ではすっかり定着しつつあるのでしょうか。一方で、「ひとりUSJ」はそれほど聞きません。バレンタインデーが近づいた今、ひとりディズニーについて考えてみましょう。(明治大学経営学部兼任講師 中島 恵)
バレンタインデーを前に
「ひとりディズニー」について考える
「おひとり様」市場が活況です。外食や映画、舞台鑑賞、アーティストのライブやなど、従来は誰かと出かけたレジャーに、ひとりで行く人が増えました。「ソロ活(ひとりで活動すること)」とも称されます。
コロナ禍によって誰かを誘うことが難しくなったことも、おひとり様消費の加速に拍車をかけました。ソロ・マーケティングやソロ・エコノミーという言葉も出てきています。受け入れ側も、おひとり様を歓迎し、ひとり席を設けるなどで集客しています。
筆者はテーマパークを専門に研究しているのですが、2010年頃から「ひとりディズニー」(ひとりで東京ディズニーリゾートに行くこと)をする人が増え、今ではすっかり定着しつつあると感じています。バレンタインデーが近づいた今、ひとりディズニーについて考えてみましょう。
昔からあった「ひとり旅」
シニア女性に急増するワケ
昔から「ひとり旅」という言葉はあって、一定の需要がありました。特に若い男性にとって、ひとり旅はカッコいい響きだったはずです。
先日、大手旅行会社の「ひとり旅ツアー」の売り上げが過去最高を記録したというニュースが話題になりました(「おひとりさまツアーは割高なのに、なぜ利用者が増えているのか “自己紹介なし”の理由」ITmediaビジネスオンライン2025年1月30日)。今は、シニア女性のひとり旅ツアー参加が急増しているそうです。
円安が進んだ影響で、海外ツアーはコロナ禍以前の2~3倍の値段が付くことも珍しくありません。記事によると、友人・知人を誘いにくいけれども海外に行きたい人が、利便性の高いパッケージツアーを選んでいるとのこと。
シニア層の場合、一緒に旅行に行っていた家族や友人の死亡や病気、体力低下もあって、ひとり旅を選ぶそうです。まとめると、ひとり旅の主要顧客はシニア女性で、お金に余裕があり、健康状態が良好な人に変化していることが分かります。