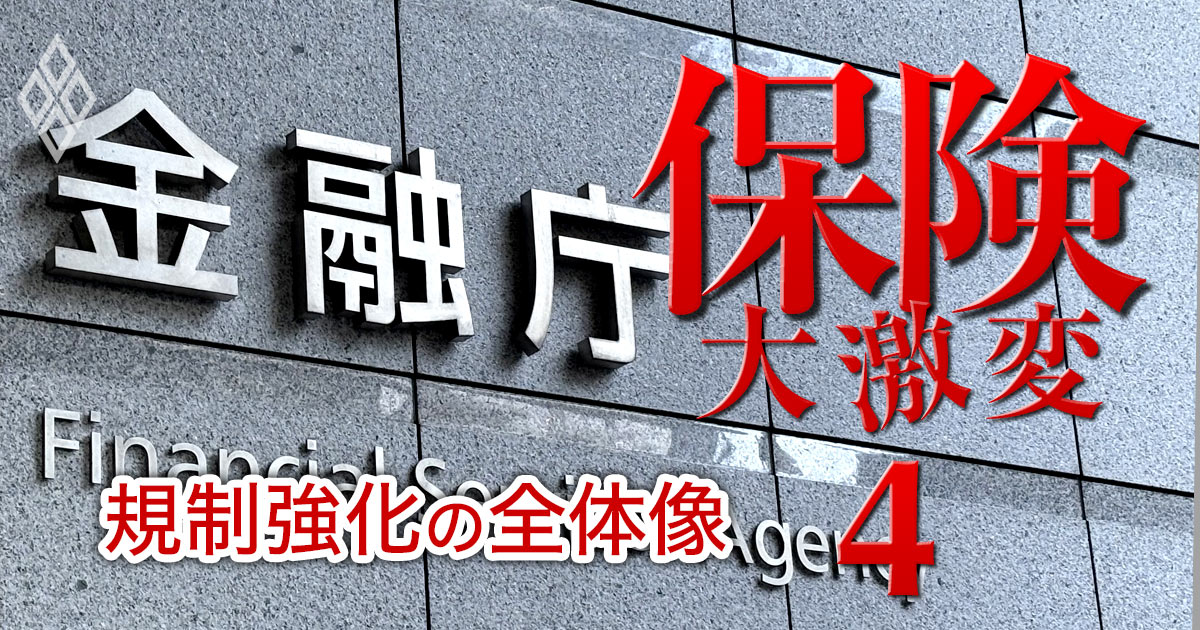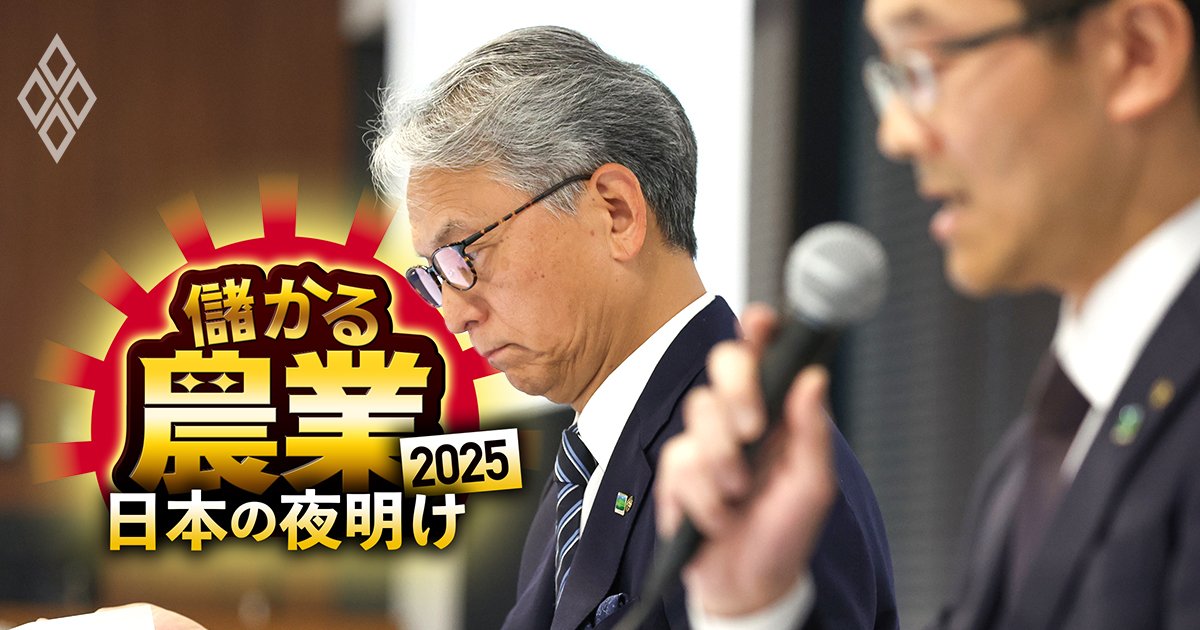プーチン氏の強権維持と
NATOへの当て付け
なぜ今、ロシアはウクライナ東部の親ロシア派地域の国家承認に踏み切ったのか。筆者は短期と中長期、二つの視点があると考える。
まず、短期的な視点は、国内の政治・経済を見据えたプーチン大統領の、「強権の維持」であろう。
資源に過剰に依存したロシア経済は、一時的な価格高による増収はあっても、長期的な展望は描きにくい。米国や中国と比べて、ロシア発の巨大IT企業の存在感はなく、イノベーションを先導しているわけでもない。経済の先行きは明るいとはいえず、国民は不満を持っている。一方、米欧諸国からはすでに経済制裁を受けており、追加制裁による影響はさほど大きくないとの見方が濃厚だ。
ロシア国内には反体制派指導者のナワリヌイ氏のような存在もいる。他方、国土が広く周囲からの侵略を恐れることから「強力なリーダー」を求めるのがロシアの国民性だ。
プーチン大統領としては、米欧に負けているような姿勢は、絶対に国民に見せられない。
中長期的な視点としては、北大西洋条約機構(NATO)の東方拡大を阻止するための、強力なメッセージ発出である。
1990年のドイツ再統一の際に、当時の西ドイツのゲンシャー外相が、「NATOは東への拡大をすべきでない」と述べている。また、米国のベーカー国務長官も、東方に拡大しない趣旨の発言をしている(ただし、解釈には幅がある)。
ドイツ再統一の際には、ロシアの承諾が極めて重要だった。そのため当時の西側諸国は、ロシアを刺激しないように、NATOの東方拡大については慎重な姿勢を示していたのだ。
しかし、この点は条約や協定として文書化されているわけではない。そのため、米欧諸国は「そのような合意はなかった」と主張しているのだ。
一方のロシアとしては、「裏切られた」と感じても仕方ないだろう。
NATOが東方に拡大しない明確な合意がないなら、ロシアは、東方に拡大させないための「強力な姿勢」を打ち出すしかなくなる。いわば、NATOへの「当て付け」である。
今後のウクライナ情勢がどのように展開していくか、予断を許さない状況だ。核保有国同士の軍事的紛争は、代償が大きすぎる。
米欧とロシアの対立が、新たな形で明確となったウクライナ危機。分断する世界を象徴する出来事として、歴史上の重要な一ページを記すことになるだろう。