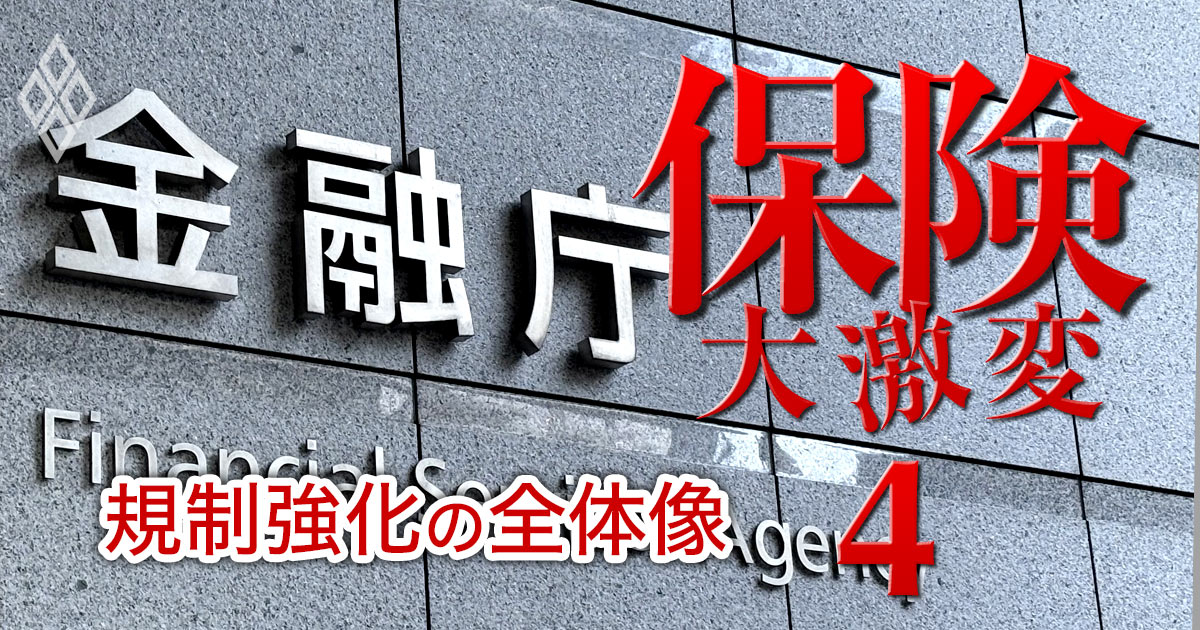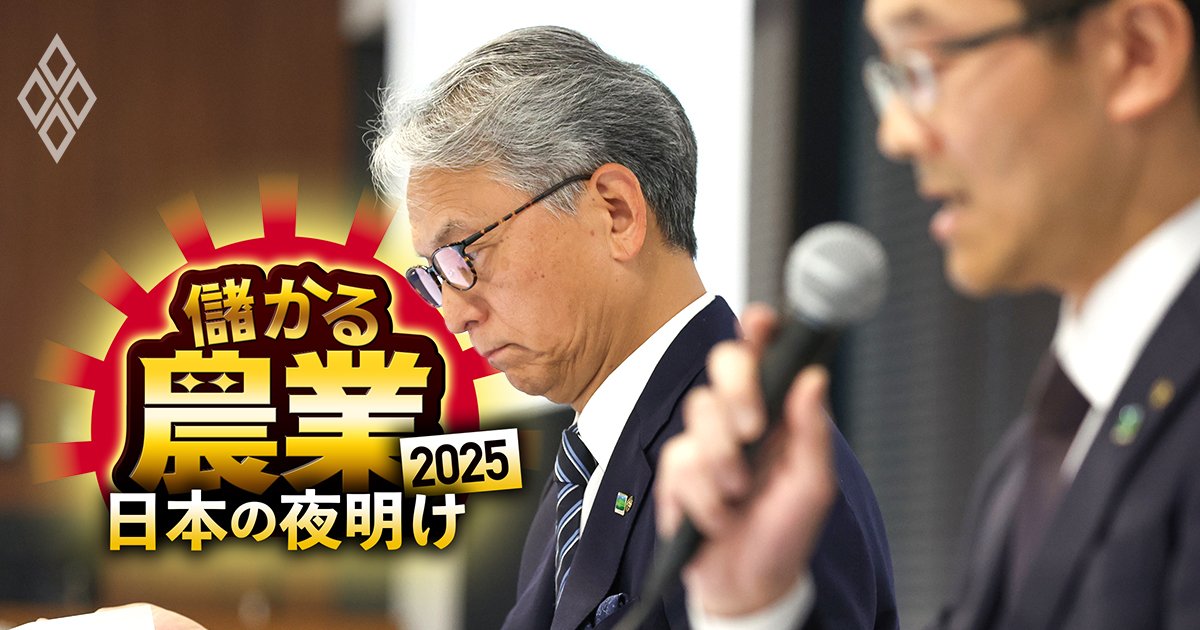兄ウクライナと弟ロシア
それぞれの複雑な感情とは
日本では、畿内と関東で別の国家となったことはない。畿内と関東で同一民族という点でも異論はない(アイヌ民族など先住民・少数民族の存在は決して忘れてはならないが)。
一方、ロシアとウクライナはたもとを分かち、言語も文化も徐々に変わっていったのだ。
そして、「弟分」のロシアが強大な帝国になり、「兄貴分」のウクライナを支配した。旧ソ連時代にも、連邦内の共和国として支配を続けた。
この点が、ウクライナから見ると、「弟分のくせに、偉そうに」となる。ロシアから見ると、「自分たちの源流であり、ロシアに近い存在」となる。
ソフィア大聖堂など正教会の重要拠点を有するウクライナが、昨今、西ヨーロッパ寄りの国になっていくことに対して、「おいおい!文化も宗教も同じ仲間なのに、何やってるんだよ!?」というのがロシアの率直な感情なのだ。
こうした因縁の関係を経て、ウクライナが独立したのは1991年。ソ連崩壊後のことだ。
ソ連崩壊は、ロシア国内では一般的に、“屈辱的なこと”として捉えられている。ソ連という大国が突如として分裂し、多くの国が独立したことで、国土や経済力が減少したからだ。独立した旧ソ連の国には多数のロシア人が居住しているが、少数派に転じたことに複雑な心情のロシア人もいる。
ウクライナとロシアとの対立は、2014年のクリミア半島併合から先鋭化している。クリミア半島もロシア人、ロシア語話者が多く、ロシアが(国家承認ではなく)併合した。国際社会の同意は得られていない。