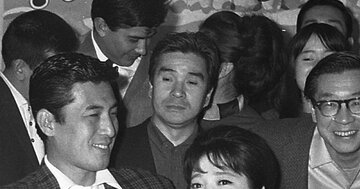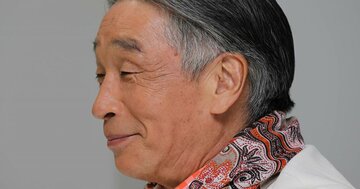だから僕は、自分がやるべき芸を決めたら、まずはその演目の歴史を紐解き、考えついた人が誰なのかを知るところから理解を深めた。それからその人へのリスペクトの気持ちを持って練習に励んだ。
1976年のことだ。『新春かくし芸大会』内で初めて披露する僕の個人芸が、曲独楽に決まった。コマ回しの芸なのだが、これが思った以上に難しい。手に何度もマメができ、皮膚が剥がれ、治ったと思ったらまたできて……と怪我の繰り返しで、つらいなんてものではなかった。
痛みに蓋をして、何度も何度も繰り返しトライするしかない。日程も迫っていて、途中で休む日も設けられないのだ。でも、その痛みの先には大きなご褒美が待っていた。
できなかった芸ができるようになれば、師匠や関係者から心底びっくりされ、手を叩いて満面の笑みで喜ばれ、そしてほめられる。そのときの達成感と快感といったら!習得した芸で食べていくつもりなんてまったくなかったものの、こういう芸事が僕は本当に好きなのだとこのとき実感した。
太神楽、ジャグリング、ボイスイミテーション、大工演奏会、カクテルパフォーマンス、トランプ技、コンダクター、ミラクルチャレンジゴルフ、帽子芸、手品、ピザ生地の芸、サイコロ芸、中国の木琴、ホールインワン……。数々の難しい演目に挑戦してきた。
年々、難度の高い演し物を
披露する羽目に……
高下駄でタップダンスをしたこともあったが、これは歌舞伎の舞踊劇「高坏」からヒントを得たものだ。昭和初期に初演されて以来、しばらく途絶えていた演目だが、17代目の中村勘三郎さん(現在の勘九郎さんのお祖父様)がNYで披露するために復活させた。台詞のない、しかしおかしみのある舞踊劇は、大変ユニークな上に、外国人にも理解しやすい。これは日本人らしい素敵な演目だなと思い、やらせていただいた。
思い出深いのは、1997年、52歳で挑戦したローリングバランスだ。円柱形の金属の上に乗せた不安定な三段の板の上で行う芸であり、高さがあるぶん大変危険で、怪我と隣り合わせであった。これは30代でもう手を引くべき芸だと周囲からは強く忠告され、当時の家族からも、「私たちとかくし芸とどっちが大事なの」ときつく叱られた。