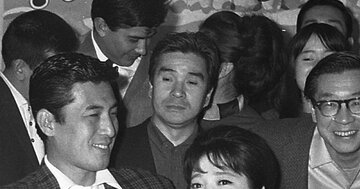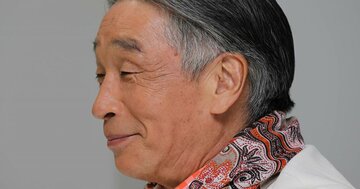そして、芸が出来上がったとしても、まだなにか加えられるものがないかと、そこに別の要素をさらに上乗せして、つけ足して……とついつい深追いしてしまう。
芸事は、画家や作家の仕事と同じで、終わりがない。そして、披露する前に助走をつけたり、芸に磨きをかけたりしている過程は見せたくない。きれいな完成形だけ見せる方が、さりげなくていいのではないかと思ってしまう。でもあるとき、かまやつさん(編集部注/かつてザ・スパイダースのメンバー仲間だった故・かまやつひろし)から、「かくし芸の練習の最中はいつもピリピリしていたから、年末はいつも声をかけにくかったよ」などと言われたことも覚えている。
会得した芸の数々は
番組で見せたらそれで終了
そうして練習の末、会得した芸の数々。僕の場合は、番組で見せたらもうそれで終わりであり、未練は一切残らなかった。
教えてくれた先生方は、「よくやった」とほめてくださり、道具を下さることも多かったが、次にそれを使う場所はないのだ。披露すると同時に手放してしまう芸なのに、僕はその都度、本番に向かって高みを目指し、集中力を高めていた。時が過ぎれば消えてなくなる芸、そういう刹那的な感じにも魅了されていたのかもしれない。
もっとも、僕が習得した芸は、必ずしも跡形もなく消えてなくなってしまうわけでもないらしい。
ある年のかくし芸大会で披露した中国の京劇は、目覚ましい出来栄えで評判もよかった。ドラマの『西遊記』とどちらが先だったかは忘れたが、そのとき演じた京劇でも、僕は中国の伝統的な演目である『西遊記』をやり、如意棒に見立てた棒を振り回すため、棒術の稽古を積んでいた。ドラマの方の『西遊記』への出演とも相まって、やがて棒術は、僕の得意技のようになっていった。
それから長いブランクを空けて、この前、あるTV番組で久々に棒術を披露する機会を持ったのだが、40年も前に仕込んだ芸でも体は意外と覚えているもので、出来栄えは上々だったので、自分でも驚いた。最近は、綿棒くらいしか持ったことがなかったのに。
芸事で僕が強い影響を受けたのは、アメリカ出身のコメディアンであるジョージ・カールさんだ。さまざまなサーカスに同行しながらヨーロッパで大成功をおさめた人で、40年ほど前にビデオでその芸を見てすっかり心を打たれてしまった。