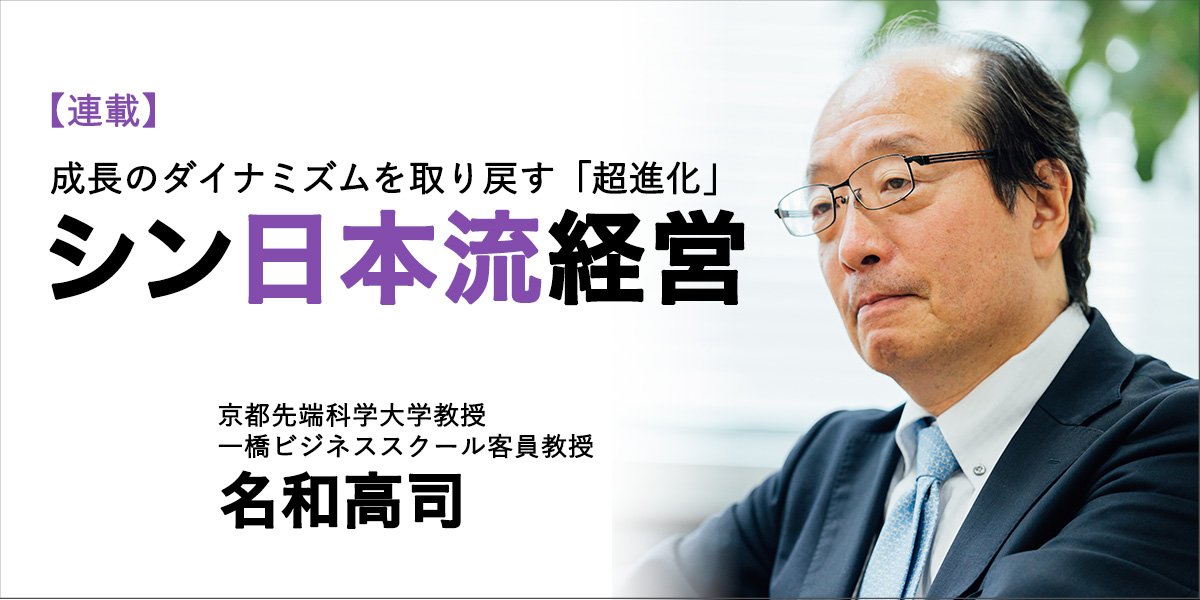
なぜいま「シン日本流経営」が必要なのか──
日本流経営は優れた元型を持ち、利他心、人基軸、編集力という日本ならではの「本(もと)」を軸に守破離(しゅはり)を繰り返し、世界で存在感を示してきた。では、なぜ多くの日本企業がそれを見失い、平成、令和という2つの時代を通じて競争力を低下させ続けることになったのか。
「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と持ち上げられたのもつかの間。バブル崩壊とともに一気に自信喪失に陥り、アメリカ流の株主至上主義に思い切り舵を切っていった。日本流を封印し、「世界標準」モデルを取り入れようとした結果が、平成の失敗を招いてしまったのである。
そもそも世界標準というものは、世の中に存在しない。取り返しがつかなくなる前に、我々は日本流の本質を取り戻し、それを「シン日本流」にアップデートさせる知恵を発揮しなければならない。
第2回はこちら
「シン日本流」を定義する
「シン○○」という言葉は、まさに「シン日本語」となっている。火付け役は、庵野秀明監督だ。まず『シン・ゴジラ』(2016年)が大ヒット。その後も『シン・エヴァンゲリオン劇場版』(2021年)、『シン・仮面ライダー』(2023年)と、「シン」シリーズを立て続けに打ち出している。
経営の世界で「シン」ブームを巻き起こしたのは、安宅和人氏の『シン・ニホン』だ。「AI×データ時代における日本の再生と人材育成」という副題のついた本書は、まさに「シン」という名にふさわしい名著である。
 名和高司 Takashi Nawa
名和高司 Takashi Nawa京都先端科学大学 教授|一橋ビジネススクール 客員教授
東京大学法学部卒、ハーバード・ビジネス・スクール修士(ベーカー・スカラー授与)。三菱商事を経て、マッキンゼー・アンド・カンパニーにてディレクターとして約20年間、コンサルティングに従事。2010年より一橋ビジネススクール特任教授(2018年より客員教授)、2021年より京都先端科学大学教授。ファーストリテイリング、味の素、デンソー、SOMPOホールディングスなどの社外取締役、および朝日新聞社の社外監査役を歴任。企業および経営者のシニアアドバイザーも務める。著書に『学習優位の経営』(ダイヤモンド社、2010年)、『パーパス経営』(東洋経済新報社、2021年)、『稲盛と永守』(日本経済新聞出版、2021年)、『資本主義の先を予言した 史上最高の経済学者 シュンペーター』(日経BP、2022年)、『桁違いの成長と深化をもたらす 10X思考』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2023年)、『超進化経営』(日経BP 日本経済新聞出版、2024年)、『エシックス経営』(東洋経済新報社、2024年)、『シン日本流経営』(ダイヤモンド社、2025年)など多数。
一方、ウリケ・シェーデ氏の『シン・日本の経営』(日経BP 日本経済新聞出版)が話題となったことも、記憶に新しい。もっとも、同書は日本のディープテック(社会課題の解決など、社会にインパクトを与える科学的発見や革新的な技術)に注目するだけで、日本をよく知る者にとって「シン」味はまったくない。
シェーデ氏の書籍に先立って、『シン・日本的経営』(東洋経済新報社)というムック本が出版された。作家、学者、経営者など、各界識者のインタビューのアンソロジーとなっている。こちらのほうは、本質に迫った問いかけが幾重にも織り込まれている。その中で筆者も、「企業は欧米流の経営手法とどう向き合うべきか」と銘打った章に登場している。ちなみに結論から言えば、欧米流を世界標準などという卑屈な呼び名で崇めてはならない、と論じている。
これらで使われている「シン」は、「新」を意味することは言うまでもない。「次世代」と言い換えることもできる。「異次元」とまで言うほどの革新性はない。これまでの伝統を受け継ぎつつ、バージョンアップを図るイメージだ。
「我々の力と云うのは、破壊する力ではありません。 造り変える力なのです」
『神神の微笑』の芥川龍之介の言葉を借りれば、「破壊」ではなく「造り変える」ことを意味すると言ってもいいだろう。
そしてそれが、「日本流」という次の言葉につながる。日本的でも、日本式でもなく、「日本流」という表現にこだわりたい。なぜなら、これまで論じてきた日本特有の「流儀」を指すからだ。

![[検証]戦後80年勝てない戦争をなぜ止められなかったのか](https://dol.ismcdn.jp/mwimgs/9/8/360wm/img_98a65d982c6b882eacb0b42f29fe9b5a304126.jpg)





