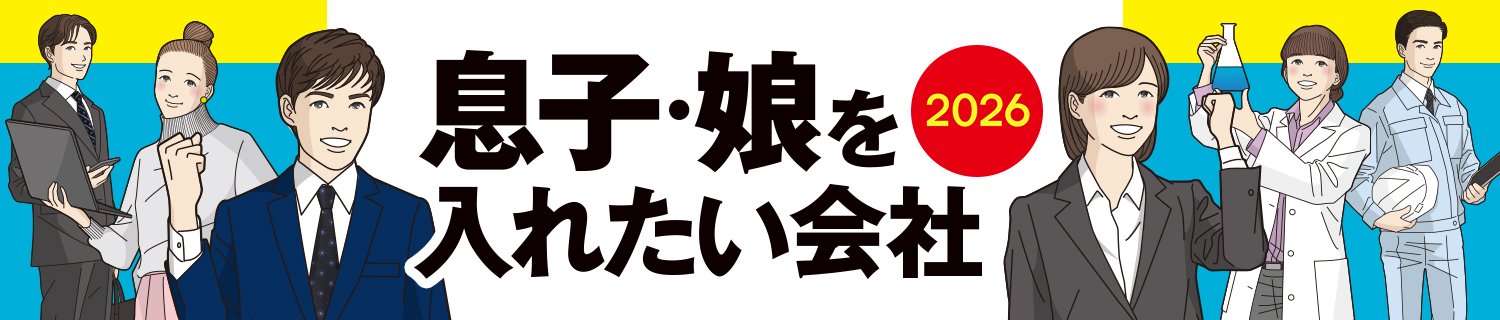26年卒向けのインターンシップからは、さらに見直しが行われた。ポイントは、春休み以降に実施される一定の条件を満たす2週間以上の「専門活用型インターンシップ」(タイプ3の一部)では、参加した学生の情報を3年生の3月から選考に活用し、内定を出してもよいことになったのだ。
ただし、2週間以上という要件は、プログラムの準備や現場の受け入れなどの点で負担が大きく、多くの企業は慎重といわれる。
一方、こうした要件に当てはまらないプログラムは「オープン・カンパニー」(タイプ1)や「キャリア教育」(タイプ2)といった名称になった。こちらの参加者については、改めて本採用へエントリーしなければならない。
インターンシップに参加できなかった…
でも内定を諦める必要はない
注意が必要なのは「インターンシップ」「インターン」という言葉が使われていても、それが上記のタイプ分けを踏まえたケースと、そうではない(全てを指す)ケースが混在していること。面倒だが、どちらのケースか確認しよう。
以上のような多少の曖昧さはあるものの、就活生の間ではインターンシップへの関心が強まっており、DHRの調査によると、平均参加回数は、24年卒の6.9回が25年卒では8.6回になっている。また、インターンシップに参加した企業に入社を決めた就活生の割合も、24年卒の34.9%から25年卒では40.6%と、着実に増えている。
今やインターンシップは就活における重要なステップとして定着したといえる。インターンシップを巡ってぜひ指摘しておきたいのは、インターンシップに参加しなければ内定(内々定)が取れないわけではないということだ。
インターンシップはもともと、「大学教育の一環としてのキャリア教育の機会」という位置付けだが、実際には企業研究を早い段階から進めたい学生と、学生との接点を早く持ちたい企業が出合う場となっている。