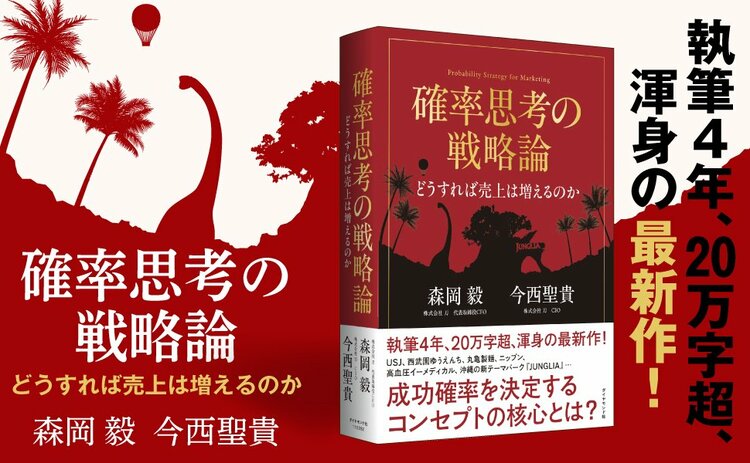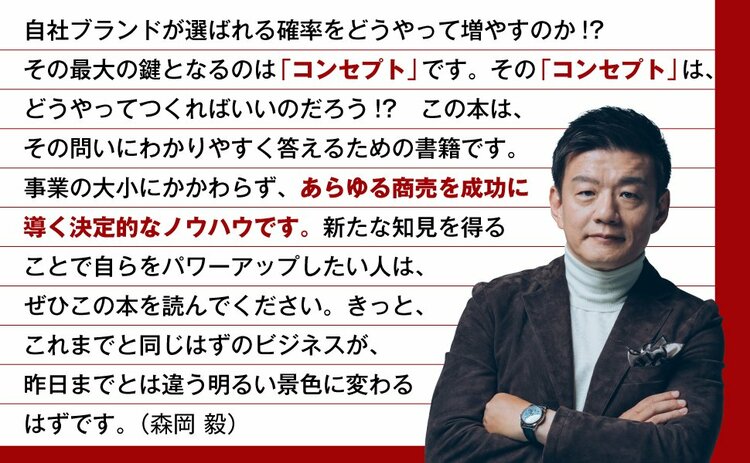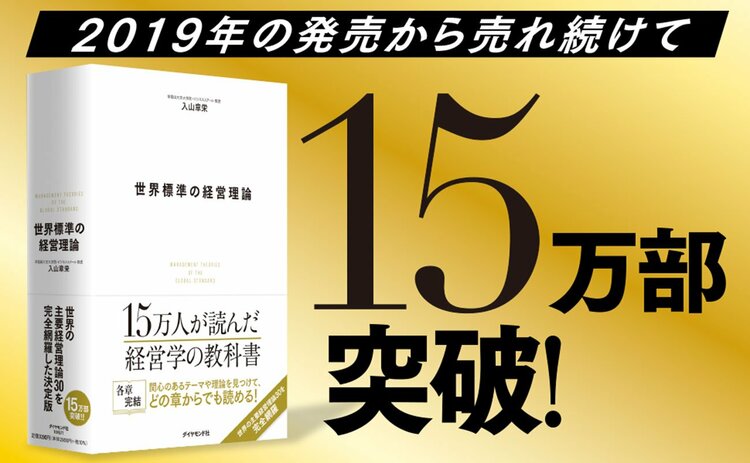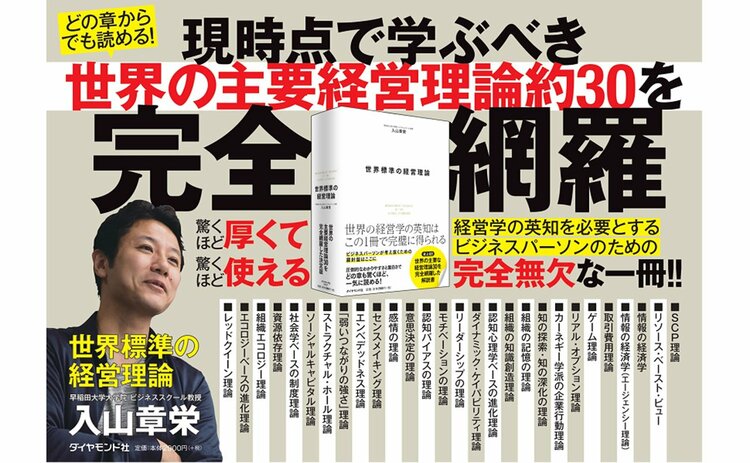コンテンツはストーリーの理解だけじゃ足りない
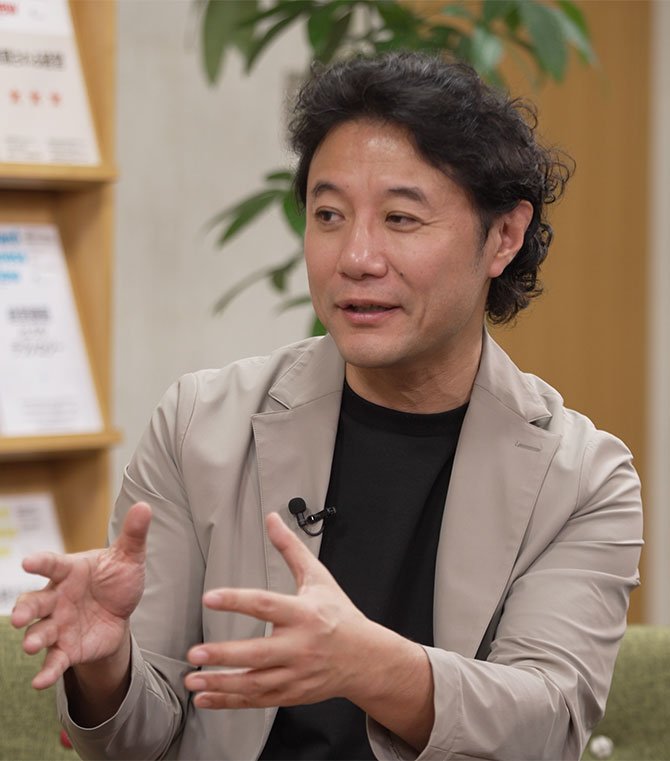 入山章栄(いりやま・あきえ)
入山章栄(いりやま・あきえ) 早稲田大学大学院経営管理研究科、早稲田大学ビジネススクール教授
慶應義塾大学卒業、同大学院経済学研究科修士課程修了。三菱総合研究所でコンサルティング業務に従事後、2008年 米ピッツバーグ大学経営大学院よりPh.D.(博士号)取得。 同年より米ニューヨーク州立大学バッファロー校ビジネススクール助教授。2013年より早稲田大学大学院 早稲田大学ビジネススクール准教授。2019年より教授。専門は経営学。国際的な主要経営学術誌に論文を多数発表。メディアでも活発な情報発信を行っている。
入山 ほかに、これまで憑依したエクストリームな人というのは、どんな例がありますか。
森岡 いっぱいありますよ。たとえば、大人気だった『けいおん!』というアニメーションのファンの方とかですね。それはUSJで『けいおん!』をイベント化する企画が出てきたときのことなんですけど。恥ずかしながら全く知らなかったので、まずは勉強するためにDVDを借りてきて見たんですね。それを借りるときも、自分で借りるのは気恥ずかしくて、当時まだ小さかった子どもに取りに行ってきてもらったりしたんですけど(笑)。恥ずかしいと思った自分が、今思えば、マーケターとして恥ずかしいですよね。
入山 いや、恥ずかしいと思うのは普通だと思います(笑)。
森岡 これが実際に作品を見てみると、遠い昔に置いてきた青春時代のフレッシュな思いが見事に美しく描かれていて、素晴らしいコンテンツだなと思いました。次に、この作品のファンの皆さんは、登場するキャラクターの誰の、どこが、どう、なぜ好きなのか知りたくなりまして、ファンが集うオフ会に紛れ込んだわけです。もう、こうなると必死なので全く恥ずかしくない。いろいろ教えてもらわないといけないから。
入山 (爆笑)
森岡 だって、コンテンツを理解するには、ストーリーを理解するだけじゃ全然足りないですよ。それを好きな人がコンテンツを見たときに、何が本能に刺さっているのかという消費者理解がないと、パーク体験として再現できない。『ONE PIECE』もUSJでショーを展開したんですけど、これもすごいコンテンツで、あそこに描かれている普遍性はずっと残ると思うんです。仁義の世界ですよね、江戸時代の芝居の脚本にも通じるような。日頃頼りなく思える船長が、いざというときには頼りになって最後は勝つわけじゃないですか。誰もがこうありたいと思う人間の本質を、尾田栄一郎先生の超絶なる情熱と集中力で描かれている。
入山 ある方に聞いてなるほどと思ったんですが、日本のコンテンツですごいのは、特に少年バトル系では、倒した敵がそのあと仲間になるところだ、と。ハリウッドだと、敵は敵のままなんですよね。敵を味方につけるというのは、人間が社会的に本当に求めていることの1つで、その話をちばてつや先生にしたら、「『アンパンマン』が人気になる国は平和になるんだ」とおっしゃったそうで、なるほどなと思いました。
森岡 たしかに、日本人特有の寛容の精神が描かれるというか。米国のコンテンツだと悪役は最後に死にますよね。
日本のコンテンツのストーリーの素晴らしさや、扱っているテーマの普遍性、それを面白く見せるための表現方法などは突出していると思います。しかも粒ぞろいのクリエイターの中から選りすぐりが抜きんでてくるシステムですから、世界中がマンガ文化に参入してきてますけど、ちょっとやそっとじゃキャッチアップできないだろうし、日本の宝だなと思います。ゲームの世界は、大陸資本が大作をバンバン作っていて、日本の優位性も危ういなと思ってますけど。
クリエイター・エコノミーに確率論で挑む
入山 日本がこれだけマンガ大国になった背景として大きかったのは、実は世界で一番書店が多かったことらしいです。われわれも子どものころ書店で少年誌を買う習慣があったじゃないですか。あのインフラがすごく効いていたそうです。
森岡 私もマンガが大好きでずっと買ってましたし、すごくわかります。江戸時代からの識字率の高さも書店の多さに関係してるんですかね。そういう日本の文化レベルの高さは素晴らしいですよね。
実は今、関連の出版社さんに了承を得たうえで、ネット上の創作物をベースに、次にどの作品がヒットするかを発売から1か月ぐらいで見破ることができるモデルを構築中なんです。どんな指標に着眼して定点観測すれば、ヒットする作品を見つけられるのかがわかれば、早期にそういうヒット予備軍の作品に投資して一気に飛躍させることができるじゃないですか。ただ、私のプライベートワークなのでなかなか進められてないんですけど。
入山 面白い! それができたらすごいですね。日本のクリエイティブ・コンテンツがこれからもっと世界に出ていくだろうという中で、最近も放送作家の鈴木おさむさんがファンドをつくって資金を集めてたりしますよね。
これからのクリエイター・エコノミーの時代において、この作品がヒットすると見抜く「目」になるのは、プレーヤーとして頂点を極めた感度の高い人が最適だろうと思うので、すごく良い取り組みだなと思ったんです。森岡さんのアプローチは、それを確率論のアプローチによって最短距離で目指すという真逆の考え方ですが、それもめちゃめちゃ良いですね。
森岡 ある命題をサイエンスで追究するのが私は好きだから、この方法を取るわけなんですけど、両方のアプローチがあるというのは経営者でも言えますよね。「商才がある」と表現されますが、彼らの頭の中では見ているけれど周りには見えてなくて、その人が健在のうちはうまくいくのだけれど、彼が弱ると企業の業績も悪化する。
入山 しかも、そういうタイプの方の多くは言語化ができないんですよね。
森岡 そうなんです。そういう経営者の才能は素晴らしいし、元気なうちはフル活用していいんだけど、別のアプローチがあってもいいはずです。彼らの判断基準を、普通の人が扱える論理として法則化できたほうがいいですよね。
凡人の意識を全体の2~3割に集中させるために、あとの7~8割のことはサイエンスで整えられる気がするんですね。サイエンスでわからないところをみんなで必死で考えることによって、成功確率が上がるんじゃないかなと思うんです。その鈴木おさむさんのプロジェクトも、彼の選球眼の7~8割をサイエンスで解明したうえで、残りの2~3割に彼の思考を集中していただくような掛け算の形にできると、さらに素晴らしい成果を上げられそうな気がします。
<次回は5月8日に【森岡毅×入山章栄対談(5)】を公開予定>
【――本対談シリーズの過去掲載分はこちら――】
・第1回「テーマパークが好きな人」と「テストステロン」の切っても切れない深い関係とは?
・第2回「結果が出る人」と「うまくいかない人」の“努力の中身”の決定的な違い
・第3回 スマホゲームに“限界”まで課金してわかったこと 森岡流の消費者理解