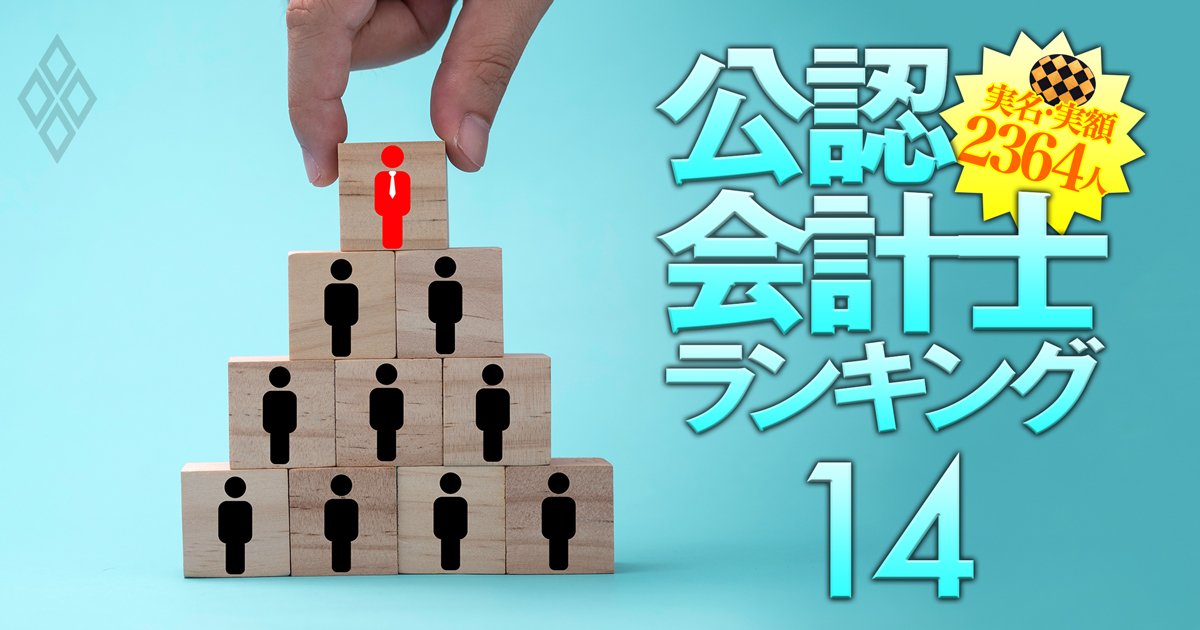このような現状認識に基づき、筆者は個人的に「(今のままのフジテレビ、あるいは同様の問題を抱えるテレビ局の番組は)見たくない」という結論に至りました。
これは単なる好き嫌いの問題ではありません。私たちが日々受け取る情報は、無意識のうちに自身の考え方や価値観に影響を与えます。人権を軽視し、ゆがんだ価値観を発信する可能性のあるメディアからの情報を、自身の情報源として選びたくない、という強い意思表示です。
これは、情報過多の現代において、どのような情報源を選択するかというメディアリテラシーの重要性を改めて認識させる問題でもあります。
「基準上は問題ない」で終わらせない
会計専門家としての真の責任は?
最後に、今回の事案と第三者委員会の報告書が、フジテレビにとって根本的な企業体質・組織風土を見直し、変革するための大きなきっかけとなることを期待します。
表面的な謝罪や対策にとどまらず、人権尊重を最優先事項とし、透明性の高いガバナンス体制を構築すること、そして何よりも、社会に対して責任ある情報を発信するメディアとしての自覚を取り戻してほしいと思います。
上場企業として社会から信頼を得るためには、「法的に問題ない」「会計基準上は重要性がない」というテクニカルな判断だけでは不十分です。特に今日のステークホルダー資本主義の時代において、企業の社会的責任や倫理観はますます重要視されています。
フジテレビ問題を機に、私たちは内部統制の形骸化やガバナンスの機能不全について改めて問い直す必要があるでしょう。専門基準と社会常識の間にある溝を認識し、それを埋めていく努力が、私たち専門家には求められているのではないでしょうか。
単に「基準上は問題ない」で終わらせるのではなく、「本当にこれでいいのか」と問い続けることこそ、会計専門家としての真の責任なのかもしれません。そして、メディアにも同様の自問自答が求められるのです。
会計監査の枠を超えて、社会が本当に求める「信頼性の保証」とは何か――その問いを真剣に考える時が来ているのです。