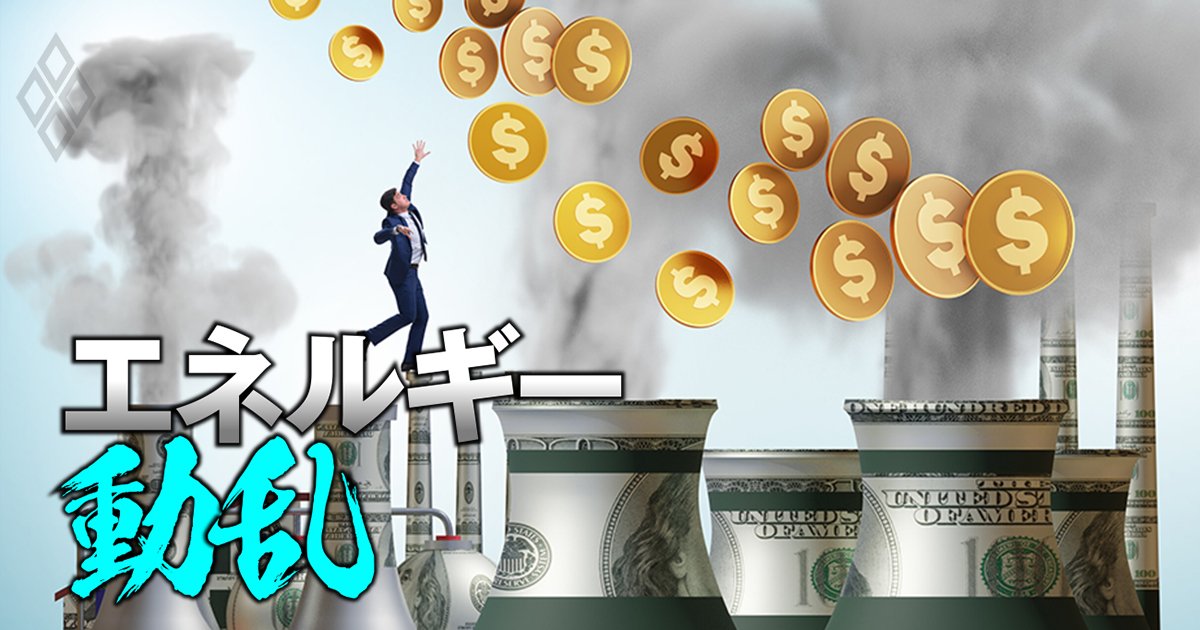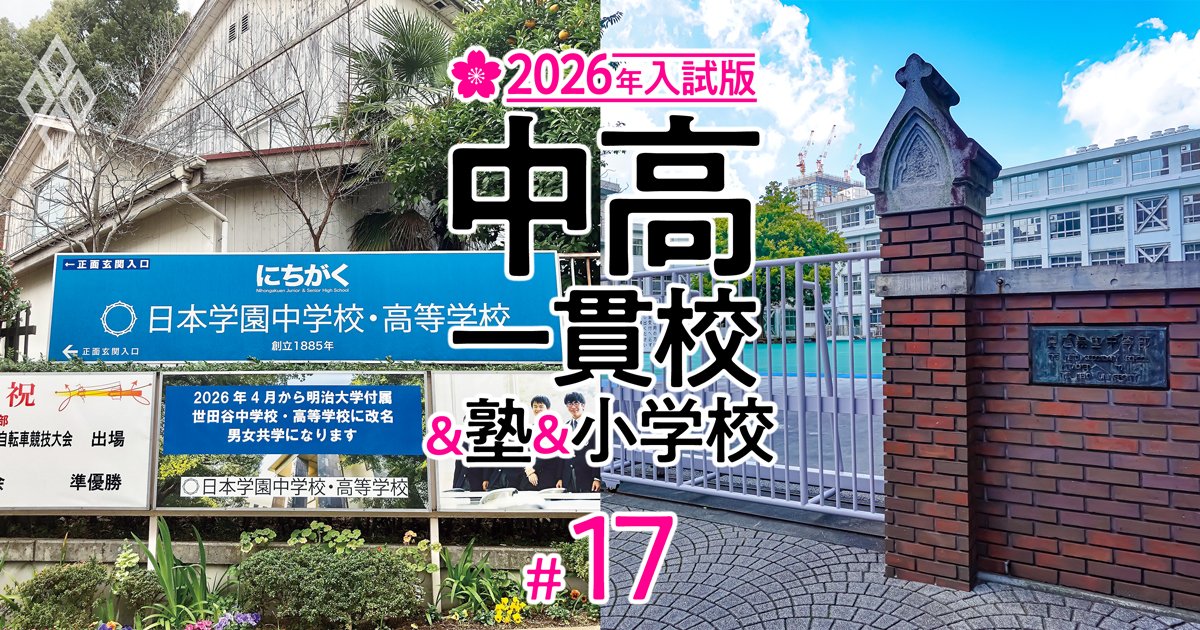「静かな退職」は労働者が自分のメンタルを守る術だとも言えますし、転職の可能性を考えるのは、生き方の選択肢を持っておくという意味で悪いことではありません。しかし企業側から見れば、深刻な事態です。「気持ちよく働いてもらうことができなければ、社員が次々にいなくなるかも」という危機感を持ってほしいと思います。
大事な部下を預かる立場としては、メンタル不調者や静かな退職者を出さないように、心がけるべきです。各自がウェルビーイングを保ちながら働き、業績の向上に貢献してくれることが望ましいのは言うまでもありません。何よりも、自身が部下のウェルビーイングを損ねる原因にならないよう、気を付ける必要があります。
営業職の若いビジネスパーソンが上司を助手席に乗せて運転中、赤信号で止まったところ、頭をポコッと叩かれて、怒られたそうです。
「なんで、こんなところで止まるんだ?」
ちょうど、助手席に陽が当たる位置だったらしいのです。しかしもちろん、若い部下の責任ではありません。私がその上司と面談したら、悪びれもせずに言われました。
「自分もそういう風に育てられたから」
私はびっくりしましたけれど、令和のいまも実在する上司の話です。「パワハラの研修は受けていますか」と訊くと、「何回も受けている」という答え。これは極端な例ですが、自分は該当しないと思っているから内容が頭に入らず、「研修会に出てるから大丈夫だ」という意識だけが残るのです。誰もが一度、我が身に置き換えて考えてみるべきです。
また、そういう人に限って仕事のスキルはあったりするので、「いいじゃないか、あいつはそのくらいで」と野放しにしがちなのが、日本の企業の問題点です。
部下と接する際、やってはいけないコミュニケーションの典型が、ダブルバインド。つまり、矛盾したメッセージを与えて混乱させることです。よくあるケースは、会議の前に「若者も自由に意見を言いなさい」と言われたので発言したら、あとから「なんであんなこと言うんだ?」と言われるケース。このように言動が一貫しない上司は、部下にとって一番の困り者です。