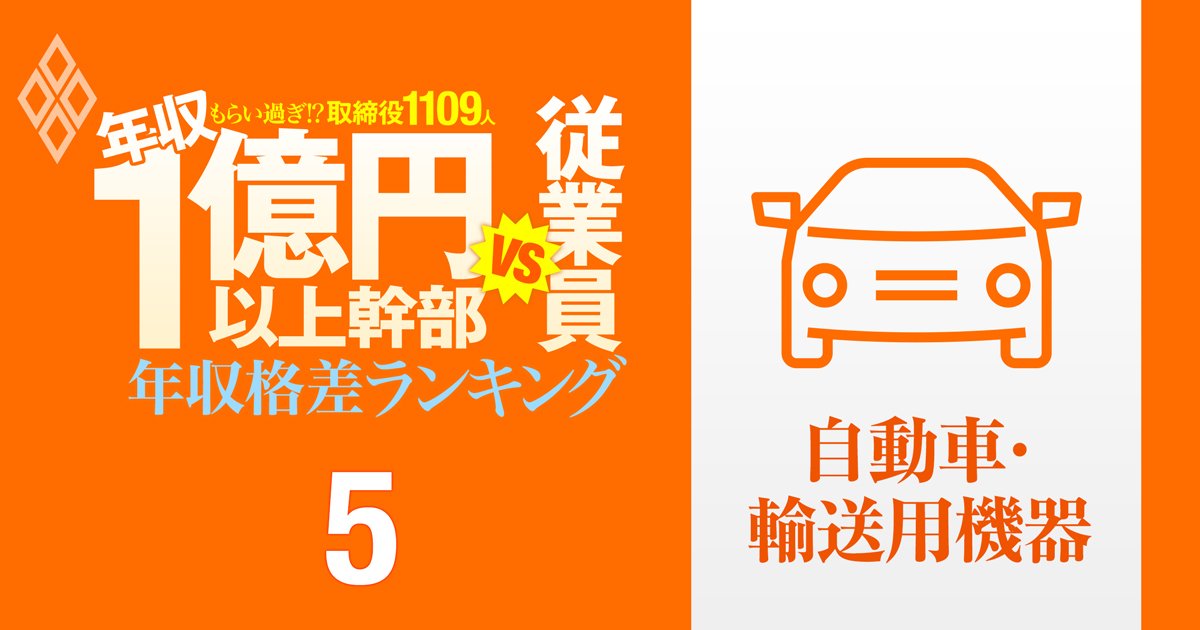仕事に対する価値観の変化
キャリアコンシャスな若者
かつては誰もが知る大企業に就職したり、地方自治体の職員や教師など公務員になったりすることは「絶対安泰」と思われていました。しかし今や、そのような「所属先に安定を求める」価値観は崩れつつあります。代わりに「よって立つもの」が自分自身になったのです。
これを私は「キャリアコンシャス(キャリア意識の高さ)」と呼んでいます。実際のデータを見ても、「自律的にキャリアを形成していく」という意識や行動は20代が最も高く、年齢が上がるにつれて低下していきます。これはパーソルのキャリア自律度調査でも男女ともに同じ傾向が見られます。
新卒学生の企業選びの軸を調査した結果でも、「自分が成長できそうか」という項目が毎年上位にランクインしています。これは、社会不安が多い世の中(地震、テロ、不景気など)で育ち、SNSなどで情報が常に流れる環境にあることが、キャリアに対する意識の高さに影響していると考えられます。
また、今の若者は「ソーシャルネイティブ」です。消費者庁の調査によれば、15〜29歳では95%がSNSを利用していて、約80%は1日1時間以上利用しています。複数のアカウントを使い分け、直接会ったことのない人とやり取りする中で、同世代間での自分の位置づけが可視化され、自信を失いやすくなっています。
ただし、彼らの「成長したい」という思いは漠然としたものであることが多いようです。具体的なキャリアイメージを持っている若者はほとんどいません。その漠然とした不安が「成長」という言葉に集約されているのです。
しかし、これを単に「若者が甘い」と責めるべきではありません。時代背景を考える必要があります。
かつては将来が見通しやすく、「この会社で30年いたら退職金がいくらもらえる」「何歳でマイホームが買える」といった予測が立てやすい社会でした。対して今の若者はコロナも経験し、不確実で曖昧な社会で思春期を過ごしてきました。
今の若者は絶対的な正解がない、「価値相対主義」的な社会で生きており、多様な生き方が認められる反面、何を選んでもよいとなると、何を根拠に選んでよいかがわからなくなり、自分のキャリアについてより丁寧なガイドを必要としているのです。
だからこそ、ホワイトな職場で「緩い」仕事を与えられるだけで放置されていると、成長できないのではないかという不安が募るのです。