
八代尚宏
高市早苗首相は1月23日の衆院解散と総選挙を表明し、政策転換と連立再編の是非を国民に問う構えだ。所得税の壁引き上げや食料品の消費税2年ゼロなど減税公約の財源を、赤字国債に頼らず歳出削減で本当に捻出できるのか。加えて、給付付き税額控除、労働・外国人制度、少子化や農政まで、制度横断改革を争点とすべきだろう。

自民・維新・国民民主・公明の4党合意に基づき、所得税の非課税枠の上限を160万円から178万円へ引き上げる方針が税制改正大綱に盛り込まれた。だが目的を「物価対策」とするなら、インフレ下の減税はむしろ物価を押し上げかねず、恩恵も中間層に偏る。矛盾を解消し、低所得層に重点を置いた減税策の給付付き税額控除の具体像を示す。

高市政権が掲げる「労働時間規制の見直し」は公平な働き方の観点からも検討すべきである。労働者が自らの意思で働き方を選べる「選択的自由」を重視した制度設計こそが真の働き方改革である。欧米の制度との比較から、今後の政策設計の方向性を探る。

与野党で導入機運が高まる給付付き税額控除(負の所得税)は、最低所得を実質的に保障しつつ就労インセンティブを損なわない“自動安定化装置”だ。基礎控除拡充などの一律減税よりも低所得層に資する再分配を実現し、行政のデジタル化とも親和性が高い。日本版の設計案と導入課題を具体的に検証する。

国民年金の財政基盤は脆弱(ぜいじゃく)である。納付率の改善が報じられるが、その内実は免除者の急増による「見かけ上の納付率」に過ぎない。基礎年金の全額国庫負担、すなわち税方式による抜本的な改革の必要性が高まっている。

2024年の人口動態統計で、日本人の出生数がついに70万人を下回った。合計特殊出生率も大きく低下し、少子化が加速している。これは年金制度の持続性にも重大な影響を及ぼし、「百年安心年金」の前提を根底から揺るがす。年金制度全体の見直しと、共働き前提の社会制度改革が急務である。
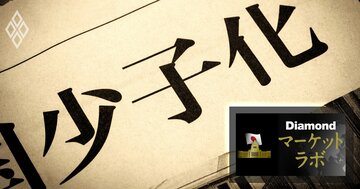
政府は2024年度年金財政検証を基に年金制度改革法案を国会に提出する予定だ。被用者保険の適用拡大などが盛り込まれているが、いずれも制度の根幹に踏み込む抜本的改革には至っていない。少子高齢化の進行が続く中、支給開始年齢や給付水準、さらには制度の財源構造そのものを再設計する必要性が高まっている。

社会保障審議会年金部会は、第3号被保険者制度の廃止を年金法改正案に盛り込まないことを決定した。サラリーマンの配偶者が保険料の負担なくして基礎年金を受けとることができるこの制度は、不公平で、かつ就業抑制の原因となり、廃止すべきである。しかし、廃止どころか制度を存続させることによるツケを企業に負わせることが検討されている。
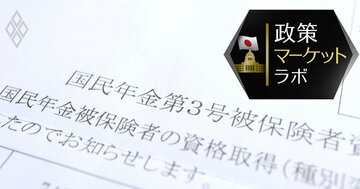
岸田内閣は人へ投資の一環としてリスキリングに5年で1兆円の資金を投じる。しかし、現在予定されている方策では生産性向上や賃上げを実現するのは困難だろう。成果を上げるために政府がなすべき4つの施策を提案する。
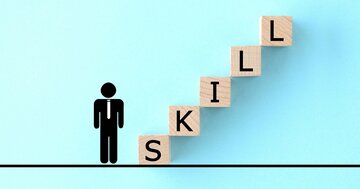
週休3日制導入を表明する企業が現れ始めた。導入時に重要になってくるのが働き方を含めた人事管理である。これまでのあり方を大きく変える導火線となる公算は大きい。
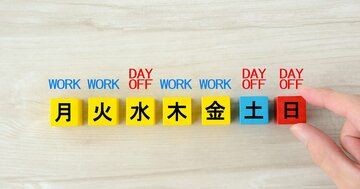
与党から中高所得層の年金受給者を対象にした5000円の一律給付案が出ている。選挙目当てのバラマキ政策であることは一目瞭然。かつ、高齢者を愚弄するものであると言わざるを得ない。

岸田政権は「中間層を手厚く」することを目標に掲げる。そのために、官が民に介入する施策を打ち出している。しかし、官の民への介入は失敗の歴史だ。むしろ、岸田政権が転換を主張する「新自由主義」において進められた規制改革こそが重要である。規制改革によって経済成長を高めることが、中間層を厚くするための取るべき施策である。

自民党総裁選への立候補者の間での政策議論が乏しい。新首相ともなる新総裁は、今後の日本の針路を示すべきである。安倍長期政権が手を付けなかった供給面の構造改革や、医療・年金などの社会保障改革、財政健全化など痛みを伴う施策から目を背けてはいけない。

菅内閣は少子化対策の切り札として「子ども庁」構想を打ち出した。そこで重要なのは保育の福祉からサービスへの転換である。一足先にその転換を果たした介護同様に、家庭の置かれている状況に関係なく利用でき、低所得者を除き適正な水準まで利用料金を引き上げ、保育士の待遇改善をすべきだ。加えて企業の参入促進も不可欠である。

丸川珠代・男女共同参画担当相が、選択的夫婦別姓の実現を求める意見書採択を阻止するよう文書で地方議員に呼びかけたことが、「ジェンダー平等に反する」と反発を招いた。そもそも夫婦別姓にはどのようなハードルや意義があるのか、改めて考えてみよう。

菅政権は、日本では株式会社が農地を購入することが認められていないという、時代遅れの規制の改革も進めるべきだ。兵庫県養父市では、国家戦略特区制度を活用して、全国で唯一普通の株式会社による農地取得が認められている。その取り組みを通じて、農地取得に関する改革の必要性と効果を考える。

雇用調整助成金は短期の不況時に雇用を維持するためには有効な仕組みであるが、感染防止のための自粛と消費拡大策の繰り返しで、長期化する休業者維持に、非常時の特例措置を漫然と延長することは妥当ではない。特例措置によって休業手当の金額が、本来のセ-フティーネットである失業手当を上回る逆転現象も起きている。人手不足の分野への雇用の流動性を高める措置も同時に検討するべきである。

安倍政権が掲げてきた2020年度末の待機児童ゼロ目標は、またも先送りとなる公算が大きい。その敗因が明確でなければ、政権が変わっても同じ失敗を繰り返すだけだ。検証すると「待機児童ゼロ作戦」には、前提として大きく3つの誤りが見える。児童福祉を抜本的に建て直すための発想とは何か。

政府の第二次補正予算案の大きな柱の1つは、コロナ休業者への直接給付の新設だ。企業に対して休業手当を給付する雇用調整助成金は使い勝手の悪さが指摘されるため、それを補足するためだ。しかし、それよりも失業手当を活用するほうが早いのではないか。

政府は新型コロナ対策として、全国民への10万円の給付を決定した。部分的にではあるが、ベーシックインカム(基礎的所得給付)政策が日本で初めて導入されたことになる。しかしそう考えた場合、今回の政策には致命的な欠落がある。
