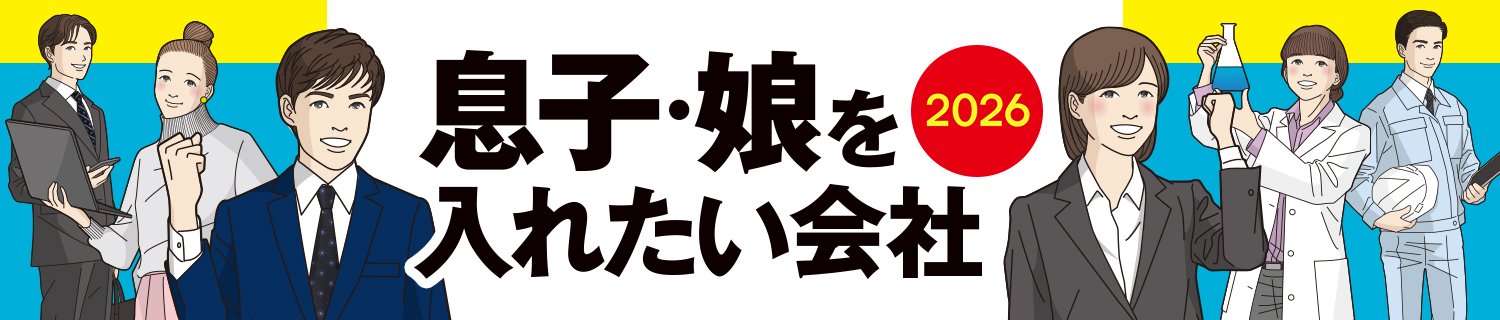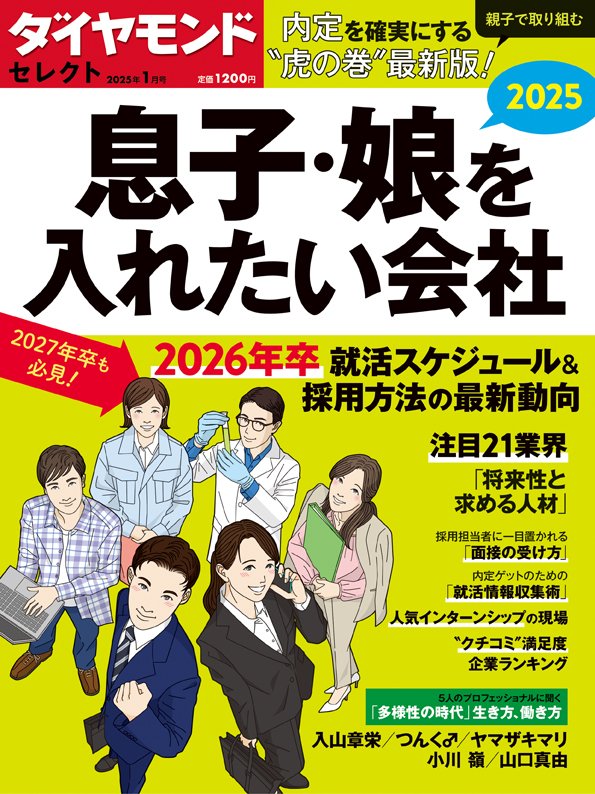フィンテック分野では、暗号資産のウォレットや個人向け商品開発に力を入れ、イノベーティブな企業文化の醸成を進めているところもある。
三井住友銀行、三菱UFJ銀行、みずほFGといったメガバンクでも、若手が社内ベンチャー形式で自由に提案できる環境づくりが進められている。中でも、三井住友銀行による総合金融サービス「Olive」はその成功例の一つだ。こうした風通しの良い社風は、今後の銀行業の変革を担う若手にとって大きな魅力となっている。
地方銀行でも人口減少に対応するため、新しい発想を取り入れ、口座維持のためのサービス改善に取り組んでいる。都市部への預金集中が進む中、地方での顧客維持戦略として若者の声を重視する傾向が強まっている。
銀行業界を志望する学生にとって重要なのは、「金利の知識」と「金融の歴史」への理解だ。
特に長期にわたる低金利環境から転換期を迎えている現在、変動金利と固定金利の特性を理解し、顧客に適切な提案ができる知識が求められる。
また、バブル期や不良債権問題の背景には、為替制度の変化や金融政策の推移が関係しており、1970年代以降の歴史を学ぶことで、金融業界全体の構造変化を読み解く力が身につく。
こうした知識を持つことは、面接でのアピールにも直結する。実際、多くの現役銀行員もこうした歴史を十分に理解していないケースがあるため、差別化の材料として有効である。
銀行業界では近年、プロフェッショナル職への報酬改善の動きが広がっている。有価証券のトレーダーや投資銀行部門など、直接的に利益をもたらす部門では専門性が評価され、給与水準の上昇が見込まれる。M&Aやコンサルティング、リレーションシップバンキングといった法人向け業務への関心も高まっており、実務スキルの重要性が増している。
地銀や信用金庫では、中小企業支援を通じた地域密着型のソリューションビジネスが広がっており、地元に根差した働き方を志す人にとってもキャリアの選択肢は広がっている。
出世を目指す場合、銀行では多様な部署での経験が求められる。特にメガバンクでは地方支店や本部、さらには海外勤務などを経て、企画部門や人事など全社的視点を持つ部署での活躍が幹部登用の要件となっていることが多い。
*この記事は、株式会社大学通信の提供データを基に作成しています。
医科・歯科の単科大等を除く全国757大学に2024年春の就職状況を調査。561大学から得た回答を基にランキングを作成した。上位10位以内の大学を掲載。就職者数にグループ企業を含む場合がある。大学により、一部の学部・研究科、大学院修了者を含まない場合がある(調査/大学通信)