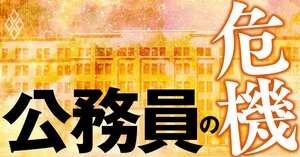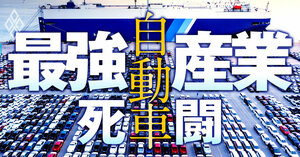せまいコミュニティで育てたいという
保護者のニーズがある
昨今、「多様性」という言葉が頻繁に使われていますが、多様性とはただ単に「さまざまな背景を持つ人々と交わる」ことだけを意味するのではありません。
公立小学校では地域に住んでいる様々なバックグラウンドの子どもたちと交流することになります。これはもちろん一種の多様性を経験する機会です。ただし、同時に少しもってまわった言い方になりますが、「いろいろな人と交流したいという意味の多様性を選ばないという意味の多様性」もあります。
「似たような価値観を持つもの同士のコミュニティの中で育てたい」という明確な意図を持つ保護者が増えているのは、これもまた「多様な教育の選択肢」の一つの現れであると言えるでしょう。
「できるだけ広く、全方位360度的に薄く」経験させるよりも、親として「ある角度60度分だけを子どもに深く経験させたい」と考える。例えば、「その私立特有の価値観」や「インターナショナルな環境」など、特定の方向性を深く追求することも教育のひとつの選択です。
少子化が進む公立小学校でも、豊洲のような人気エリアでは1学年5クラスもあり、毎年クラス替えが行われます。一方、私立小学校では1学年2クラス程度の小規模な環境です。
公立小学校が「浅く広い人間関係」を提供するのに対し、私立小学校では「深く狭い人間関係」を形成しやすくなっています。生きている限り、人間が出会える人の数は限られています。何かを選ぶということは必然的に何かを捨てることです。その限られた時間と出会いの中で、どのような濃密な関係性を築くかは個々の選好次第でしょう。
また、公立小学校が変化しているということも大きいでしょう。以前の公立小学校では、卒業式のあとに謝恩会もありました。また、町会などに属していれば、地域の夏祭りなどがあり、そこで子ども同士、保護者同士の交流も活発でした。
しかし、最近では、個人情報保護の観点から、連絡網の名簿づくりはおろか、卒業文集や卒業アルバムの作成さえ行わないところも出てきています。共働き家庭の保護者の負担を減らすため、PTA活動や、家族が参加するタイプの課外活動やイベントを廃止するところも増えています。コロナでその動きは一層加速しました。
その結果親同士の顔は互いに見えにくくなっており、学校への帰属意識も希薄になっています。