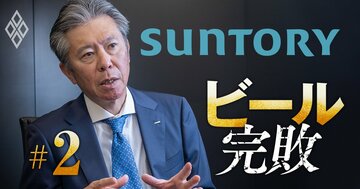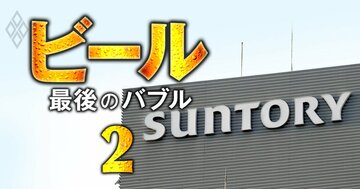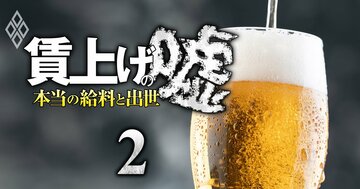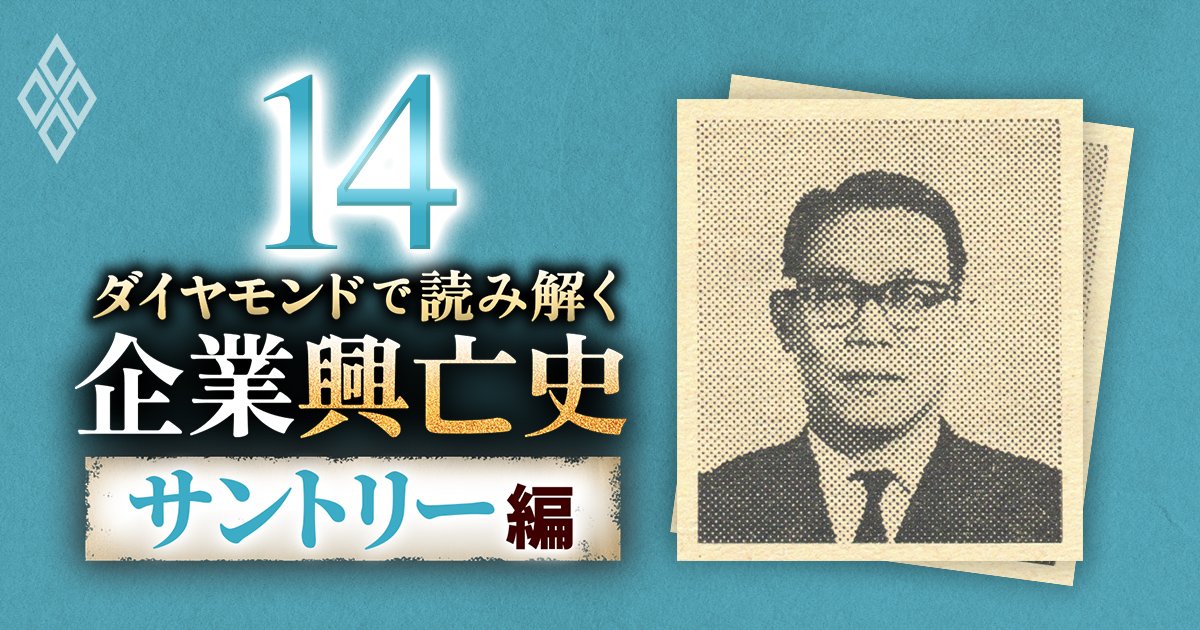
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』では、「ダイヤモンド」1967年2月20日号の特集『泡立つ“ビール戦争”業界地図は果たして塗り替えられるか』からの抜粋記事を前回から3回にわたり紹介する。中編の本稿では、サントリーの原三郎専務のインタビューを再掲する。原氏は大幅減に沈んだ1966年のビール販売について反省の弁を述べる一方、「撤退の意思は全くない」と強気の姿勢を示している。また、サントリーの必勝の方程式ともいえる「サントリー商法」の要諦についても明かす。(ダイヤモンド編集部)
サントリーがビール出荷減も
専務は「撤退の意思は全くない」
――1966年のビール業界は、麒麟独走、後発2社の大幅な出荷減となったが、まずその点から反省の弁を……。
原 昨年(編集部注:1966年)は、一番のかせぎ時である初夏に、サッポロ・朝日の合併話が持ち上がって、結局は破談に終わったが、この影響が痛かった。それと、取引の正常化が強く推進された。しかし、そのどちらの影響が大きかったかといえば、後者の方がうんと響いた。
今回の取引是正は、人気の強い銘柄、弱い銘柄に応じて、リベートなどの販売費、あるいは業務向けビールの値引き幅などに一定の制限を設けるやり方で出発した。ところが、全国一律にこの制度の適用を強行したため、地方では人気の薄い後発メーカーは大きな痛手を受けてしまった。
ウイスキー業界では、こういう場合、銘柄別のほかに地域別にもリベートに変化を持たせている。だから、弱い銘柄にしわ寄せがいく、というケースが少ない。取引是正はもちろん結構だが、今後は、もっときめの細かい処置を取ってもらわないと……。
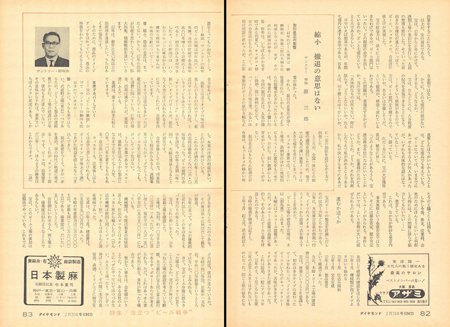 「ダイヤモンド」1967年2月20日号
「ダイヤモンド」1967年2月20日号
――結局、サントリーの66年のビール出荷は前年比6.1%減。当初の計画である前年比80%増という目標に比べると、相当の開きが出ましたね。この状況では、いつからそろばんに乗るかという確実な期待が持てませんが、今後の方針について……。
縮小、撤退の意思は、全くない。仮に、67年の出荷が引き続き思わしくなくても、拡大均衡、積極戦法を貫いていきます。