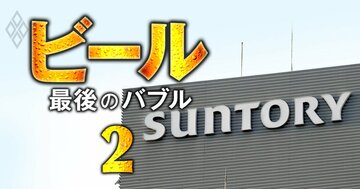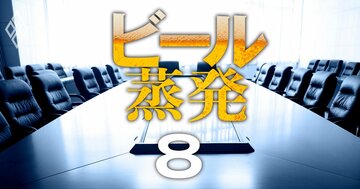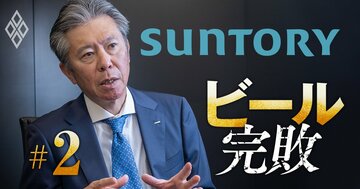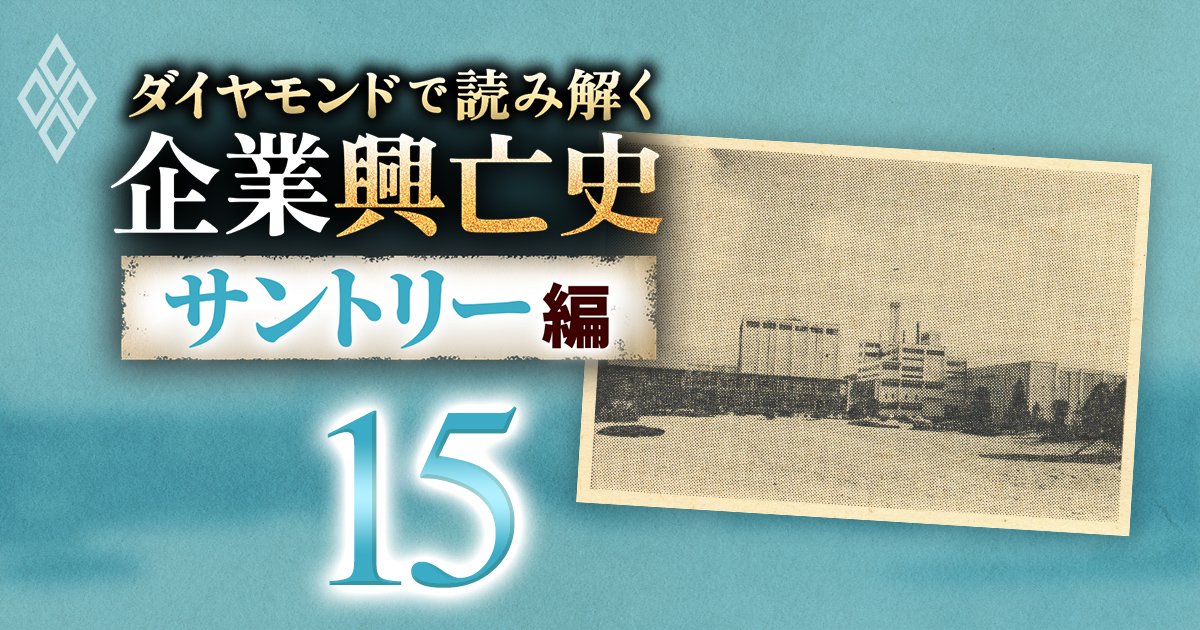
今春、サントリーホールディングスで10年ぶりに創業家出身者がトップに就任する“大政奉還”があった。1899年に「鳥井商店」として産声を上げ、創業120年の歴史を誇る日本屈指の同族企業、サントリーの足跡をダイヤモンドの厳選記事を基にひもといていく。連載『ダイヤモンドで読み解く企業興亡史【サントリー編】』では、「ダイヤモンド」1967年2月20日号に掲載された特集『泡立つ“ビール戦争”業界地図は果たして塗り替えられるか』からの抜粋記事を前々回と前回に続いて紹介する。後編の本稿では、“局地戦”に活路を見いだした、ビール後発組のサントリーと宝酒造による大手3社(キリンビール、サッポロビール、アサヒビール)への対抗策について明かしている。記事では、ビール市場を巡る戦いの「100年戦争」への突入も示唆している。(ダイヤンモンド編集部)
後発組の「大手3社路線」踏襲に限界
サントリーは「集中販売方式」に軸足
ヨーロッパやアメリカでは、ナショナルブランドと、ローカルブランドが共存している。小規模メーカーは、特定地域の市場をガッチリ押さえ、その風土に適した特色ある製品を売り物にしている。また一つのメーカーが、高級品から大衆品まで、あるいは味やアルコール濃度の異なるものまで、広く手掛けているケースも多い。
それに対しサントリーや宝がとってきた方法は、簡単にいえば、大手3社の路線の踏襲である。全国販売、宣伝も広範囲に及ぶ。これでは、経費がかさんで体力が持たない。
宝では、今後の販売方針について、「宣伝、拡販費というものはある一定の水準を超えると大きなロスが出る。今後は、全国一律のキャンペーンでなしに、地区ごとの効果的な販売を考えていくつもりだ……」と、語っている。
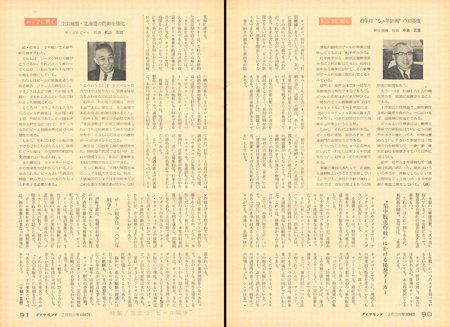 「ダイヤモンド」1967年2月20日号
「ダイヤモンド」1967年2月20日号
サントリーでも、最近は東京、大阪など大都市中心の“集中販売方式”に切り替えつつある。