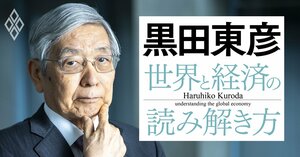資産があるのは“生まれた時から当たり前”であり、豊かさが「空気」となっています。何かに耐え忍んだ経験もなければ、作り上げたという実感もなく、使うことが中心となってしまうのです。
結果、「資産は自分の努力の成果ではない」ため、心理的な所有感も責任感も希薄になります。海外留学をさせてもらうのも普通で、別荘、むしろ自宅自体が何カ所もあるのが当たり前です。
そんな中で事業が傾いたり、承継が失敗したり、親族内のもめ事に巻き込まれたりしたとき、“崩壊”のスピードは一気に加速するわけです。
家訓も教育もなく
「黙って引き継げ」には無理がある
最近では「家族憲章」といって、高額な報酬を支払い、家系の価値観や資産方針を言語化する富裕層も出てきています。
冒頭で述べたように、もともと日本の地主系の富裕層においては、それに相当する“家訓”が暗黙の了解として存在していました。
「先祖代々の土地は、絶対に売るな」
「本家は長男が守るもの」
「家の名に泥を塗るな」
これらは紙には残っていない家族憲章であり、子や孫は空気のようにそれを受け継がされてきていたわけです。
ですが、ここ最近は事情が異なってきました。
都市部では相続税の土地評価額も上がり、不動産のままでは納税資金を捻出することができません。
それでも「売るな」と言い張る親と、「売らないと税金が払えない」という子や孫がぶつかるわけです。また、ジェンダーフリー的な世の中なので、「本家は長男が守るもの」という価値観も揺らいでいるでしょう。
ここに、“美学”と“現実”の板挟みが起きているのです。
「資産を守る」とは
売らないことでも、渡さないことでもない
そもそも、相続税は「相続のたびに資産を細らせる」よう設計されています。
例えば、23区内にファミリータイプのマンションや駐車場、自社ビルなどをいくつも保有している資産100億円規模の地主の場合、相続税は50%超に上ります。代替わりのたびに十億円単位の納税が発生し、資産はどんどん小さくなってしまうのです。