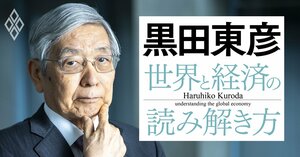さらに長子相続ではなく、兄弟姉妹で均等に分けるとなれば、土地の分筆・共有化・売却が避けられません(その分、土地が売却放出されて私たちが家を買えるという見方もできますが)。
実際、「相続対策はきっちり税理士などの専門家に相談しているから大丈夫」などと語っていた地主家系でも、相続発生後には半分以下の資産規模になってしまったという例をゴマンと見てきました。
つまり、資産を守るという価値観そのものが、現代の制度と衝突しているのです。
「資産を守る」とは、単に売らないことでも、誰にも渡さないことでもない。
むしろ、「税と実務に耐え得る仕組みを作ること」こそが、本当の継承ではないかと考えます。
・ 生前の資産分割や法人化
・ 共有ではなく“機能分担”による承継設計
・ 家族で資産に関する対話の場を持つ(憲章でなくとも、“物語”を共有する)
こうした仕組みを作らなければ、どんなに立派な土地や資産も、2〜3回の相続であっという間に“形見レベル”にまで細ってしまうのです。
徳川家に学ぶ
“家系マネジメント”の力
家系を守っていくヒントは、歴史に学ぶこともできます。
資産家は3代で普通の家に逆戻りすることが多い一方で、江戸幕府を築いた徳川家は15代・260年以上にわたって江戸幕府を存続させました。
その背景には、まさに前述の仕組みがあったということを思い知らされます。
・ 武家諸法度、家康の遺訓に始まり、将軍職の役割・価値観を代々で明文化
・ 徳川家康は後継者(秀忠)を早めに将軍にし、自分は“大御所”として実権を握った
・ 年中行事や儀式を形式美として継承
要するに、「人物」ではなく「仕組みと形式」で継承を支えていたのです。
この仕組みがあるからこそ、個々の将軍に多少問題があっても、家系としては機能し続けたわけです。