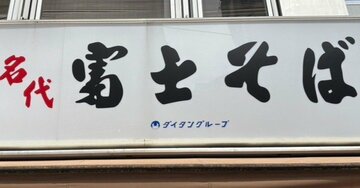「価格に敏感」か「量重視で価格に鈍感」か客をふるい分ける
ブライアン・マクマナス氏が発表した学術論文『寡占市場における非線形価格設定:スペシャルティコーヒーの事例』は、まさにこの現象を理解する上で、極めて重要な示唆を与えてくれる。
論文は、企業が顧客一人ひとりの好みや支払意欲を正確に把握できない状況で、どのように価格と品質(今回の場合はサイズ)のメニューを設計するかを分析している。
企業は価格とサイズの選択肢を複数用意することで、顧客に自らのタイプを表明させる「スクリーニング(ふるい分け)」と呼ばれる戦略を用いる。価格に敏感な顧客と、量を重視し価格に鈍感な顧客を、異なる商品(サイズ)へと巧みに誘導するのだ。
この過程で、企業は製品の設計を意図的に「歪める」ことがあるとも論文は指摘している。さらに、次のような記述もある。
《企業は、より大きなサイズを購入する顧客からより多くの利益を吸い上げるため、その誘因として、小さなサイズの製品を意図的に『小さすぎる』ように設計することがあるのです》
この視点を当てはめると、セブンのレギュラーサイズが97gとやや物足りない量に設定されているのは、偶然ではないのかもしれない。価格に敏感な層を安い単価で引きつけつつ、量を求める顧客には割高なラージサイズを選ばせるための、計算された「歪み」である可能性がある。
ラージサイズが割高なのではなく、レギュラーサイズが戦略的に「小さく」されているという解釈だ。
冷静に考えれば、一杯ずつ豆から抽出されるコンビニコーヒーが提供してくれる価値は、単価だけで測れるものではない。淹れたての豊かな香りと深い味わいは、工場で生産される缶コーヒーとは一線を画すものであり、日々の生活に小さくても幸せな潤いを与えてくれるものだ。
ローソンのMサイズの「異常値」に憤るよりも、Sサイズやメガサイズが、それぞれの顧客ニーズに合わせて戦略的にお得な価格で提供されているのだと捉え直すべきなのかもしれない。
セブンのラージサイズに不満を抱くのではなく、レギュラーサイズが価格にシビアな人々のために特別なディスカウント価格で提供されているのだ、と感謝することもできる。
結局のところ、提供される情報の意味を理解し、自らの価値観に基づいて最適な選択をすることこそ、賢い消費者の姿なのだろう。
記事初出時、ローソンとファミリーマートのアイスコーヒーの価格を誤り、「税込価格」にさらに8%を上乗せした金額を記載していました。一覧表と本文の数値を正しいものに訂正しました。
(2025年7月28日 11:00 ダイヤモンド・ライフ編集部)