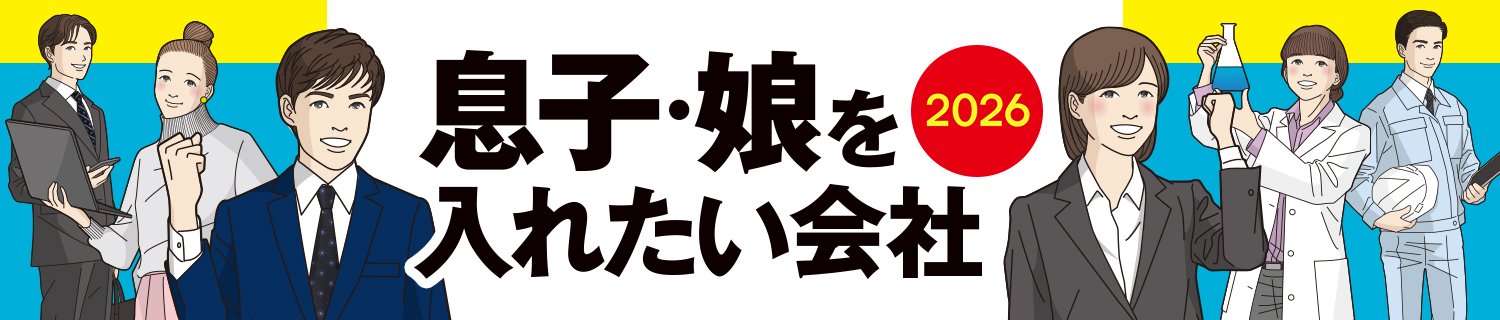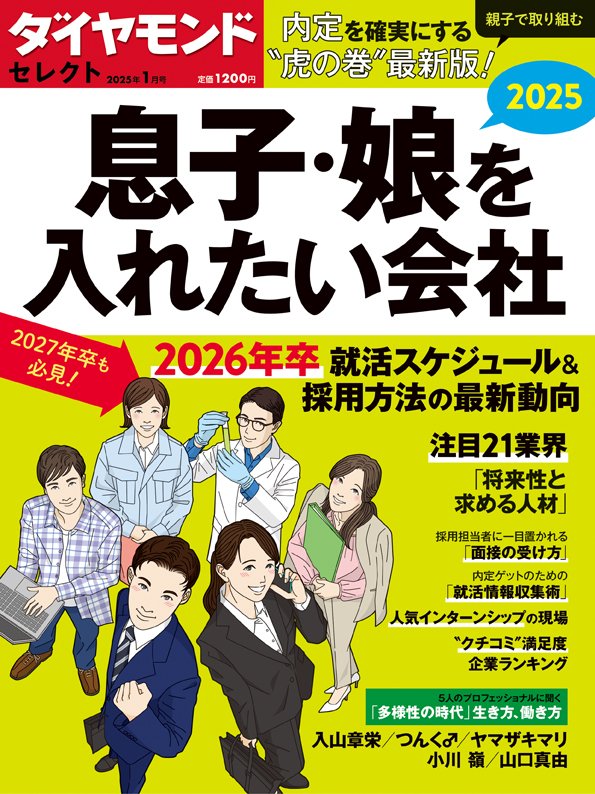リモートワークの鍵は
「納得感のある運用」
出社・リモートのいずれにも振り切れない「制度過渡期」を示すコメントも散見された。制度上はリモートが可能であっても、雰囲気的に利用しにくいという声、紙文化や物理的な席不足など環境面の制約からリモートが難しいという声、さらには部署や上司によって運用に差があるという指摘もあった。
制度そのものは存在しても、文化としては定着しきれておらず、働く人々が模索しながら利用している現状が浮かび上がっている。
「リモートワークをして良いことにはなっているが、コロナ禍の風潮は消え、気軽にリモートワークできない雰囲気がある」(事務、「個人の裁量で出社・リモートを選択可能」と回答)
「会社の制度としては、一定の評価グレードに達すれば週2日のリモートをさせてもらえますが、社内を見ると出社派が多い気がします。私もリモートしたいなと思う方ですが、社員対応や、紙書類の対応があるので、何だかんだと出社することに…もう少しDX化やペーパーレスにならないと、リモートは難しいです」(人事、「週3出社が義務」と回答)
「出社しなくても仕事できるのに…と思いながら満員電車に揺られて出社。営業はリモート無しで、管理系の部署は在宅OK。同じ会社なのに部署で差があります」(その他〈営業〉、「週5日出社が義務」と回答)
リモートワークをめぐる声から浮かび上がったのは、制度そのものの有無以上に「納得感のある運用」が鍵であるという点である。
出社日を設けるのであれば「出社で得られる価値」を実感できるようにすることが必要であり、リモートワークを推奨するのであれば「リモートでも不安なく成果を出せる環境」を整えることが求められている。不明確な制度運用や説明不足は、不公平感やリモートワーク取得の控えにつながってしまう。
リモートワーク制度は単なる勤務ルールではなく、社員のライフスタイルや働き方に対する企業の考え方を示すものである。各社で方針が多様化する中、企業には制度の意図や運用方針を丁寧に伝える姿勢が求められているといえる。