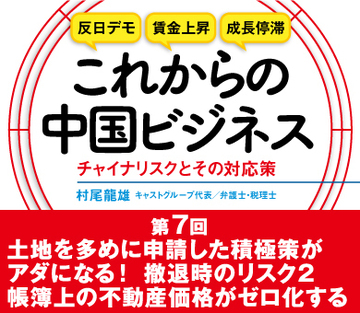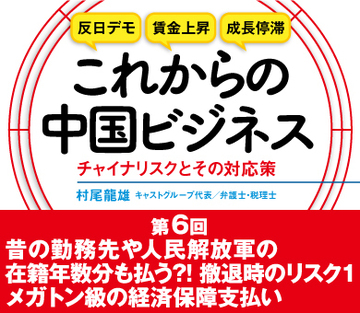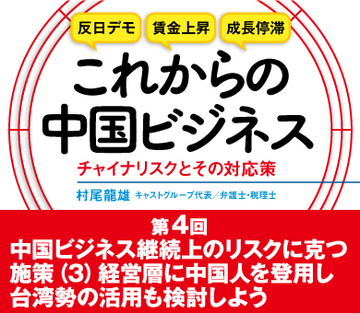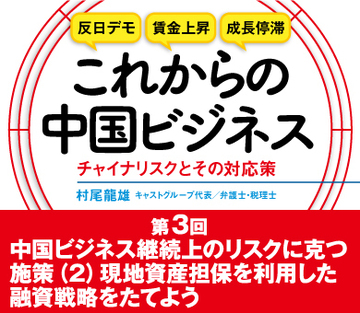もっとも、この「棚上げ合意」は、わずか1分程度であろう首脳同士の会話のみに立脚しているうえ、棚上げ期間やその後の具体的解決法が明示されていない点で、合意というには未成熟だとの批判があります。中国側もこの首脳同士の会話ではなく、次に紹介する別の、鄧小平氏による「棚上げ合意」にその根拠を求めます。
もうひとつ棚上げ合意の根拠として挙げられるのは、1978年8月の日中平和友好条約締結に際して、北京で鄧小平氏が園田直外相と会談したときに、「この問題はこれから先も当面脇に置いておこう」と提起した、というものです。さらに同年10月、同条約批准書交換のため来日した鄧小平氏は、福田赳夫首相と会談した際にも「棚上げ」を提起し、続く日本記者クラブの会見でも次のような趣旨で明言しました。
「釣魚島(尖閣諸島の中国名称)の問題については、大局を重視し、国交正常化が実現した時には、双方この問題には関わらないようにしましょう。この問題について協議が整うとは思えず、触れないことが賢明ですし、この問題については少し棚上げしておいても差し支えないでしょう。われわれの世代の知恵では不十分だが、次の世代はきっとわれわれより聡明であり、いずれ、みんなが受け入れることができる良い方法を発見し、この問題を解決することでしょう」。
この発言は当時の日本政府の了解のもとに発せられたものであるから、ここにおいて「棚上げ合意」が形成された、と中国は主張しています。日本政府は「棚上げ合意」を否定する立場ですから、この鄧小平氏の発言も日本政府が了解したものではなく、一方的に発表したものにすぎないと反論しています。
日本の主張は国際的には通りづらい?
両論とも水掛け論だ…そう感じる読者の方も多いのではないでしょうか。「棚上げ合意」の有無をどのように捉えるべきなのでしょうか。
持論を述べさせてもらえば、仮に明確な「合意」はなかったとしても、日本政府は過去の継続的態度に鑑みて「棚上げ合意があった」と認めざるを得ない、と考えます。決して中国へ迎合するわけではなく、一法律家として以下のように考えられるからです。
英米法には「禁反言(estoppel)」という考え方があります。これは「何らかの行為によってある事実の存在を主張した者に対して、その主張した事実に反する主張を禁止する原則」(英米法辞典参照)です。これと同じような考え方(禁反言)は日本でも民法の権利濫用(民法第1条第3項)を根拠として認められていますし、中国でもそうです。
この考え方を、尖閣問題にあてはめて考えてみましょう。日本政府が「棚上げ合意」は一切存在せず、尖閣諸島について領有権問題すら存在しない、尖閣諸島は歴史的に見て日本固有の領土であると考えてきたのであれば、その実効支配を対外的に表示するなんらかの行為を見せるべきだったのです。たとえば、1980〜1990年代の中国が脆弱で日本の助力を必要とする時代、特に1980年代の中曽根--胡耀邦蜜月時代に、ドンドン助力を与える代わりに、灯台や船着場を建設して公務員を常駐させるなどすればよかったのです。