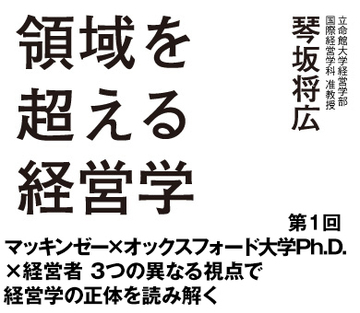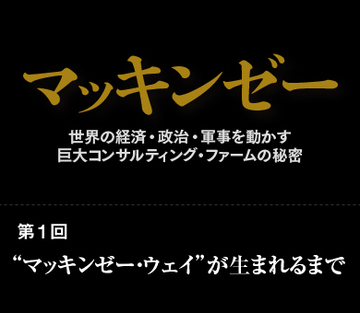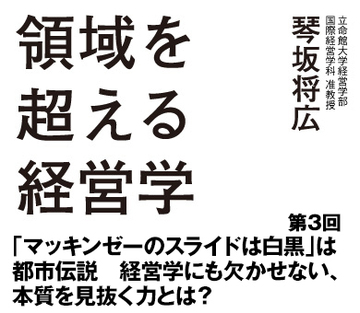短期間で研究を成功に導いた2つの勝因とは
琴坂 結果的には3年くらいですよね?
安宅 だいたい3年半強で出ました。でも、研究そのものは半年くらいで当たりましたね。
琴坂 それは、運が良かったからですか?
安宅 半分は運で、半分は技だと思う。運を除く勝因には、2つあったと考えています。1つは、思いつくアプローチをコミッティーと相談した時点で詰めたこと。各分野のエキスパートである彼らと話すことで、筋が悪そうだと思われるものを事前にすべて切ってしまいました。
もう1つ、筋がいいと思われるアプローチでも考えられるオプションはたくさんあったので、それをまさに「MECE(ミッシー)」に、つまり決め打ちせずに取り組んだこと。5個、7個、10個と、考えられる太筋のオプションを、まずダブりもモレもなく拾って“当たり”をつけて、そこから感度のいいところをさらに深掘るというアプローチを取りました。
琴坂 分析的かつ論理的に取り組んだんですね。
安宅 そう。論理的にここしか当たりそうもないよねと絞り込むのも1つの方法だと思う。でも、僕の研究でそれを行うのは、危険すぎると思っていたからね。
琴坂 なるほど。安宅さんは自然科学で、私は社会科学ですよね。実は社会科学の場合、自然科学のように、正しさが1つ存在して、それを再現できるかどうかという形ではないことが多いです。
自分の博士研究では、いまの経営学者たちが、私が研究している課題をどのように探究していて、彼らがどこまでわかっていて、何をわかっていないかを掴んでいくプロセスが本当に重要でした。
それをある程度掴んだあとに、私が自分独自の研究で実証しようとしていることに、果たしてバリューがあるのかということを確認すること。たとえば、その分野の重鎮、キーパーソンに意見を聞いて研究の内容を調整する作業のほうが、実際の実証研究よりもはるかに重要だったと思います。
安宅 それは僕も同じだと思う。その設定には相当頑張りました。これなら当たるだろうというテーマであり、かつ意味があるもの、しかも答えを出せる見込みがある程度あるものを選ばなければいけないからね。グッド・クエスチョンを発見すること、それはもう絶対なんです。
琴坂 ある意味で、冷酷ですよね。
安宅 そうだね。何かに答えなければいけないんです。最後は1本のディサテーション(dissertation:博士論文)にならないといけないから。いま(博士)学位の価値が揺らいでいるよね。こういう時期にこの議論をしていること自体が、何となくシュールだね(笑)。
琴坂 そういうつもりはまったくなかったんですけどね(笑)。