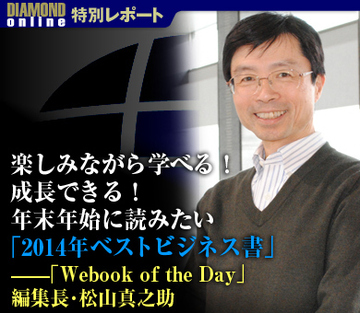山本夏彦も愛読していた
実はスゴい子ども向けの本
夏休みは、まさに絶好の読書の機会でもある。出版業界では大型連休の前になると、入門とタイトルが付けられた学習書、解説書を売るよう書店店頭でのプロモーションを強化する。休みの時間を使っての勉強、教養を深めようという根強い需要があることを知っているからだ。
 夏休みこそ教養を深めたい。そんな人にオススメなのは、実は子ども向け学習マンガ。実は、大人向け入門本よりも、遥かにクオリティが高く、分かりやすい本がたくさんある
夏休みこそ教養を深めたい。そんな人にオススメなのは、実は子ども向け学習マンガ。実は、大人向け入門本よりも、遥かにクオリティが高く、分かりやすい本がたくさんある
しかし、その気持ちに応えるだけの本に出会うことができるかが最大の問題である。書名に「入門」と謳っていても、それは著者や出版社の「ええかっこしい」であることも多く、木で鼻をくくったような、よく分からない解説に、何かを学びたいという最初の意気込みもいつのまにやら雲散霧消、貴重な夏の日が浪費されていく−−そんな経験は誰もがあるのではないか。
この夏は、いつものヘタは打ちたくない。そんな人に、ぜひとも手にとってもらいたい本がある。子ども向け学習マンガである。
「およそ天下に五枚で書けないことはない」。ここでの「五枚」とは200字原稿用紙のことなので、1000文字でなんでも伝えることができると豪語しているのは、世の偽りを鋭く難じて絶大な人気を誇っていたコラムニストの山本夏彦氏。氏は子ども向けの教科書を愛読していたという。
なぜか。よく考えると、子ども向けの教科書にはいくつもの「手に取るべき理由」があることが分かる。
何よりもまずは「子どもにも分かるようにやさしく書かれている」ことだ。逆に言えば、大人向けの入門書はレベル設定が高すぎるのである。恐らくは、「高校卒業程度の知識はあるだろう。なれば大学の一般教養レベルの内容にして、専門書に繋がるようにしよう」−−大人向けの入門書は、そういう基準で入門編と想定しているフシがある。それは書き手や編集者の力量と想像力の限界であり、子どもレベルの知識のない読者は相手にしないという、いやらしい根拠のないプライドみたいなものでもある。
しかし、大人であろうが、有名大学を優秀な成績で卒業していようが、苦手なこと、分からないことはたくさんある。その「分からない」こととは、多くの場合は中学生レベルの知識から欠落しているのである。世の中の森羅万象を無理矢理、義務として教えられるのは中学生の時代。ここで苦手意識をもったら、その後は学ぶ機会はなくなる。つまり、欠落している知識は中学生から作り直す必要がある。